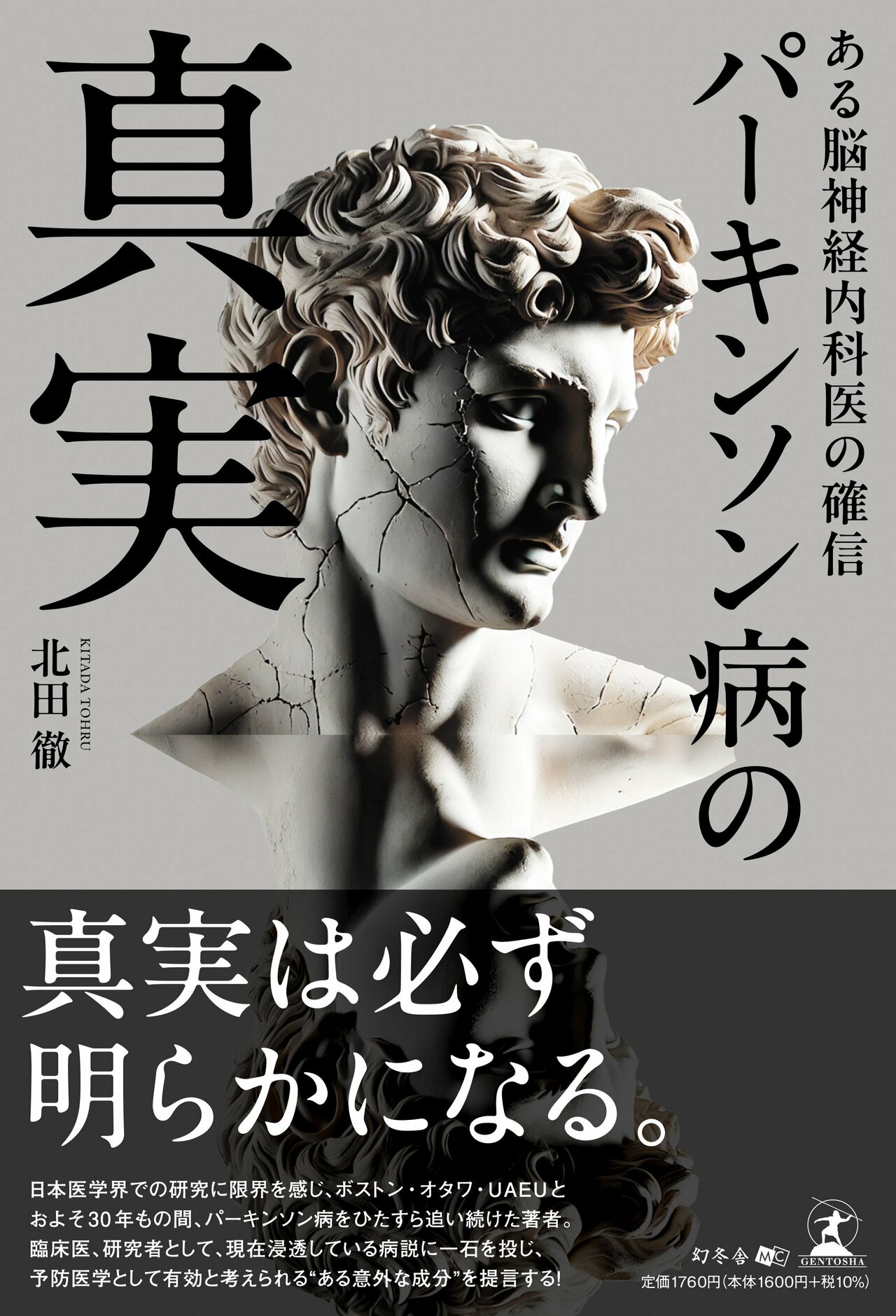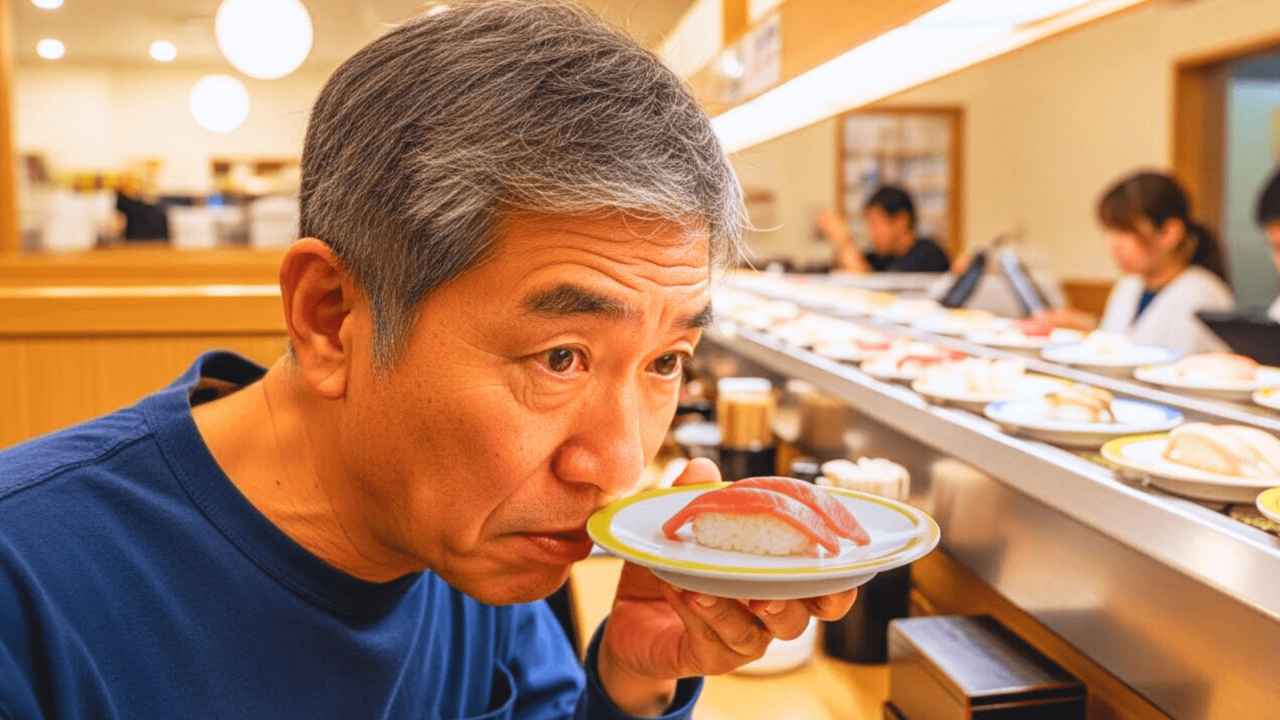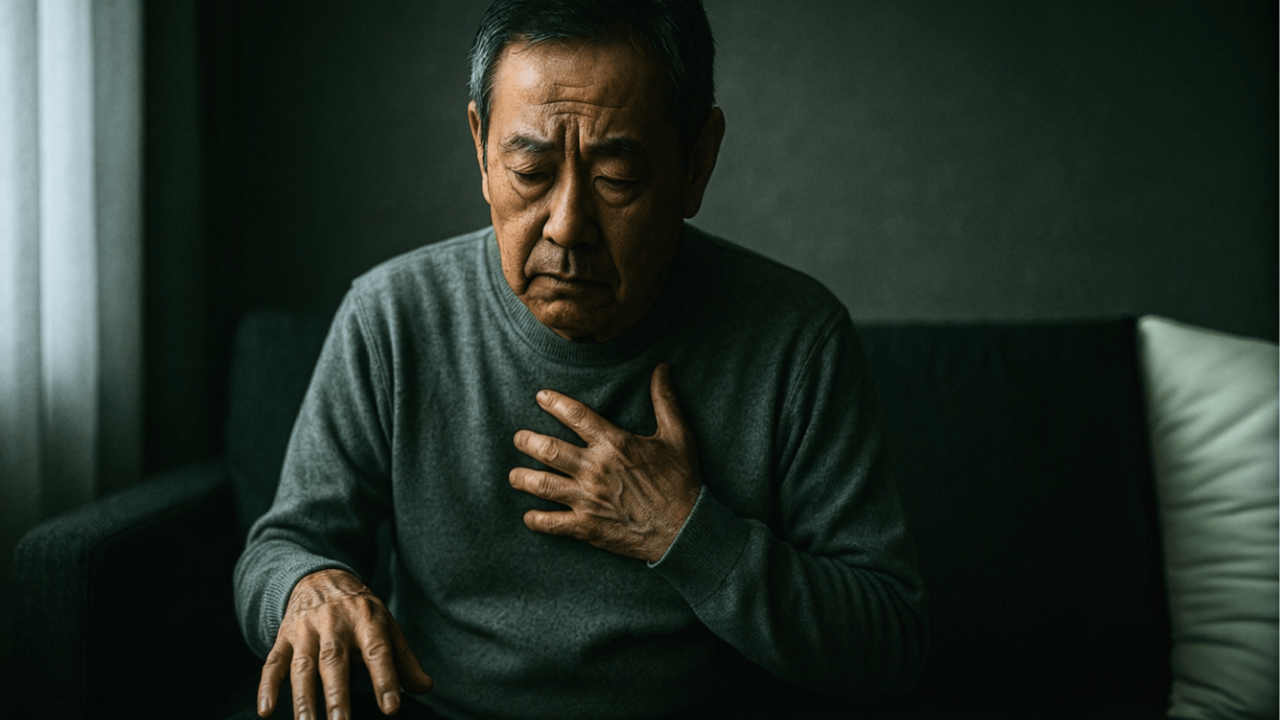第1章 パーキンソン病の基礎知識
患者様や一般の読者を対象としたパーキンソン病に関するわかりやすい良書はたくさん刊行されていますので、本書ではパーキンソン病に関する基礎知識に一通り触れるに留めます。一方、1800年代にまで遡る疾患の歴史や病因論に関しては、本書で少し踏み込んで概説したいと思います。
パーキンソン病とは
パーキンソン病は振戦(ふるえ)、筋固縮(筋肉の緊張度が増す)、動作緩慢(動作が鈍くなる)を3徴とし、さらに姿勢反射障害(転倒しやすくなる)を含めて4徴とする運動障害が主症状の神経変性疾患です。
運動症状の他に、嗅覚の低下、便秘、発汗異常、頻尿、起立性低血圧、易疲労性、むずむず脚症候群、睡眠障害、また不安、うつ、アパシー(意欲や感情の低下)、認知障害、幻覚などの精神症状といった非運動症状が起こることもあります。
これらの運動症状は錐体外路症状とも呼ばれます。注意すべきは「錐体路」と「錐体外路」の違いです。「錐体路」は大脳皮質から始まる運動神経伝達路をいい、ここに障害が生じると症状として麻痺が起こることがありますが、パーキンソン病ではこのような麻痺は来しません。
これに対し「錐体外路」はこの錐体路以外の運動の指令を遂行するための経路の総称で、大脳深部の基底核を中心とする複雑な経路であり、運動全体の調節をしています。この協調がうまくいかないとパーキンソン病で見られるような運動症状が起こります。
そして、その運動の調節を指示しているのが「ドパミン(dopamine)」と呼ばれる神経伝達物質です。中脳黒質のドパミン産生神経細胞で作られたドパミンが、大脳基底核の主要な構成要素である線条体に送られます。さらに線条体から運動調節の指令が大脳皮質へ伝わり、全身へ運動の指令が伝達されます。
黒質神経細胞の減少による線条体でのドパミン不足(別の神経伝達物質アセチルコリンが相対的優位になる)が病気の本態と考えられます。
パーキンソン病は中年以降での発症が多く、高齢になるほど発症率および有病率が増加し、日本では有病率は10万人に100 人~150人、65歳以上では10万人に1000人くらいです。40歳以下で発症することもあり、若年性パーキンソン病と呼ばれますが、家族性の場合もあります。