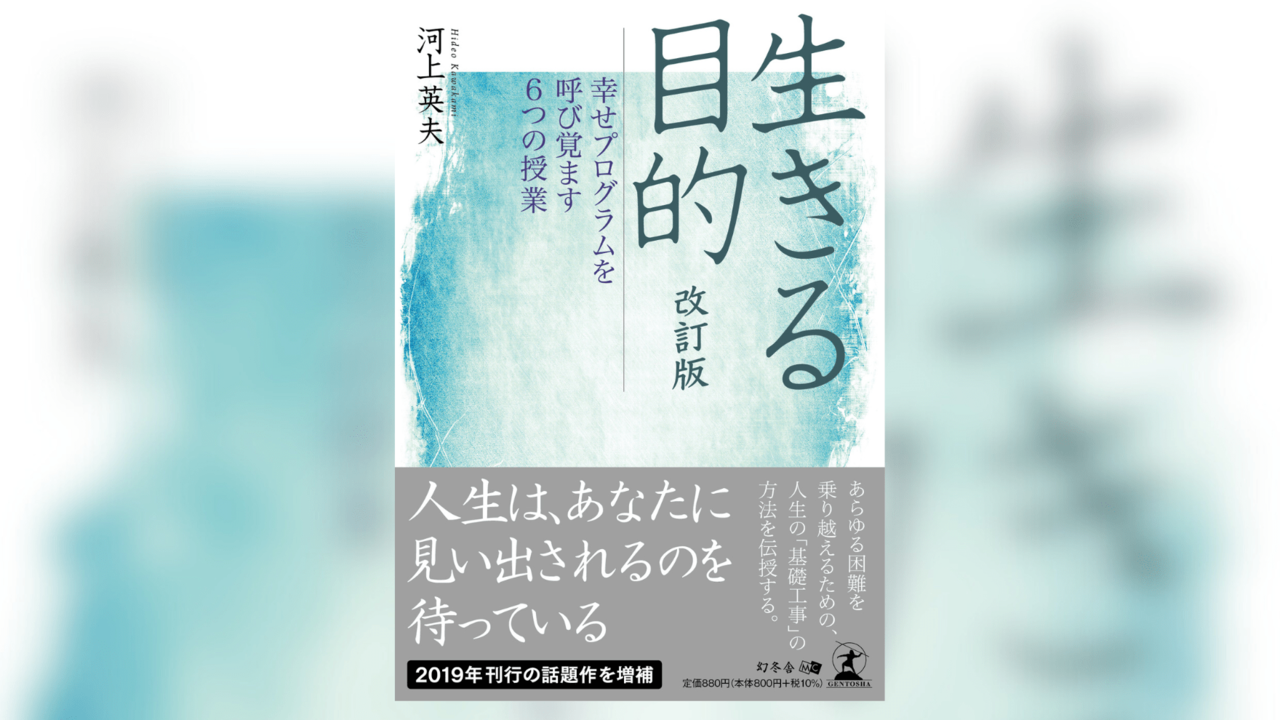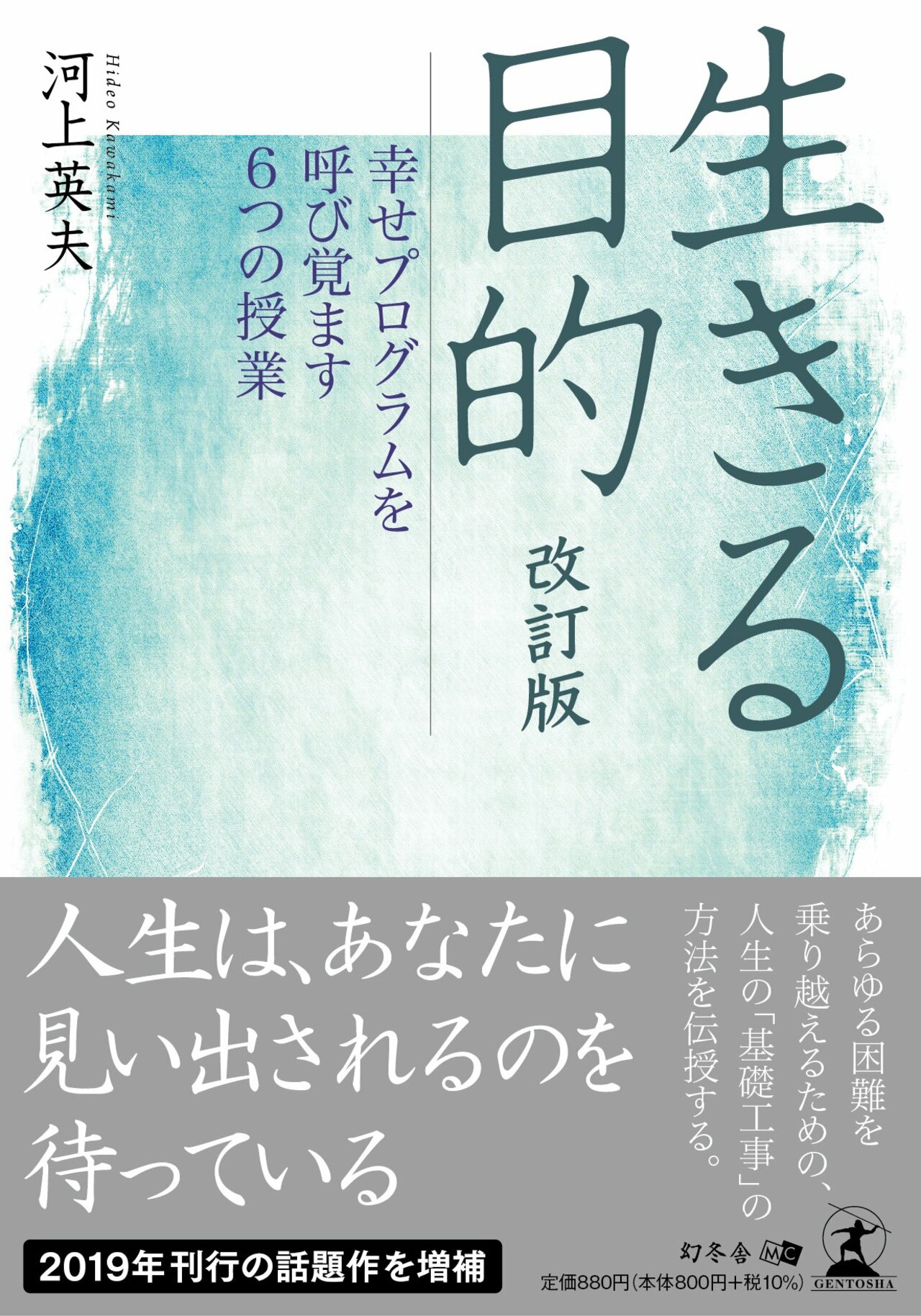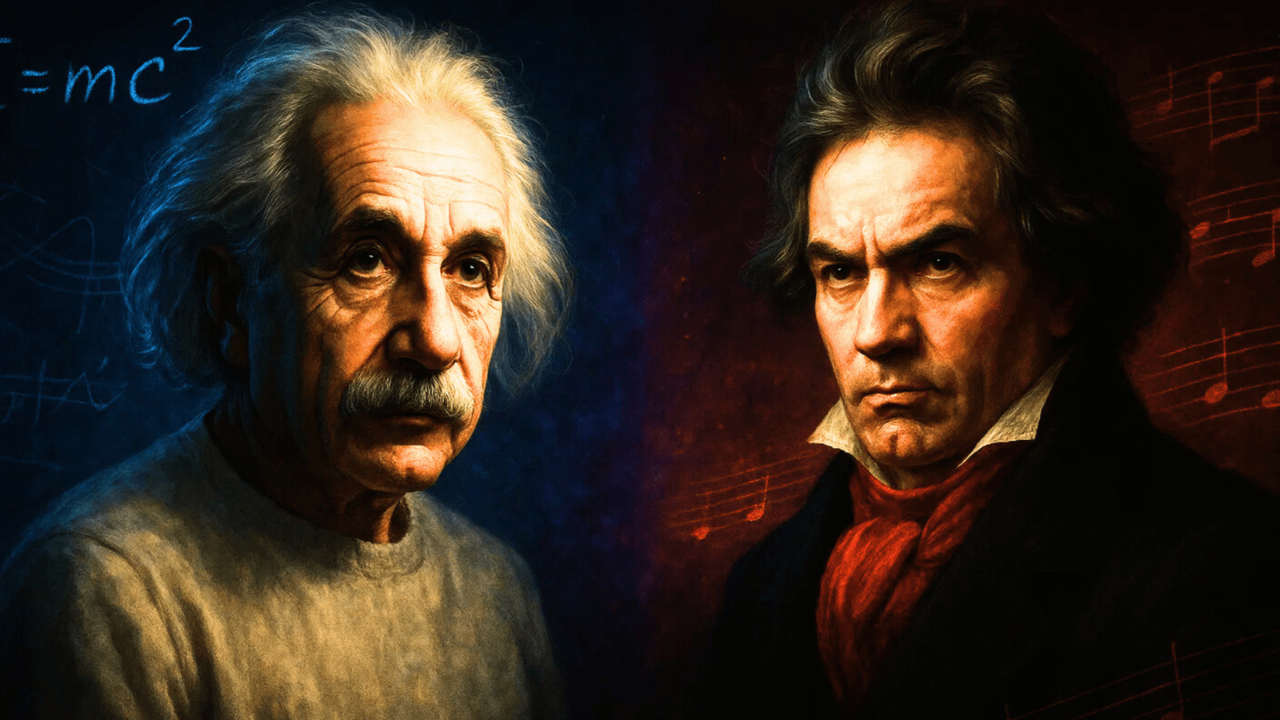【前回記事を読む】"もう限界かもしれない"と感じたとき――生きづらさを抱える人に伝えたい『生きる目的』を正しく把握する方法とは
はじめに
一 なぜ私が「生きる目的」を書くようになったか
今考えると不思議であるが、生きるということに対して強い執着心はなかった。それは私だけではなかったと思う。当時の軍国主義教育のせいかもしれないが、我々の多感な青春時代に、戦争という状況が訪れたために死に対する感覚が麻痺してしまっていたようにも思われる。
ただ、この時代のことが土台となり、戦後になって平和をとり戻すと、人類は、生存競争のためには他を殺さなければ生きていかれないという必要悪がある醜い動物のように思えるようになって、生きることの目的がわからなくなり、このまま漫然と生きていることに意味があるのだろうかと疑問を抱くようになった。
そこで、手当たり次第に人生論や哲学書を読み漁って一応の納得はできたが、私には常に満たされないものが心の底に残っていて釈然としなかった。
五年制の旧制中学で勉強したのは動員されるまでの二年生までと、四年生の夏に敗戦を迎え動員解除になり秋から復学して五年生で卒業するまでの一年ほどだったので、実際に勉強したのは三年間だけであった。
しかしながら、その間に戦争という稀に見る体験をしたので、平凡な学生生活では得られなかったであろう私の人生観が芽生えていったことは確かだ。
郷里が四国だったので、旧制中学の卒業後は高松経済専門学校(後の香川大学経済学部専修科)に入学したが、高松市内の校舎は空爆で焼失したため校舎は善通寺の砲兵第十一師団の兵舎であった。
二 西田哲学との出会い
当時の学生は弊衣破帽(へいいはぼう)の風習が残っていて貧乏学生にとっては生活しやすかったが、衣食住全てが最低で、なるべく腹が減らないようにと下宿で本ばかり読んでいた。
そんな時、哲学の講義において西田幾多郎(にしだきたろう)が著した『善の研究』の解説を受けた際に、急に人生がバラ色に変わったことを今でも鮮明に覚えている。
まさに目からウロコが落ちたとはこのことで、早速、友人から借りた『善の研究』を下宿で読みはじめたが、興奮して寝られず知らぬ間に朝が来ていたことが度々あった。
当時古本屋に二百円で売っていた『善の研究』が買えなくて、とうとう写本してしまったほどである。それまでの私はどちらかといえば暗い性格であったが、自分でも自覚できるほど明るい積極的な性格に変化し、西田哲学との出会いに欣喜雀躍(きんきじゃくやく)したことは今も忘れ難い思い出である。
その後、社会人となって購入した『西田幾多郎全集』全十九巻は私の座右の本となった。