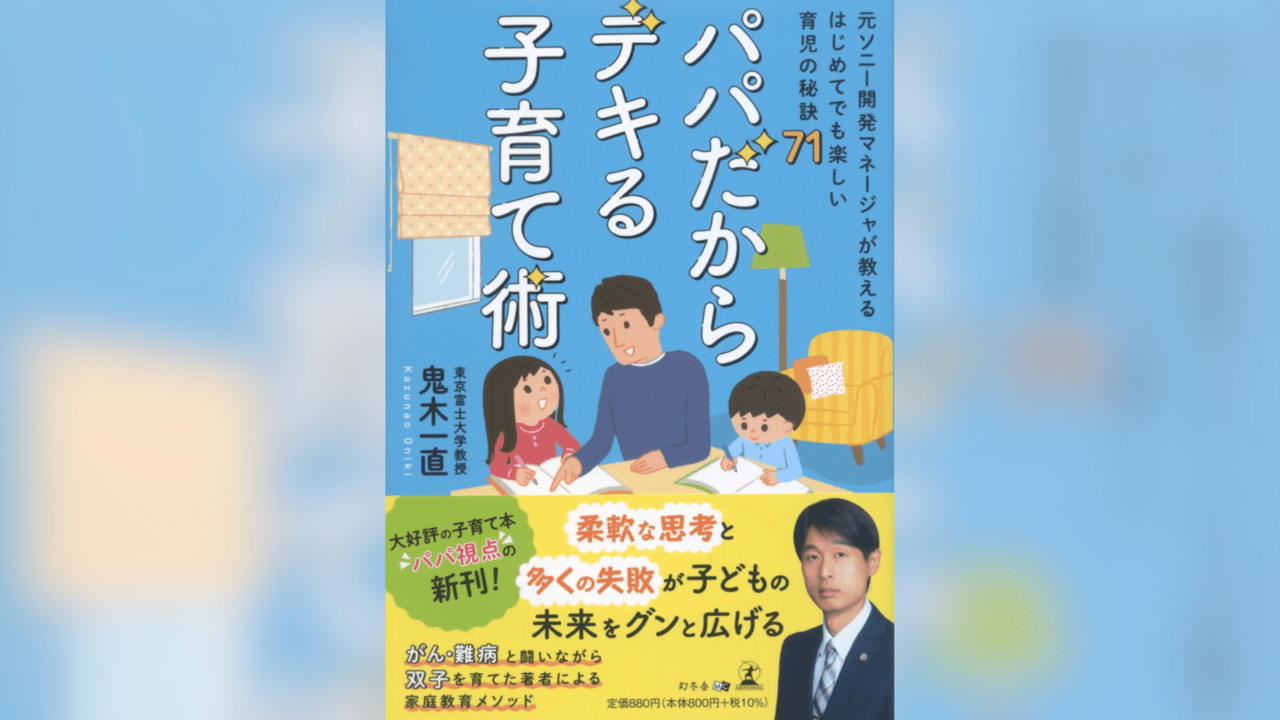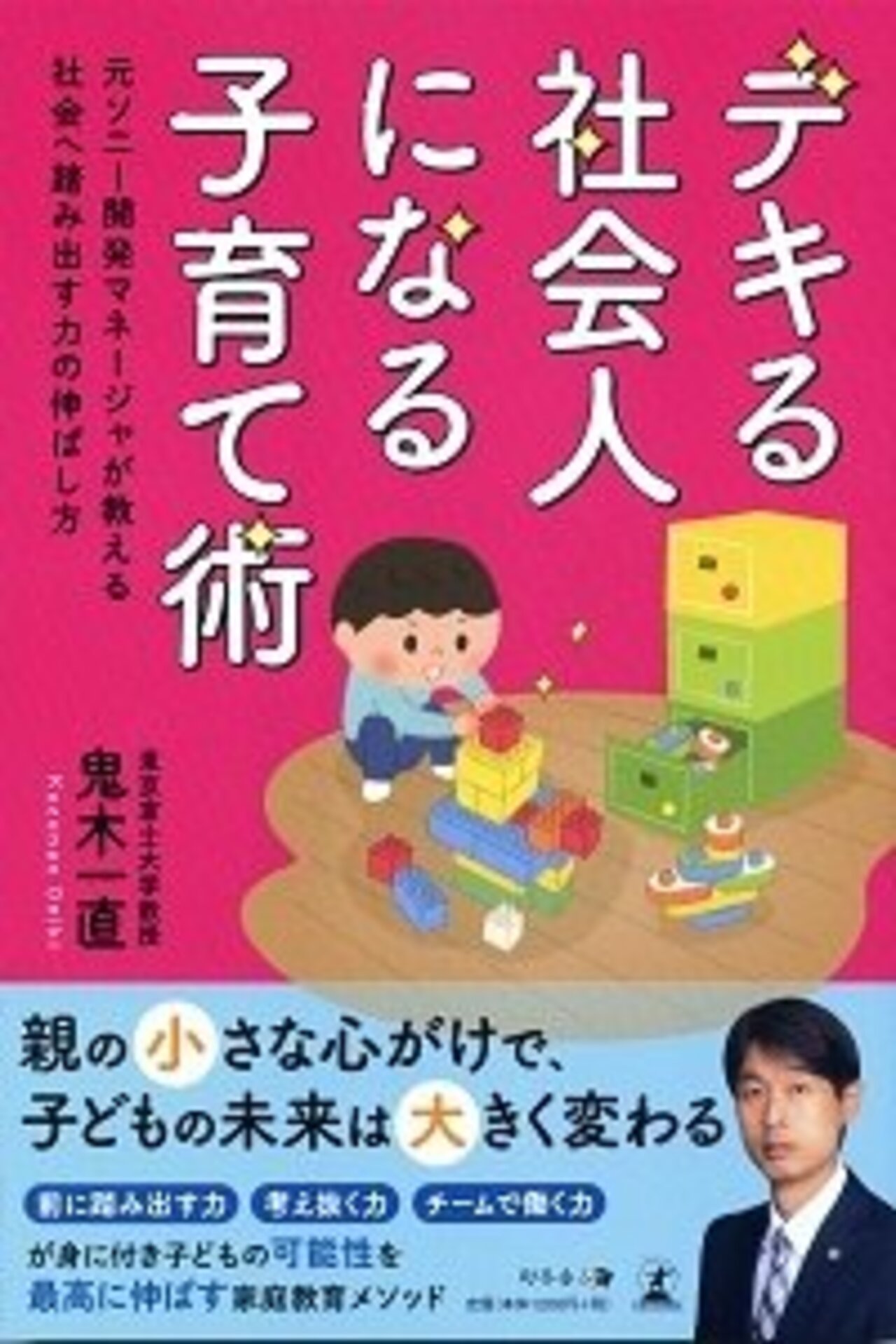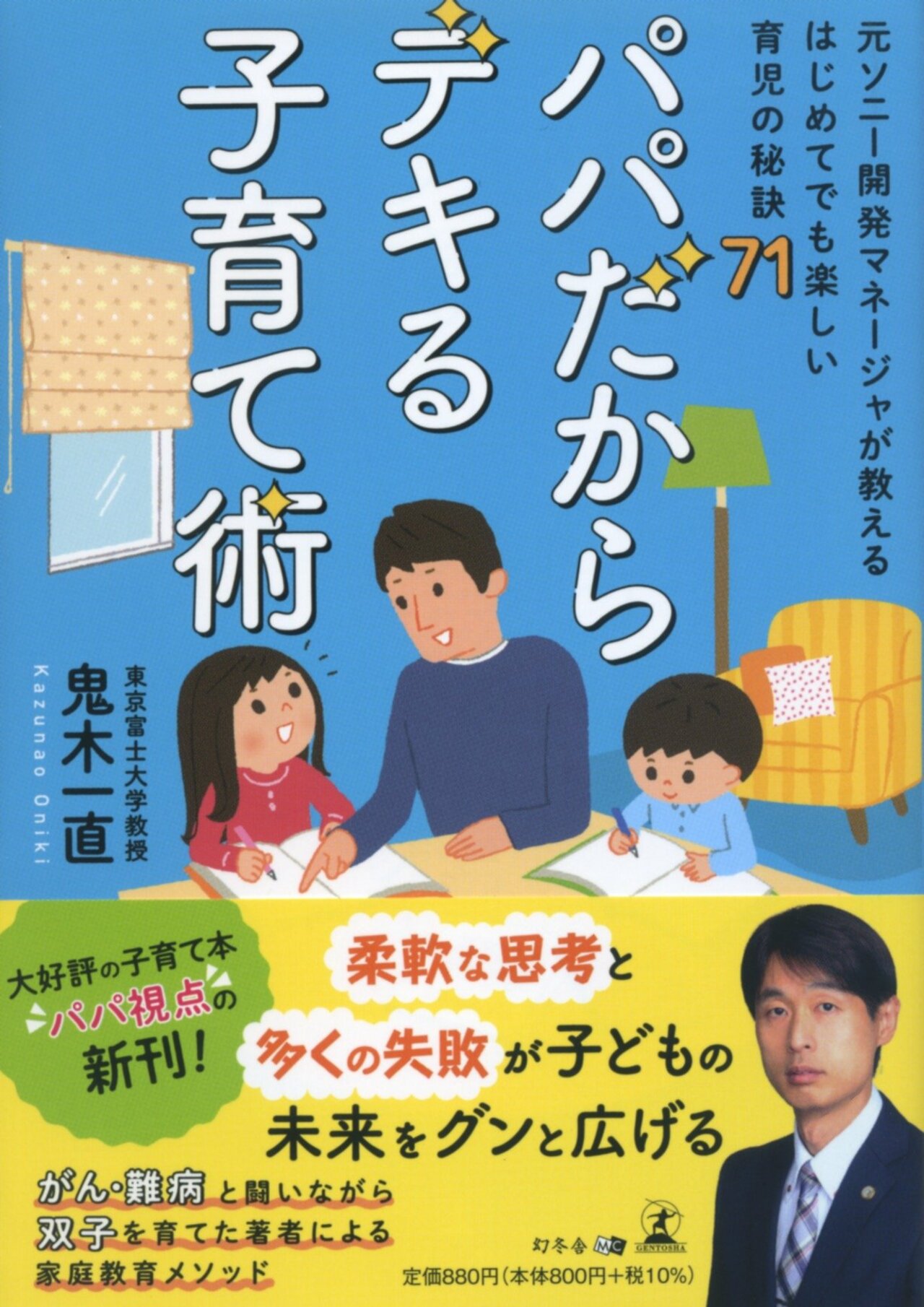【前回の記事を読む】なぜパパの育児参加がうまく進まないのか? イクメンブームを超えて考えるパパの子育ての取り組み方についてご紹介!
第1章 パパの育児参加の意義
イクメンは今や昔の言葉
今の時代、パパが子育てをするのは当たり前
しかし、〝イクメン〟というのは、女性が子育て、男性が仕事をするのがベースにあるからこその言葉であり、どちらが仕事をしてもいいし、育児をしてもいいという考えのうえでは、〝イクメン〟という言葉は意味を成さなくなってきます。
子どもを公園に連れていき、その光景をSNSにアップする。それを見た人が「お父さんが子どもを公園に連れていっているんだね、すごいね!」となってはじめてイクメンであり、それを日常の散歩と捉えるようになれば、それはイクメンでもなんでもないのです。
「俺なんか、おむつも替えているんだよ」と言うと、「偉いね」となりますが、うんちの時はちょっと……なんて言っているようでは、お手伝い程度でしかないと言われても仕方ありません。
育児は毎日のことなので、想定外の事態も含めて対応できなければ意味がないのです。そうは言っても初めからなんでもできるわけではありません。
試行錯誤しながらできる範囲で少しずつ挑戦してみてはいかがでしょうか? イクメンプロジェクトが発足されて以降、父親が子育て参加することが推奨されてきましたが、現実的には〝仕事から早く帰りたいけれどなかなか帰れない〟時期が続きました。
そのような状況の中で、「少子化社会対策大綱(たいさくたいこう)」(2015年)において、2011年には一日あたり67分だった「6歳未満の子どもを持つ男性の育児・家事関連時間」を2020年に2時間30分にするという目標を掲げるなど、
男性の長時間労働を是正する動きもありました。しかし、結果としては2016年時点で83分と、わずかな増加に留まっています。