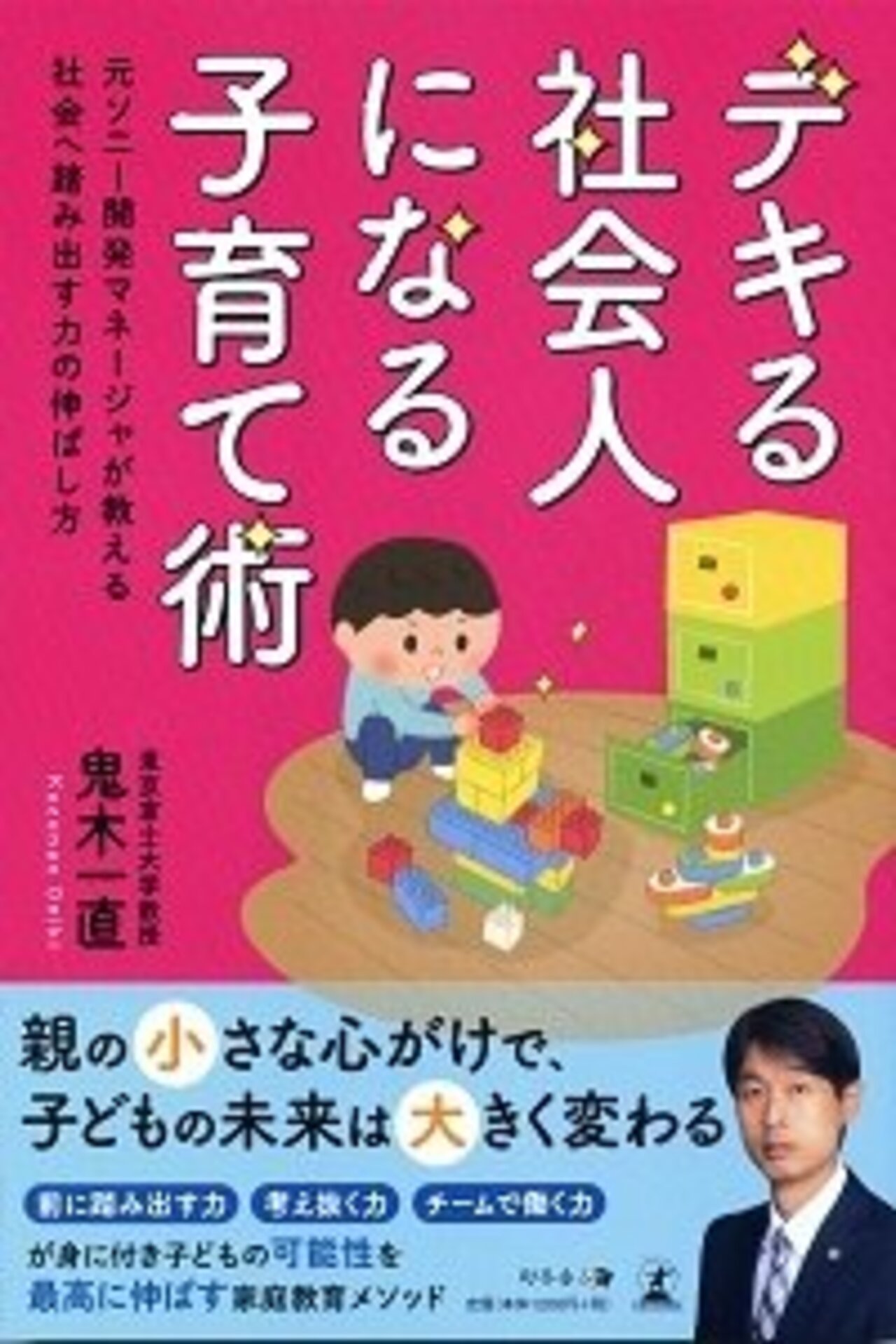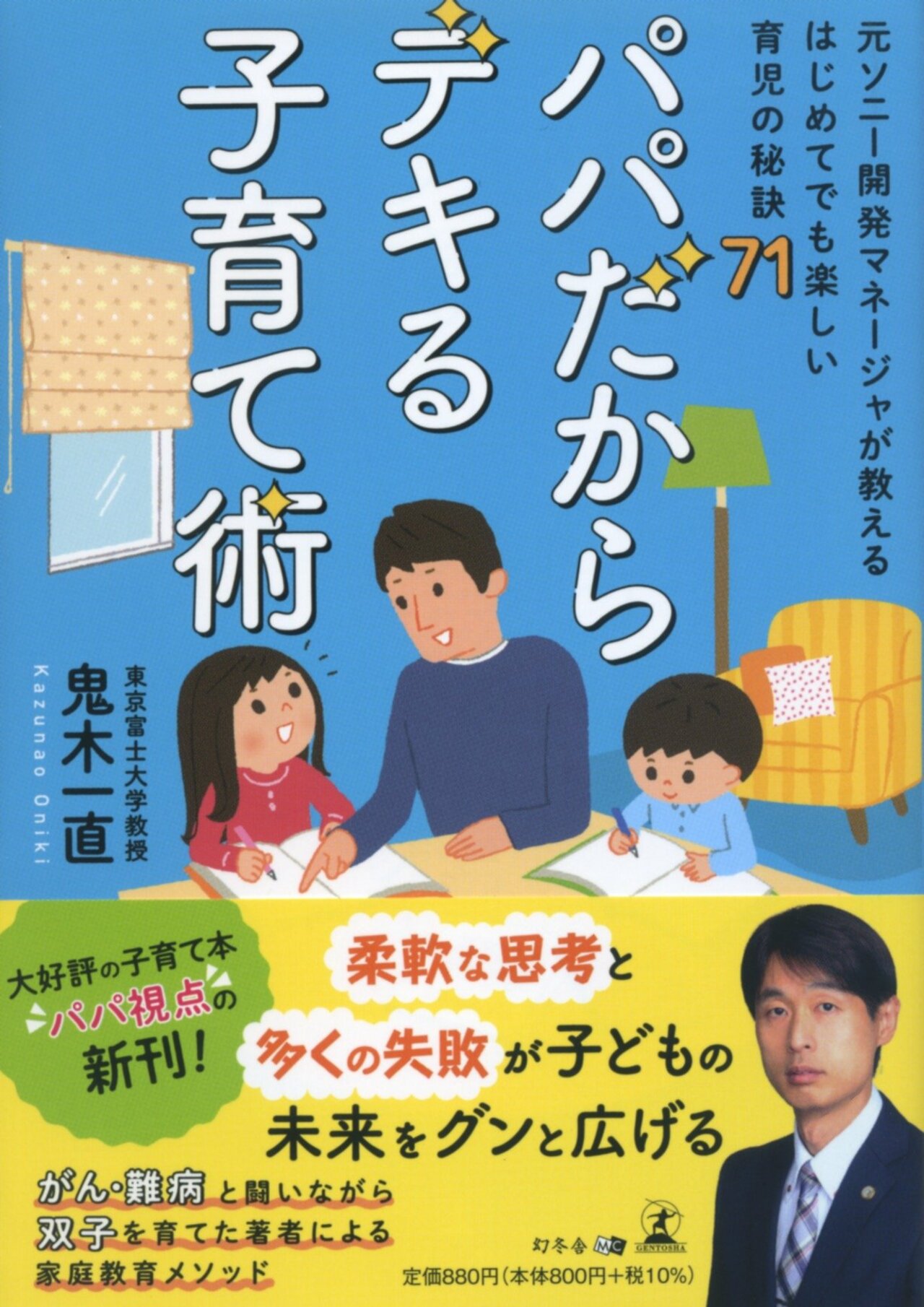ここがポイント
家族にはいろいろな形があり、正解は1つではありません。ただ、女性が仕事をする機会は増えてきており、パパの育児の必要性がどんどん高まってきています。積極的に育児参加して円満な家庭を築いていけるといいですね。
子どもを育てる環境は自ら構築していく
子育てに参加したいという精神論では現実は打破できない
労働時間短縮に向け、一歩踏み出すことができたのは大きな進歩だと思います。ただ、法的是正だけでは、子育て環境は大きく変わらないということです。
私も双子が生まれる前はソニーで働いていましたので、帰りが遅く、家内には苦労ばかりかけていました。
そんな時にがんになり、一命は取り留めたものの、抗がん剤治療の副作用でなかなか体力が戻らない厳しい日々が数年続きました。そこで、以前から興味のあった教育に携わることができ、時間をコントロールしやすい大学での仕事に転職することを決断したのです。
大学教員が楽ということは決してありませんが、夜遅くまでの残業は少なくなり、育児に少しずつ力を注ぐことができるようになりました。
闘病中の私にとって、双子を育てることはあまりにも大変でした。しかし、環境を変えたことで、子どもたちとの大切な時間を多く持つことができ、今では病気になったことにも感謝しています。
パパが育児参加する意義はどこにあるのでしょうか? まず、ママが楽になるということです。ママに余裕ができれば家庭の雰囲気が穏やかになります。
では、子どもに対してパパの育児がもたらす効果とはなんでしょうか? その一つに社会性の発達が挙げられます。