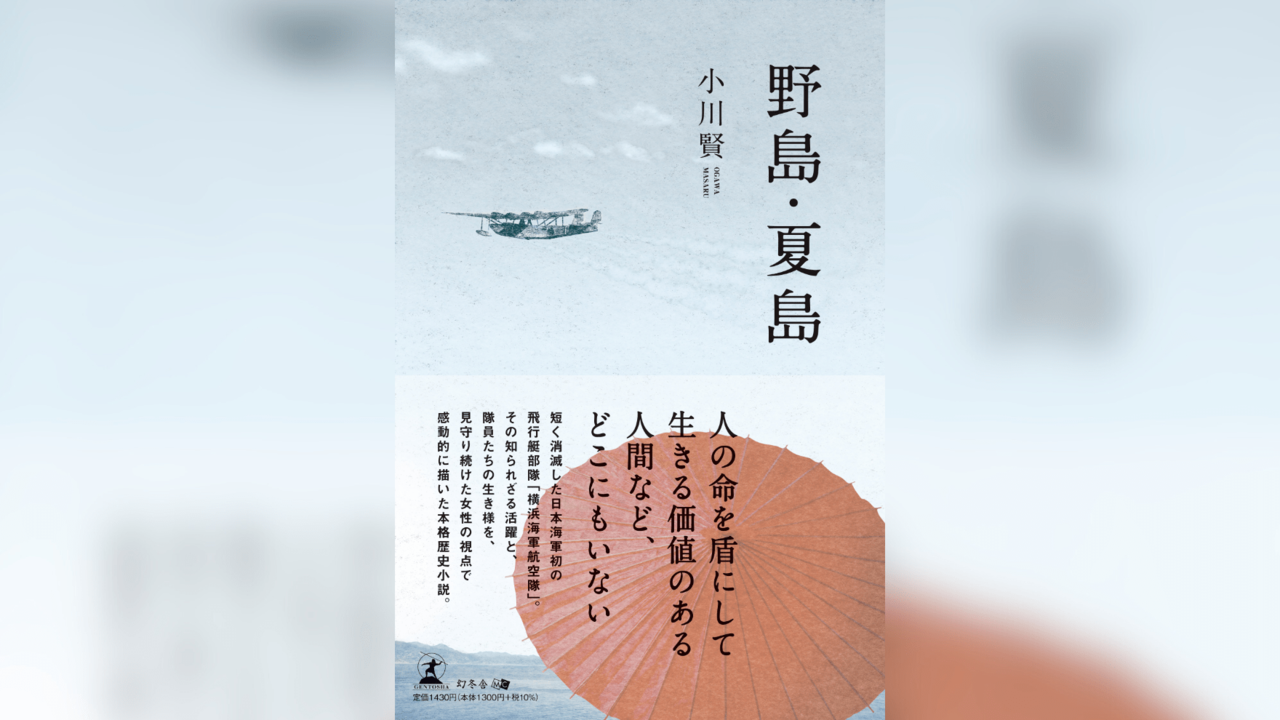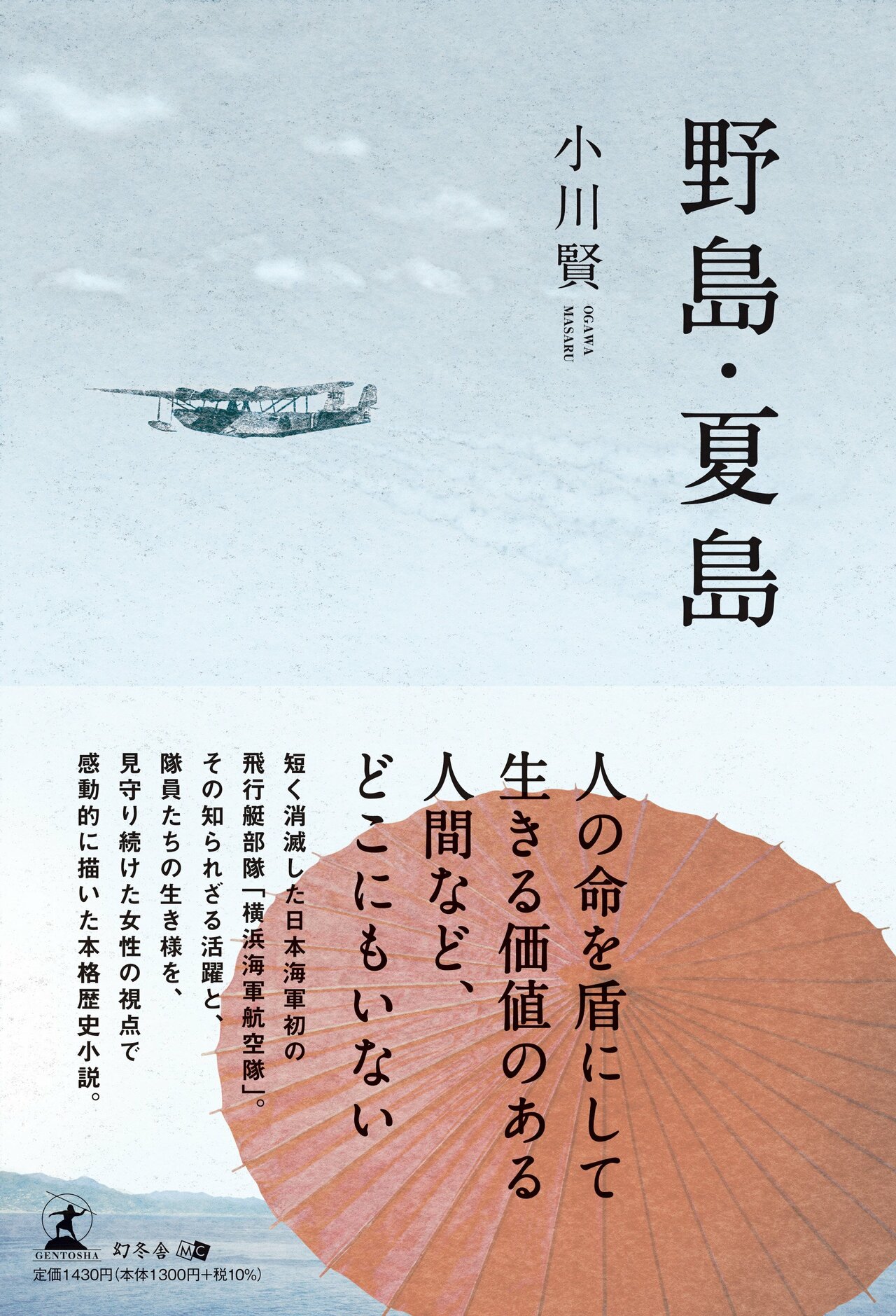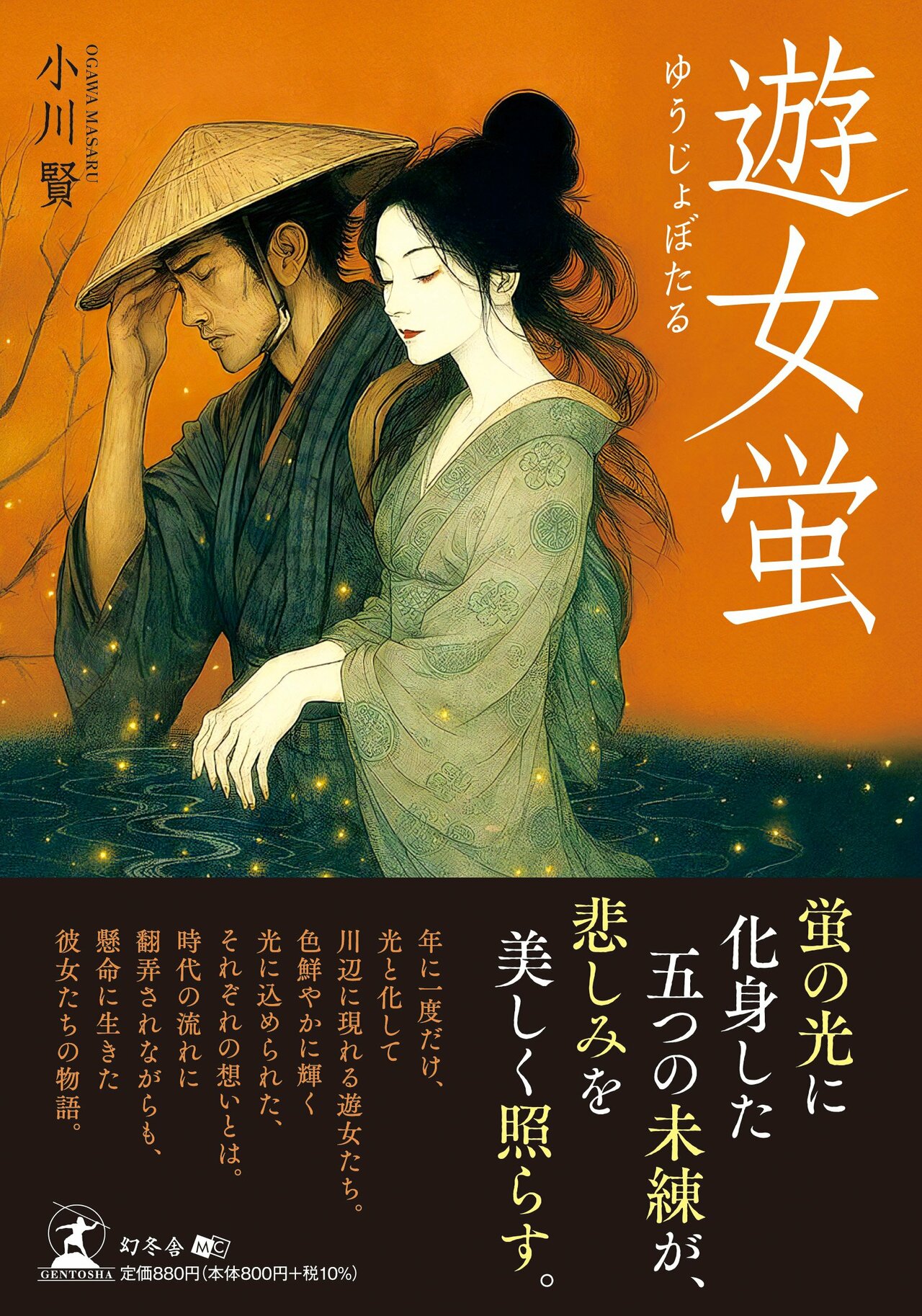【前回の記事を読む】かつて野島は風光明媚な場所で人々に愛されていた。しかし、今では帝都東京を守るための重要な海軍基地になっていた
一 野島・夏島
金沢文庫駅からの細い道を十数分歩くと、左手に称名寺(しょうみょうじ)の古びた赤門が見えてきた。ガンベラの朱色は風化して色が抜け、赤茶にくすんだ木肌が剥き出しになっていた。
赤門をくぐり抜けると、真っすぐに延びた参道の両側には桜並木が並び、その先には風雨に晒(さら)されて黒ずんだ大きい仁王門(におうもん)が、土中から生えた古木のように立っていた。
怒ったような格好をした左右の仁王様に手を合わせ、奈津はその間をくぐり抜けて境内に入った。
幼い頃、寺の仁王門を通り抜けるのは一種の恐怖だった。いつ後ろから「こら待て、奈津」と呼び止められ、仁王様の太い腕で襟首(えりくび)をつかまれないかと不安で胸がいっぱいだった。奈津がそれまでした悪戯や悪事を仁王様に大声で裁かれるのではないかと怯(おび)えていたのだ。
何事もなく仁王門を潜り抜けると、小山を背景にした金堂が姿を現した。
本堂の前には大きな池が広がり、池は阿字ケ池(あじがいけ)と呼ばれ、反橋(そりばし)と平橋(ひらばし)を組み合わせた浄土世界を現わしているとのこと。鎌倉時代からの名刹(めいさつ)で、浮世絵〈称名晩鐘(しょうみょうのばんしょう)〉にも描かれた寺であるが、今は人々から忘れさられているのか、かなり荒れているように見えた。
奈津がこの寺の名を知ったのは、座敷に父が正座して謡う謡曲(ようきょく)の響きの中にあった。夕刻が迫ったうす暗い座敷間から聞こえてくる低い声。
「所から心に叶ふ称名の、……、御法(みのり)の声も松風も、はや更(ふ)け過ぐる秋の夜の、月澄わたる庭の面(おも)……」父の声が脳裏に聞こえる気がした。