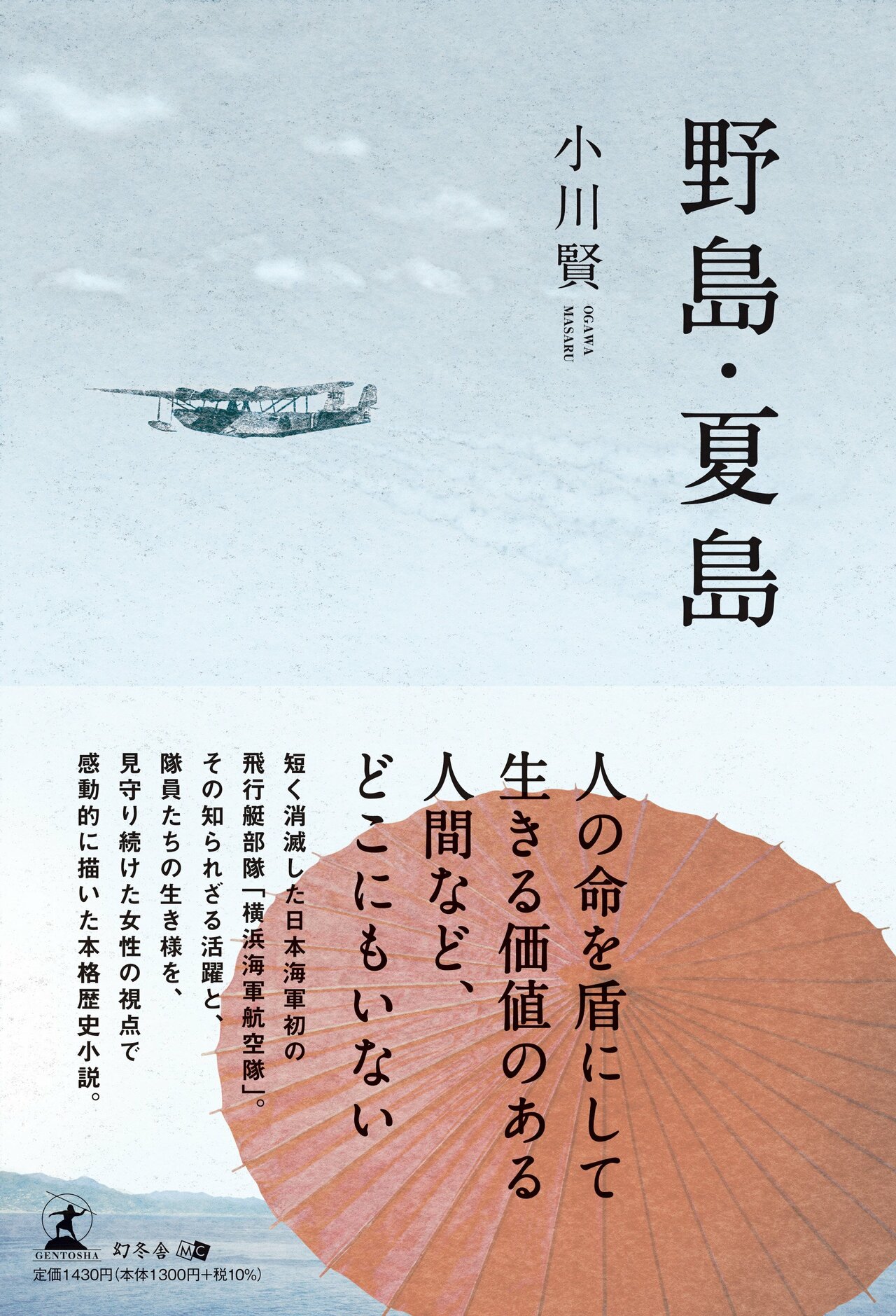小山を借景(しゃっけい)に、前庭に池を配した古寺(ふるでら)での薪能(たきぎのう)の舞台。月夜の庭で焚く薪の炎に照らされ、暗闇に白く浮かぶように舞う小面(こおもて)をつけたシテとワキの旅僧姿を想像すると、奈津はうっとりとして時の経つのを忘れていた。
「バシャ」
突然阿字ケ池の鯉が跳ねた。ぼんやりとしていた奈津は我に返った。腕時計を見ると、奈津は慌ただしく称名寺の境内から出ていった。
奈津は蓮田の畦道(あぜみち)に立っていた。初夏の陽光を浴び、蓮田では大きい葉が風にゆらゆらと揺れ、緑々とした葉をこすり合わせていた。淡いピンクの蓮花が開くのはお盆頃でまだ早い。しかしこの地方は暖かいせいか、小さく固い蕾がチラホラとのぞいていた。
蓮の丸い葉にキラッと輝くものが見えた。奈津にはそれがなんであるかはすぐに分かった。
子供の頃、兄や近所の子と遊んだ記憶。蓮の葉に降りた朝露の雫は、葉の中心の一番低くなったところに集まり、銀色の丸い水滴となった。水滴と葉が接する面が銀色の鏡となって、光を浴びると宝石のようにキラッと輝くのだった。
風に葉が揺れると水玉が蓮の葉の皿の中でぐるぐると回り、しばらくすると再び元の位置に戻ってくる、その動きが不思議で面白かった。子供たちは蓮の葉を手で引っ張って銀の水玉を葉の上で左右に揺するのだが、大きく揺らしすぎると、銀の水玉は葉の外に飛んで行ってしまった。
普段はここで水玉遊びは終わるのだが、遊び慣れてくると子供たちは大胆になり、水玉の宝石をもっと大きくさせようと試みた。すぐ近くの葉同士を引き寄せて二枚の葉をくっつけ、隣の葉に溜まっている水玉を一つの葉に集めた。一つひとつの水玉は小さくても、数枚の葉の雫を集めるとかなり大きな水玉になる。
しかし、水玉の宝石の大きさにも限界があるのか、水玉が大きくなりすぎると、一つの水玉にしてもすぐに二つ三つの水玉に分かれてしまった。そして水玉が多くなりすぎると、蓮葉の一部が急に折れ曲がって溝ができ、宝石の水玉はその溝を通って、あっという間に蓮田の水面に落ちていった。