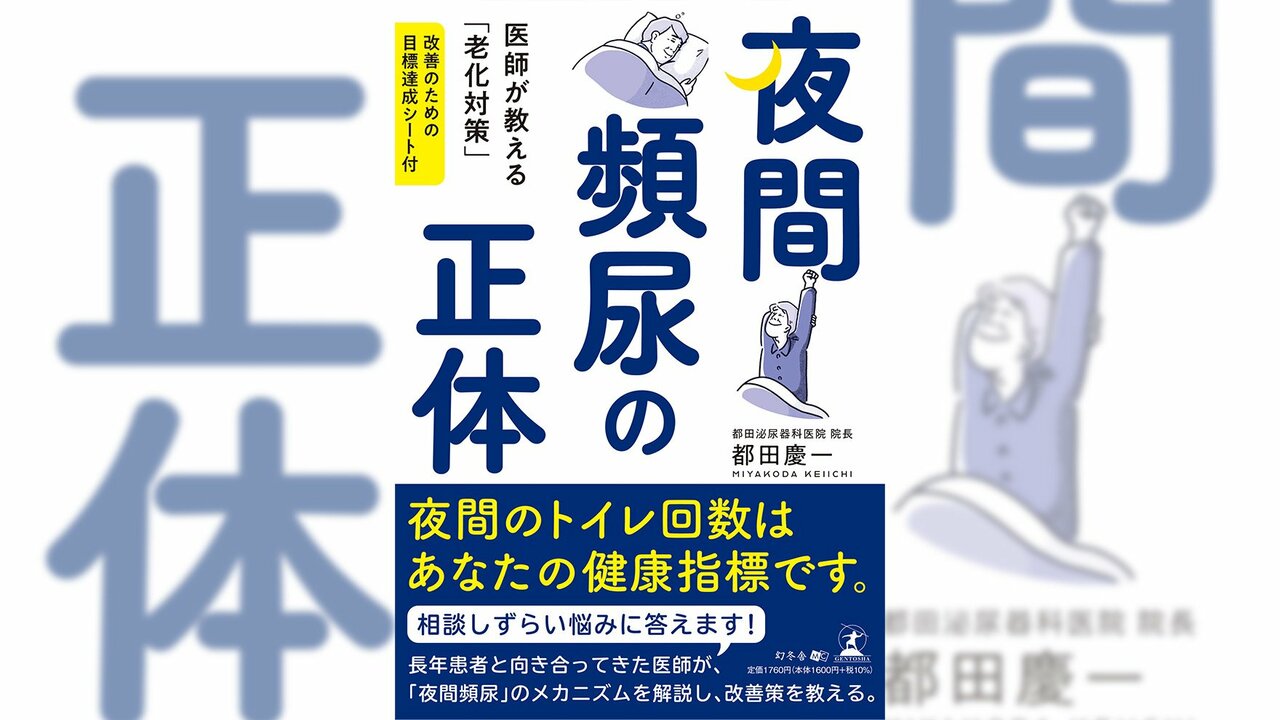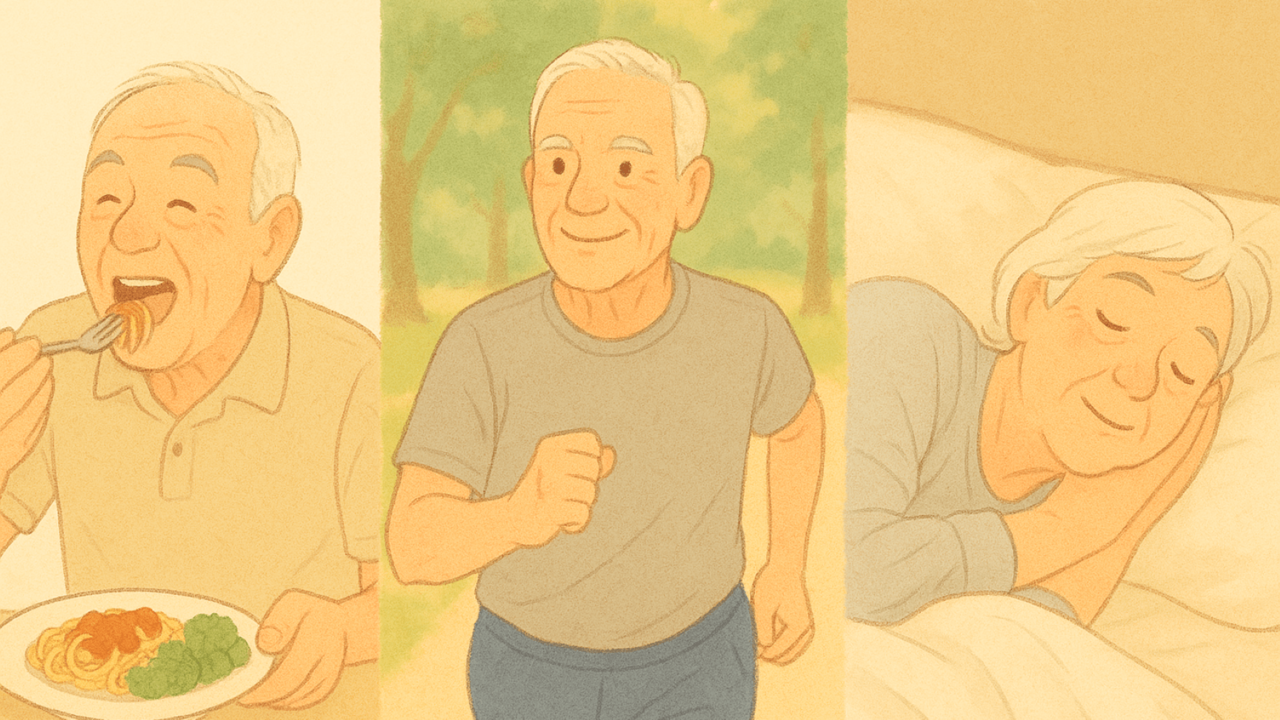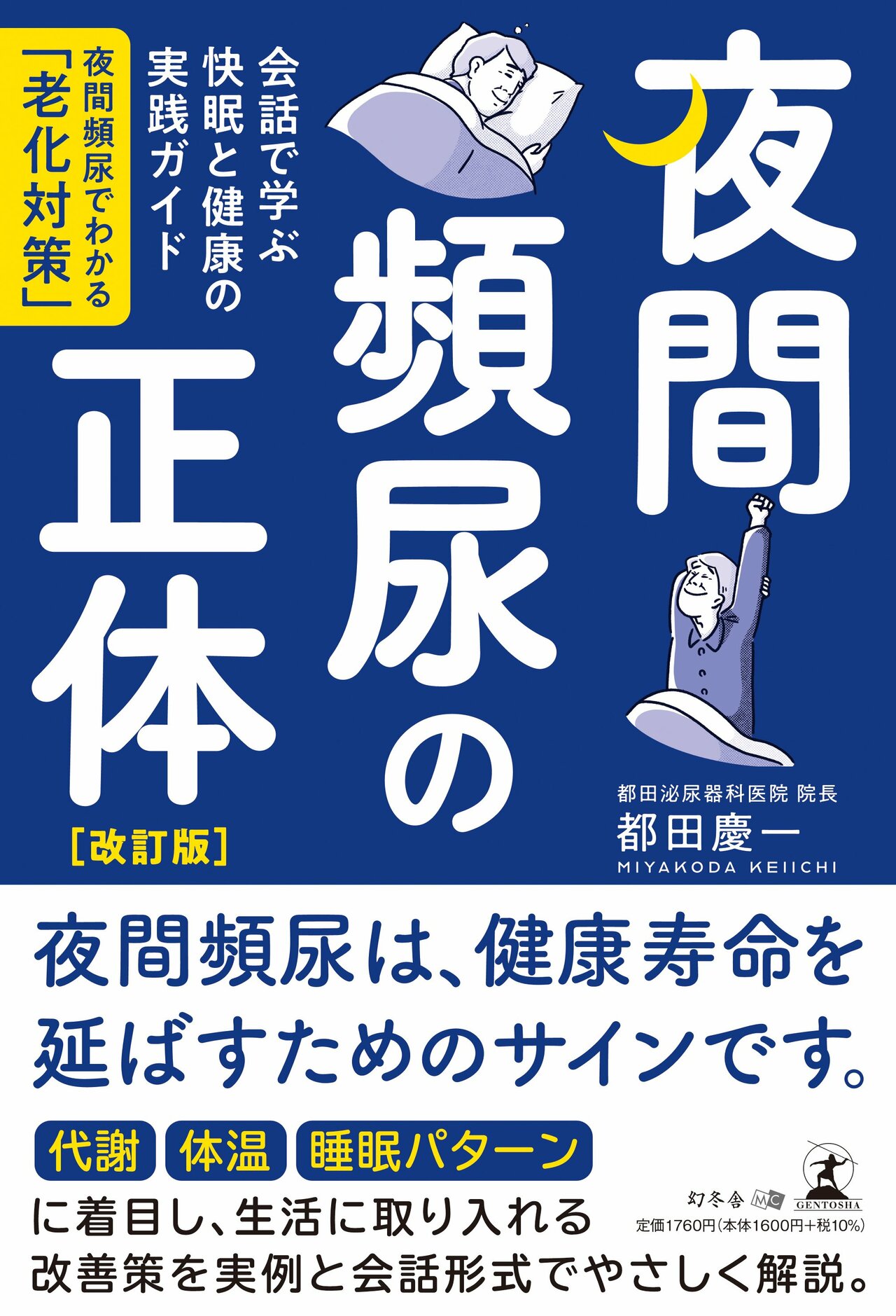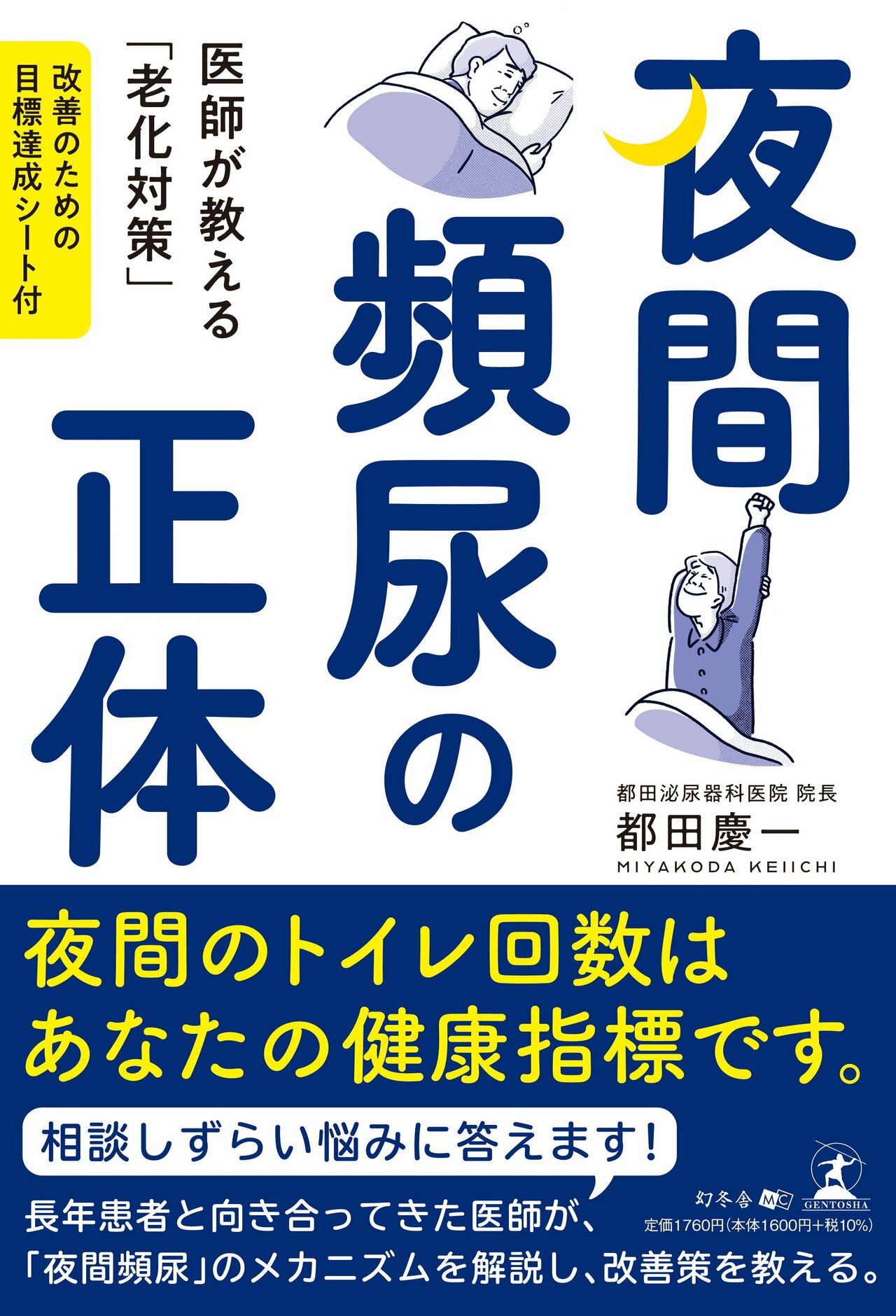【前回の記事を読む】夜間、排尿のために1回以上起きなければならない人は夜間頻尿の疑いアリ。元気で夜間排尿回数の少ない人の生活としては...
[二]実はコレ! 夜間頻尿を引き起こす原因
この章の流れ
1.夜間頻尿の原因
夜間排尿の原因について、従来からいわれていること、その治療の流れ、薬の効果の印象、について述べます。そこで、他医療機関での夜間多尿の改善効果が今ひとつ伝わってこない中で、当院の治療効果の概略と方向性について触れています。
夜間頻尿の原因
夜間頻尿の原因は、①膀胱刺激や残尿を増やす疾患があること、②夜間尿量の多いこと、③睡眠の乱れ、この3つから構成されている、とされるのが定説です。疾患対策では、優れた内服薬があります。睡眠と尿量の管理については、生活の中での自己管理、あるいは生活指導が、夜間頻尿を安定化させたり、効果を増強するためには必須です。
しかし、夜間頻尿はそんなに単純なものではなく、内部環境では高齢者の生体機能の劣化の影響、季節や室内環境の影響で不安定化します。
生体機能では、代謝であり、深部体温調節であり、睡眠の仕組みなどが関わっています。外的環境では、温度、湿度に影響され、冷えやうつ熱、中途覚醒に影響を及ぼし、夜間頻尿の原因になります。内外的環境によるものに対しては自己管理と生体機能の維持、向上、そして行動性体温調節で対応します。
夜間頻尿の原因を踏まえた生活指導は、それらを全て組み入れたものであり、大きな壁である夜間頻尿診療ガイドラインに記載されている行動療法との違いを示しながら、その意義について述べておきたいと思います。
当院の②夜間尿量と③睡眠管理に対する生活指導は、周辺の知見を加えて膨らみました。よって、それなりのエビデンスを加え、自分でもフィールドワークの統計をまとめて方向性を探って参考にしました。この生活指導で効果が得られていることで、夜間頻尿の正体に迫る上で自信が湧いてきたように感じます。
夜間頻尿の要因、背景についてはいろいろあり、本書で少しずつ解き明かしていきます。