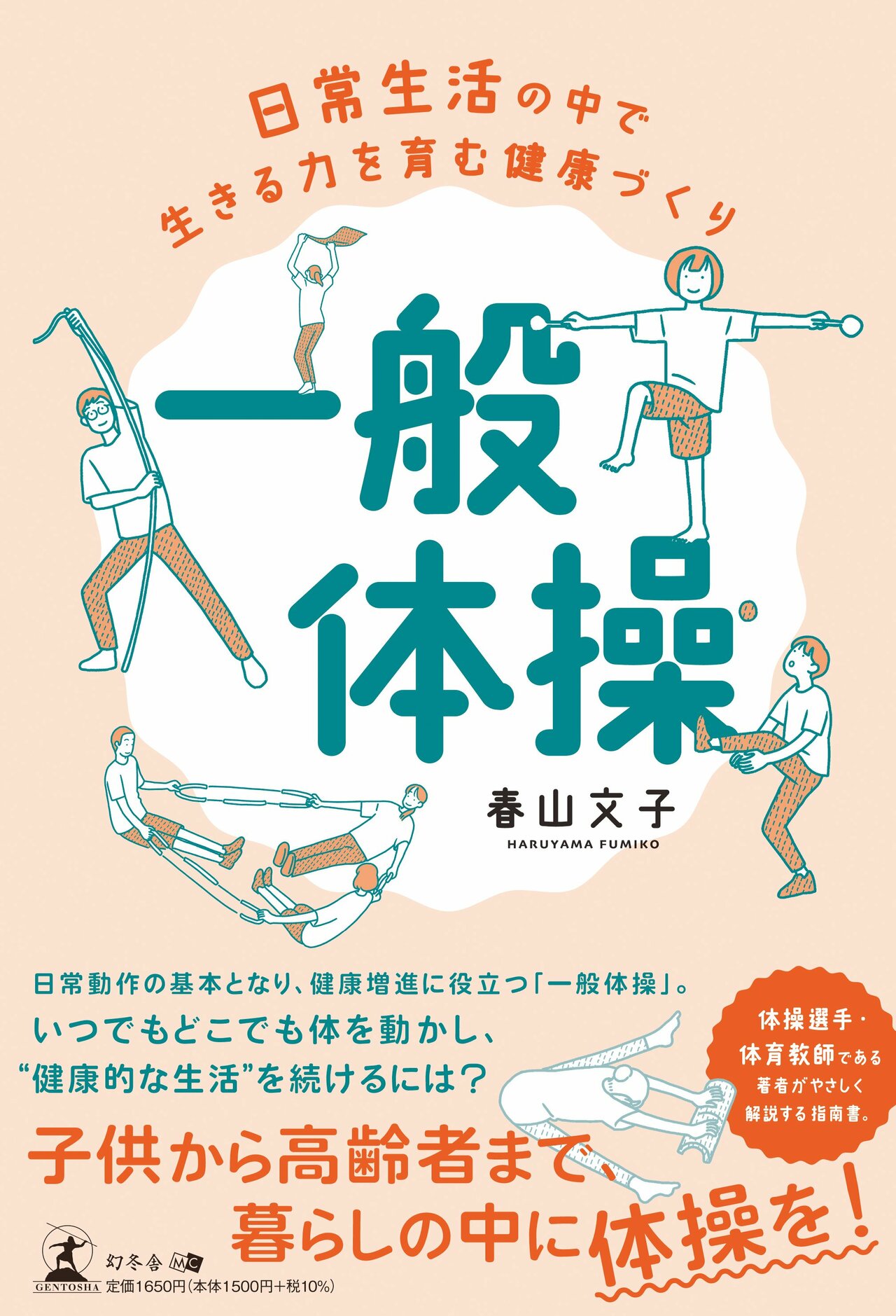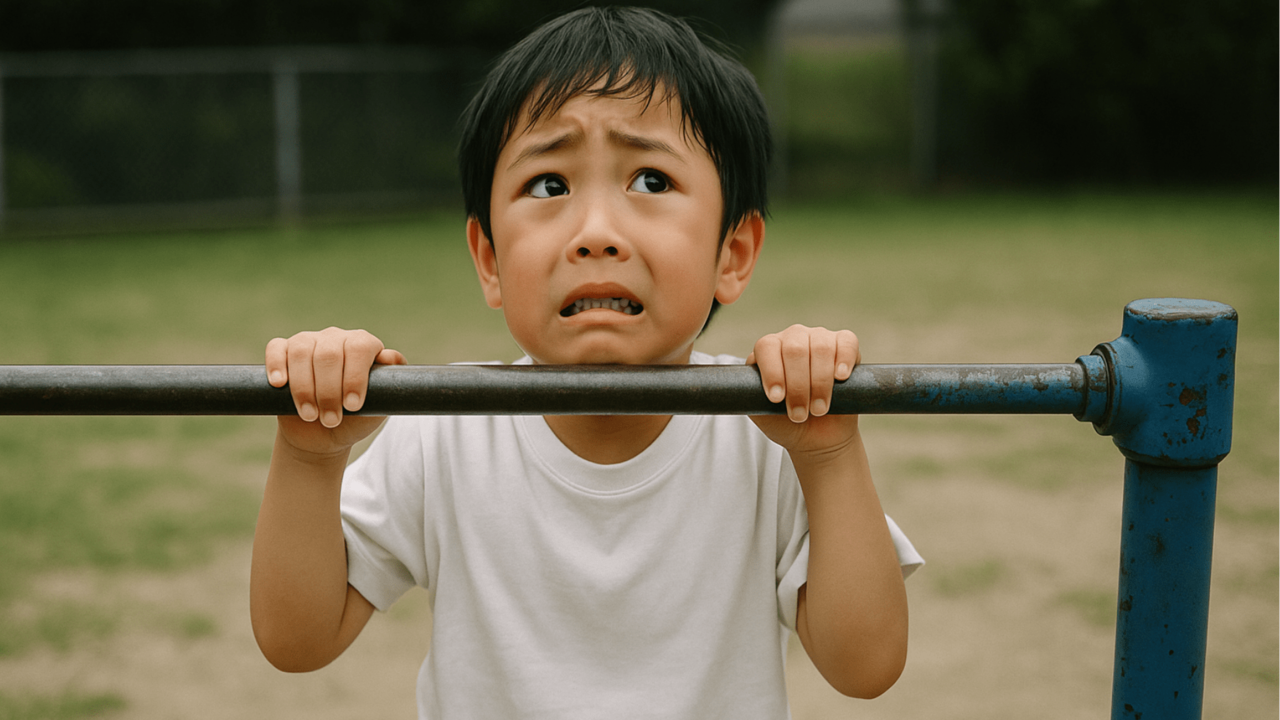若い人、成人、老人に共通するのは、日常の動きや動作が“いつでも、どこでも、だれでも”できるつもりになっていることです。
コロナ禍の生活も3年が過ぎ4年目に入った今、生活習慣を見直す良い機会になったように思われます。ただ、動かなければ不具合にも気づきません。恵まれた生活環境の功罪に早く気づくためにも動いて具体的な改善内容を見出して、できることから行動を開始すると楽しみになります。
自粛生活は萎縮生活になり、体力の調査結果でも明らかなように総合筋力の低下は握力でも報告されました。
その他、サルコペニア、ロコモティブシンドローム、フレイルが気がかりな情報として強調されています。もちろんメタボリックシンドロームや認知症など、運動不足が関連して起こるすべての生活習慣病の予防が呼びかけられていますが、生活の見直しの中で、「座りすぎ世界1位の日本人」(主要国中)の意識改善が示唆された報告もあります。
運動不足予防のおすすめのノウハウはいろいろ紹介されていますが、自分のからだに相応しい内容かどうか、どこの筋肉が減少しているか、どのような動きを必要としているかを確認することもなく安易に取り組むと、からだに不具合を感じて休みがちとなります。こうした自己流の対症療法後の中止は、知識不足や自覚不足とも感じられます。
受診で運動不足を指摘され、体力をつけたいと漠然とした目的で健康体操講座に来る人もいます。
確かに運動はからだづくり、動きづくり、友達づくりなどに効果がありますが、からだの即効薬的な効き目ではなく、運動を続けるための導入とし、その後の生活の中で動くことが習慣化するように、具体的に理解しておくことが参加するときの心構えになります。
また、一人で自由に動くのと仲間や集団で動くことのそれぞれのメリット、デメリットにも注目してみてください。身体的、精神的、社会的に得られる多様性は多方面で活用でき、健康体力が一層高められるでしょう。