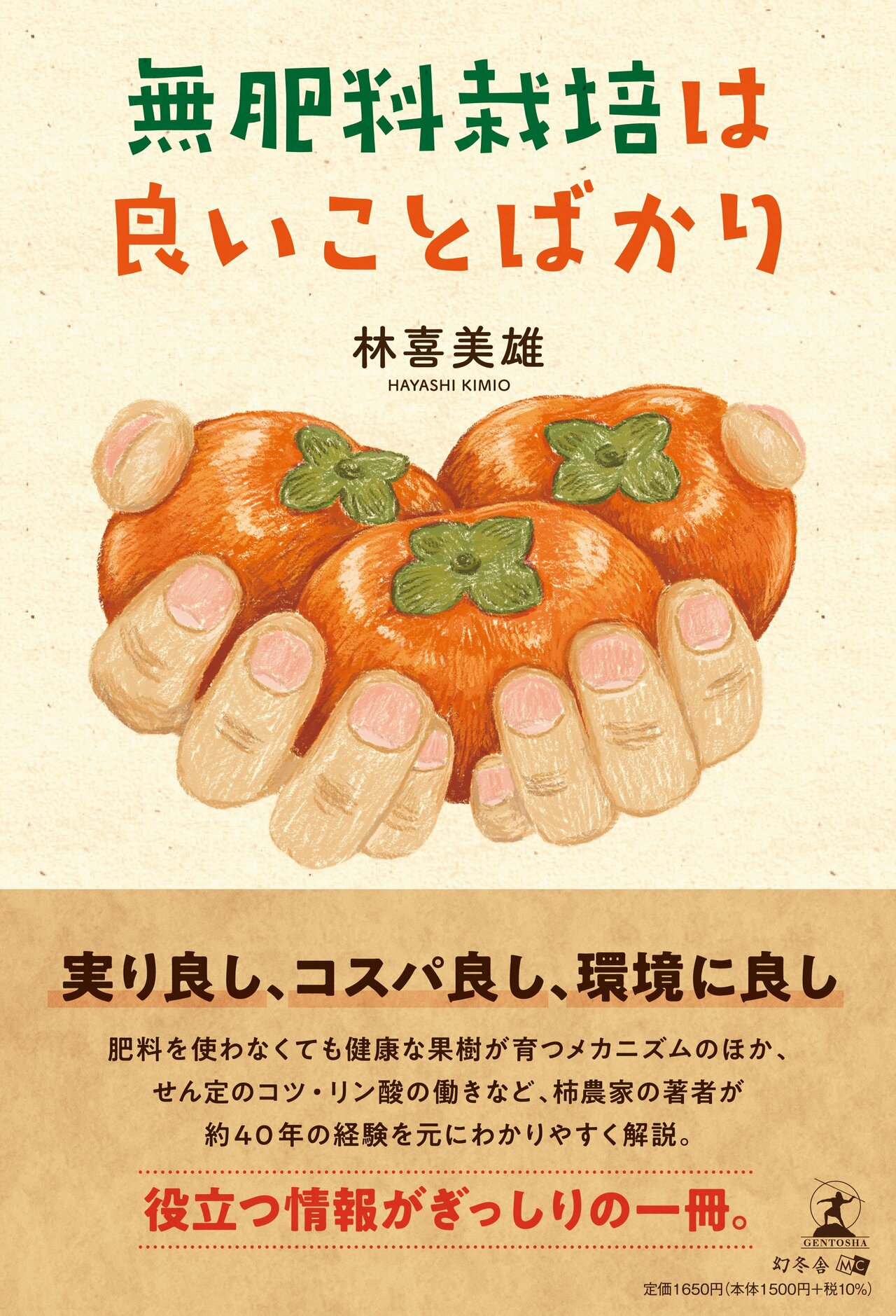ところで、勉強の結果であるが、最初に疑問を持ったのは肥料のことである。二月頃元肥(もとごえ)と称して、一年間に必要な量をほぼ全量施しているのが一般的である。
あらかじめ、土壌に馴染ませておいて、必要な時に吸収してもらおうという作戦のようだ。
植物は、三月に入った頃、その年の新しい根を出す。私は、かつて、盆栽が趣味であった時期があり、三月の植え替えの時、褐色の根の先に白い新しい根が二~三ミリメートル伸びているのを何度も見ている。
また、小学生の時、真水の入った容器にヒヤシンスの球根のお尻を少し浸しておくと、根がいっぱい出てやがて花を咲かせるのを思い出した。つまり栄養分はない方が根は良く伸びるということだ。
これから根が伸びようとする時に肥料を与えるとは何という無謀なことなのだろうか。そう思ったのである。
又、窒素、リン酸、カリウムを高度化成という形で、あらかじめ配分された肥料を通常は使っている。
例えば、窒素、リン酸、カリウムが12-8-10とか、10-10 -10とか、三成分を合計して三十以上になると高度という文字を使えてイメージが良いから無理に使っているのではないだろうか。事実かどうかわからないが、選択肢が制限されるのは良くない。
そこで、新年度、私にとっては初年度でもあるが、次の様に施肥計画を立てた。肥料の全体量は半分とし、元肥は廃止する。六月末の夏肥だけとし単肥で施した。
リン酸の量を減らすには、あらかじめ配合された高度化成では無理であるからだ。
リン酸は、光合成で作られた糖を運ぶ役割を担っており、ヤワ果の原因であると考えていたので、半分にして試してみたかったのだ。
そしておそらく今後の栽培における最大のポイントになるであろうと感じていた。
【イチオシ記事】一通のショートメール…45年前の初恋の人からだった。彼は私にとって初めての「男」で、そして、37年前に私を捨てた人だ
【注目記事】あの臭いは人間の腐った臭いで、自分は何日も死体の隣に寝ていた。隣家の換気口から異臭がし、管理会社に連絡すると...