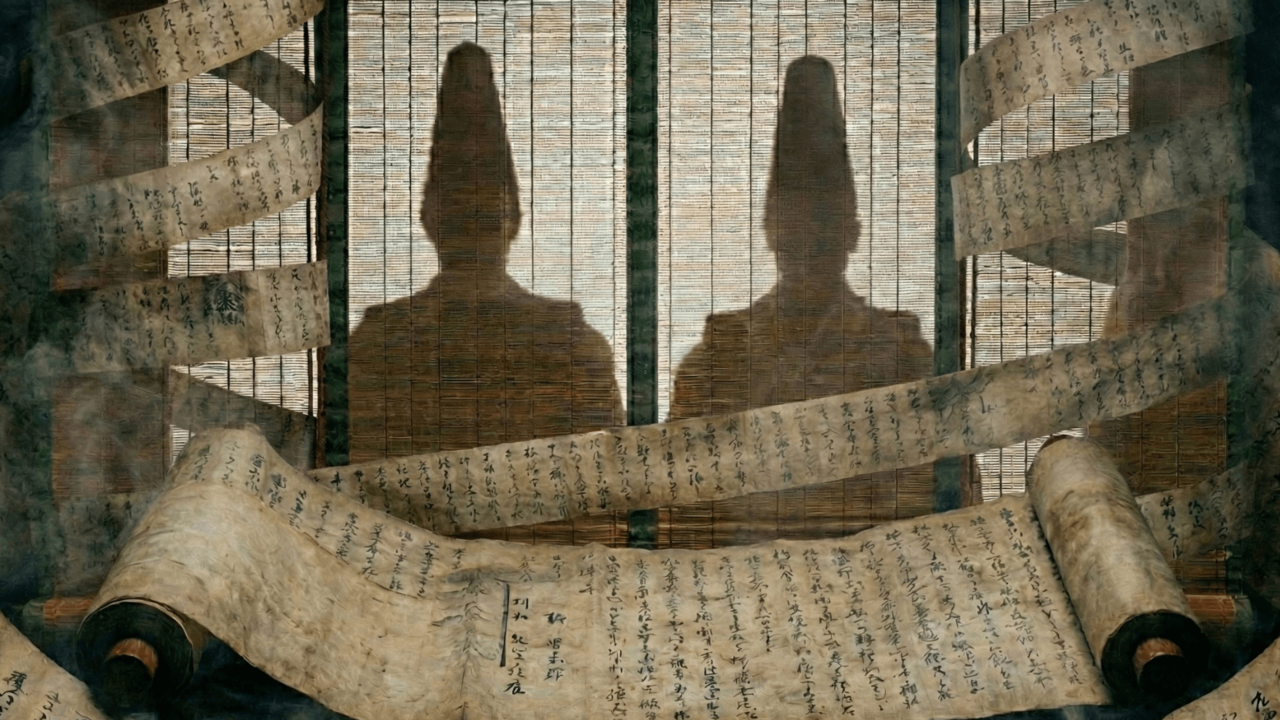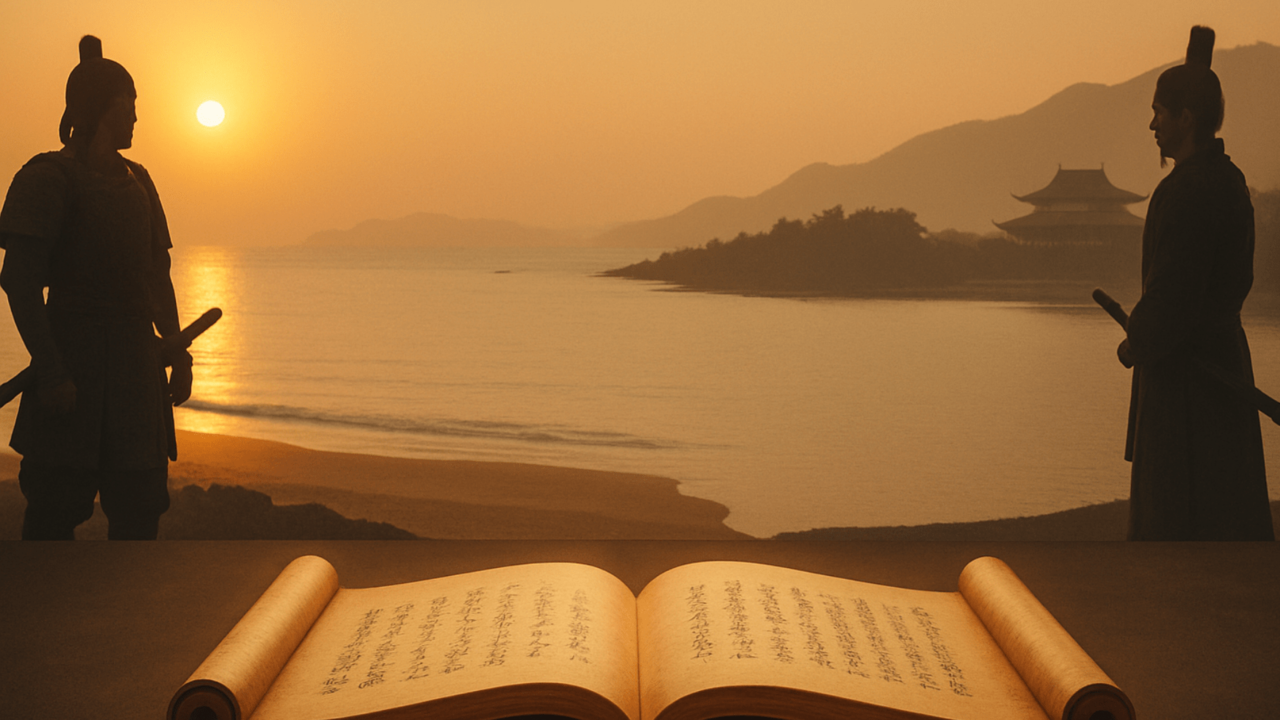『記紀』に書かれていることを十分吟味するだけでなく、書かれていない事実をもっと尊重すべきである。結果として邪馬台国が「大和天皇家」と関係ないことが、「倭の五王」の考察に付随して導き出される。
「倭王武=雄略天皇」説が広く流布されているが、成立しえない説であると論じた。これまで歴史学者がなぜこの説に固執するのだろうか。その理由は、「倭王武=雄略天皇」説が中国史書の時間軸に『記紀』の年代を繋ぎ止める接点になっているからである。
天皇の在位年代は、『宋書』夷蛮伝に記載された「倭王武」が宋に遣使を送った昇明二年(西暦478年)を「雄略天皇」在位期間に置くことで、前代、後代の天皇の在位年を類推してきた。
もし「倭王武=雄略天皇」説が成立しないとするならば、再び日本古代史は時の波間に漂い流れることになるだろう。しかしこれは決して不都合なことではない。
中国史書に記された倭国の王を天皇に対応させ、所在を大和に求める強迫観念から解放され、もっと多角的な視点から古代史を俯瞰する機会となる。このような姿勢で『記紀』を読むと、巨大な未整理のデータバンクでありながら、宝の山でもあることに気づく。『記紀』を「つまみ食い」するのでなく、データバンクから史実の断片を抽出する試みを心掛けたい。
第三話 数値情報から見る二倍年暦と皇統譜
「第一話」において『記紀』は史実に関して数値情報が乏しい一方、天皇の寿命や天皇位に関する行事(立太子、即位など)の数値情報は異様なほど一貫性、整合性があると述べた。表1(21ページ)はそれらの情報をまとめた一覧表である。
すべての天皇の即位年は「干支」で記されているが、これは六〇年周期で繰り返され、人の生涯に一、二度しか経験しないことなので西暦に容易に換算できる。表では「壬申の乱」(西暦672年)を基準に遡って換算した。
表から受ける違和感は即位情報の連続性だけではない。表の上半分の天皇の情報の方が下半分の後代の天皇のそれより多いことである。
二‐二 『宋書』夷蛮伝
太祖元嘉二年、(中略)讃4 死弟珍4 立、遣使貢献、自称使持節都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭国王、表求除正、詔除安東将軍・倭国王。(元嘉)二八年、(済4 )加使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六
国諸軍事・安東将軍如故、(以下省略)。世祖大明六年詔曰、倭王世子興4 (中略)宜綬爵号、可安東将軍・倭国王。順帝昇明二年、遣使上表曰、(中略)東征毛人、五十五国、西服衆夷、六十六国、渡平海北、九十五国(中略)詔除武4 使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭王。
二‐一 「神功皇后紀」巻第九『魏志』引用の記事
三九年。是年(ことし)、太歳己未(つちのとひつじ)。魏志(ぎ)しに云(い)はく、明帝(めいてい)の景初(けいしょ)三年の六月、倭(わ)の女王(じょわう)、大夫(たいふ) 難斗米等らを遣つかはして、郡こほりに詣いたりて、天子に詣いたらむことを求もとめて
朝献(てうけん)す。太守(たいしゅ)鄧夏、吏(り)を遣(つかは)して将ゐて送(お)くりて、京都(けいと)に詣(いた)らしむ。
四〇年。魏志に云はく、正始(せいし)の元年に、建忠校尉梯携等(けんちうこういていけいら)を遣(つかは)して、詔書印綬(せうしょいんじゅ)を奉たてまつりて、倭国(のわくに)に詣いたらしむ。
四三年。魏志(ぎし)に云(い)はく、正始(せいし)の四年、倭王、復使大夫またつかひたふ)伊声者掖耶約等八(らや)人たりを遣(つかは)して上献(しょうけん)す。
四六年の春三月(はるやよひ)の乙亥(きのとのい)の朔(ついたちのひ)に、斯摩宿禰(しまのすくね)を卓淳国(とくじゅんのくに)に遣す。
【イチオシ記事】一通のショートメール…45年前の初恋の人からだった。彼は私にとって初めての「男」で、そして、37年前に私を捨てた人だ
【注目記事】あの臭いは人間の腐った臭いで、自分は何日も死体の隣に寝ていた。隣家の換気口から異臭がし、管理会社に連絡すると...