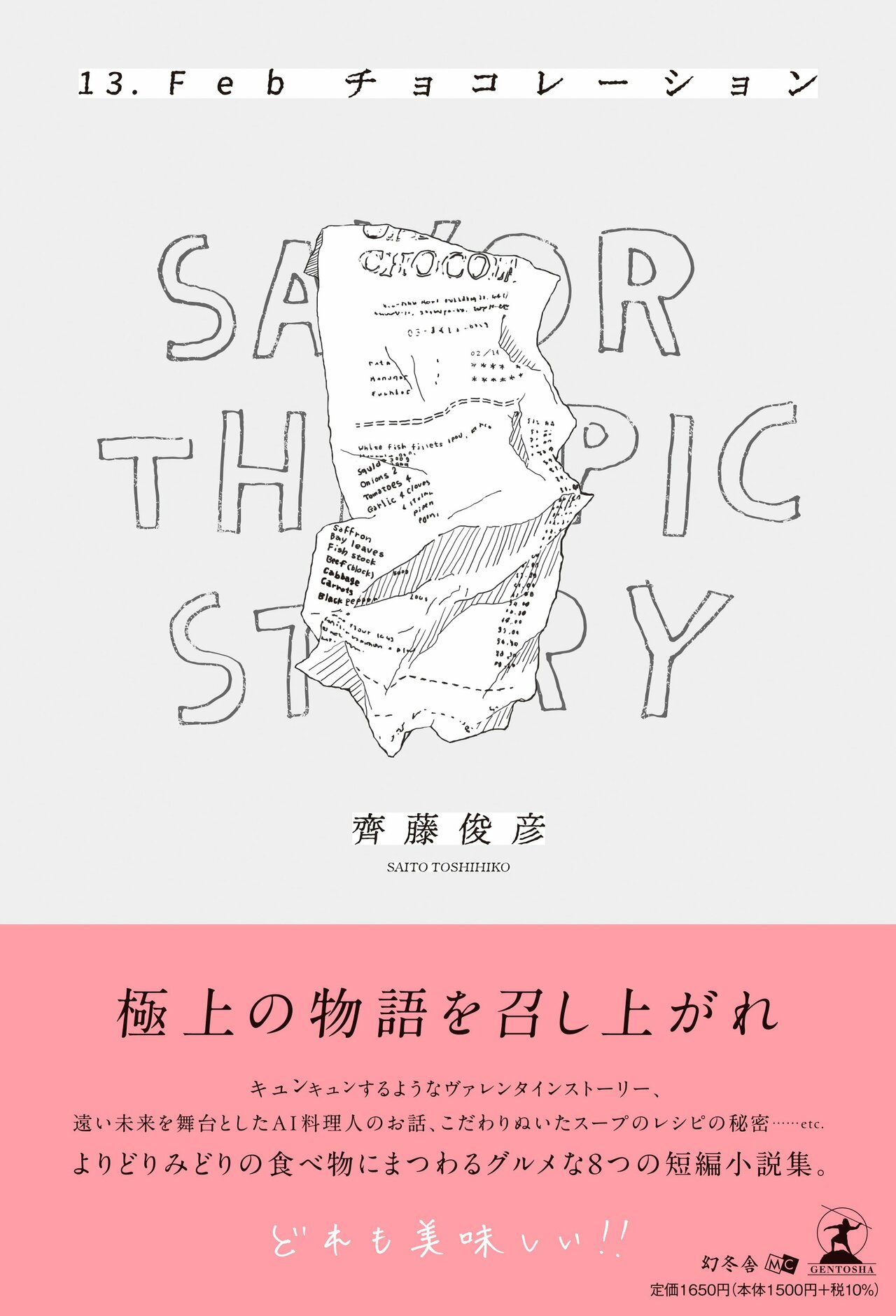「でもなぜ日本にある?」
「私だってよくは知らない。文化大革命の直前に大陸から香港に移されたの。それ以前にも、第二次世界大戦の直後にも、分けられた一部が国民軍と一緒に台湾に渡ったと聞いているけど、その後、それがどうなったか誰も知らない。今も台湾のどこかにあるかもね」
「同じものが、たくさんあるのか?」
「日本だって鰻の蒲焼きのタレはあちこちにあるじゃない。暖簾分けした店って、ずっと付け足しできているでしょ」
里見は、ある老舗の鰻屋で、戦時中にタレの壺を土中に埋めて空襲から守ったという話を思い出した。
「だけどこれはスープだろ、タレとは違う。水分活性が高いからすぐ傷む」
「そうよ、大陸にあった時には、大きな銅鍋で24時間火を絶やさないように5人の料理人が交代で番についていたって聞いたわ。炉には石炭を放り込み、鍋には水を足して、食材を入れる。香草を入れ、岩塩を入れ、灰汁(あく)を取り、濃縮されたスープを客に供する。数百年、火を絶やさず続けていたのよ。だから細菌の増殖なんかない」
玲蓮は、いつものように手櫛を入れると、ため息をついて、遠くを見るような目で鍋を見つめた。
「誰のために、そんな物を」
「さあね、最初は村の人たちの日常食でしょ」
「村の?」
「昔はその村の人に供していて、今は一部の高貴な人のもの。長老たち」
「どんな人たち?」
玲蓮は里見の目を捉え、口調を少し厳しくして言った。
「それは秘密。だけど皆、大変なお金持ちで、世界に散っている」
「長老以外、盗み味したものは舌を切られるとか?」里見はおどけて見せた。
「まさか、今は21世紀よ。味のチェックは必要でしょ。それに門外不出の秘伝の変わらぬ味ではなくて、いつも入れる材料で変化していくのよ。長老は、みんな味の変化を楽しんでいるの。特に最近の長老はね。ビンテージワインの味を懐かしむみたいにね。何年の時はどんな味だったとか」
「そんな道楽な」
次回更新は6月23日(月)、22時の予定です。
【イチオシ記事】妻の姉をソファーに連れて行き、そこにそっと横たえた。彼女は泣き続けながらも、それに抵抗することはなかった