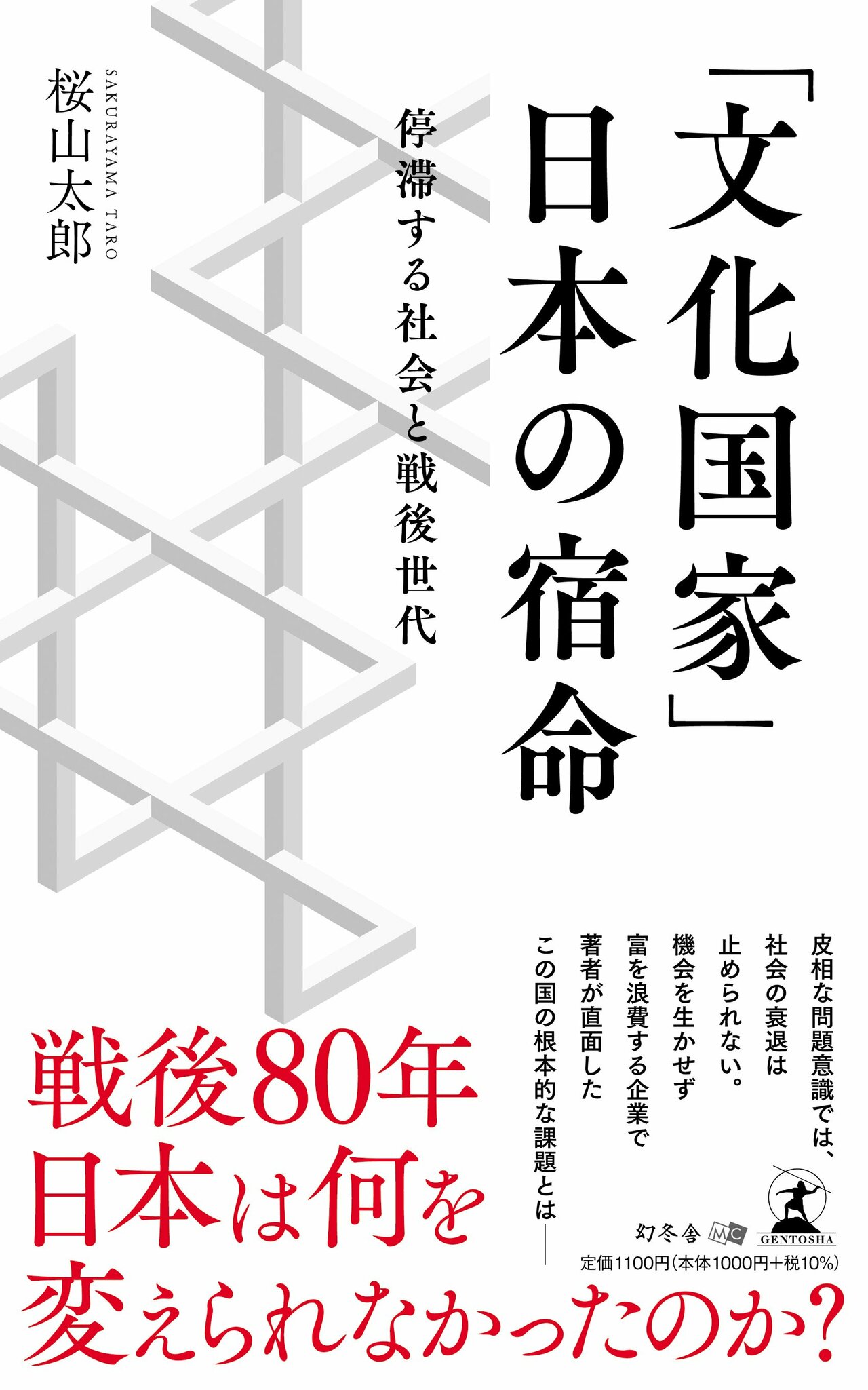第一章 幸せなおじさんたちの罪
―崩壊する「科学技術立国」の現場
問題意識と語られない情念
タイトルや前書きから察せられる通り、本書は社会問題を論じた著作物に分類される作品として書かれている。あえておことわりする必要はないのかもしれないが、社会問題について語るというスタンスそのものが著述の前提を不問にし、決定的なバイアスを伴うという現象についての話から本文を書き始めたいと思う。
人が社会問題を論じるときは、自分以外の人々にとって望ましくない状況について述べ、それは解決されるべきだと善意で考えるのが話者と聞き手のあいだで共有される約束ごとになっている。
オレがモテないのは社会が悪いからだと主張する人や、我が一族が豪奢(ごうしゃ)な暮らしを続けるためには他の日本人を貧困層に落としても構わないなどと述べる人は、社会問題について論じる人とは一般に見なされない。
しかし社会一般の改善や維持向上を当然の目的として語られるもっともらしい議論にも私的な発想や偏見は必ず入り、その偏りは個人的な事情に世間的な通念や議論の型、言語能力や認識力の限界などさまざまな要因が重なって生じている。
例えば現代の日本が抱えている大きな問題として、少子化の現象が頻繁に語られる。子供が減る、若者が減る、労働力が不足する、税収が少なくなる、社会全体が貧しくなる、という必然は多くの人にとってわかりやすく、その克服はたしかに取り組むべき課題だと思わせる話になっている。
ところが全国で広く共有できるテーマであるために問題の捉え方の微妙な相違が逆に見過ごされ、議論の前提が互いにわからなくなっている面がかなりあると私には思われる。