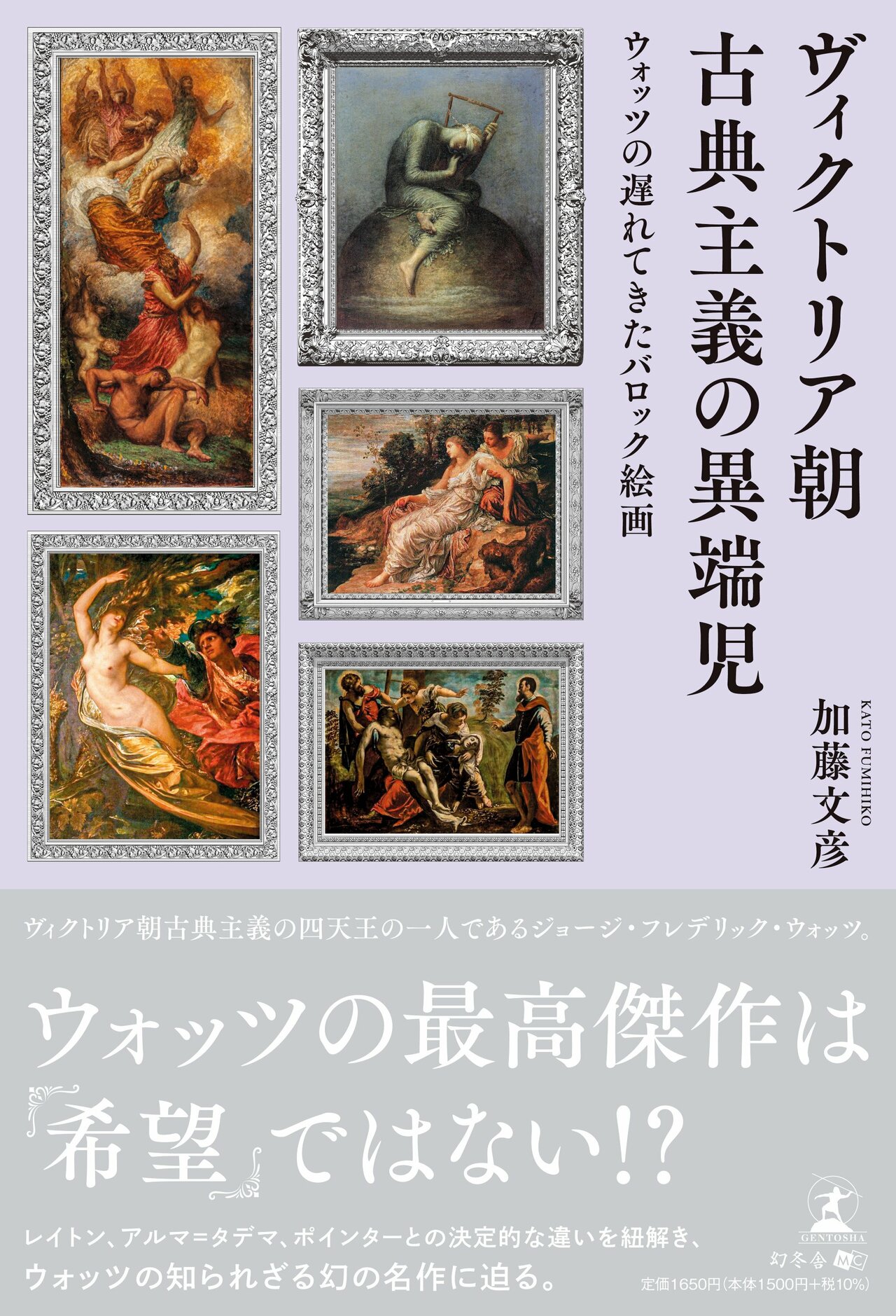そのウォッツを、ロイヤル・アカデミー会長フレデリック・レイトン卿 Lord Frederic Leighton (1830-96)、アカデミズムの王道を世俗的歴史画によって開拓した巨匠ローレンス・アルマ=タデマ Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912)、そしてレイトン卿の跡を襲って1896年にアカデミー会長となったエドワード・ポインターSir Edward John Poynter (1836-1919)の三人とひとくくりにすることには、直感的に奇異の感がある。
というのも、ウォッツは最晩年に近い1902年に日本の文化勲章に相当する騎士団勲章 Order of Merit は受けたものの、ヴィクトリア女王からの準男爵位下賜を断った在野精神あふれる信念の人だからである。
画家としてそれなりの成功を収めた晩年には、慈善事業への寄付を欠かさなかったと言われている。彼はまた英国における象徴主義の先駆者という、もう一つの側面を併せもつ画家という評価がなされてきた。
英国でこの時代の絵画史の最高権威の一人とされるクリストファー・ウッド Christopher Wood の『英国美術事典』第四巻をなす『ヴィクトリア朝の画家たち その2:通史と図版』Victorian Painters 2: Historical Survey and Plates in Dictionary of British Art Volume IV (1995)を筆頭に、こうした扱いが標準である。
同時代のフランスやベルギーの画壇に興った象徴主義との関連付けは自然な成り行きといえるかも知れない。
日本の美術史家の間でも、多少のニュアンスの違いはあるが、この分類が踏襲されているようだ。代表的な例を一つ挙げれば、小学館『世界美術大全集』西洋編第24巻(1996年)の「イギリスの世紀末芸術」の項目を担当した荒川裕子氏は、ウォッツが抽象的観念の視覚化を志向する「象徴主義に接近して」いったことに触れながら(279〜80頁)も、基本的にレイトン、アルマ=タデマ、ポインターにアルバート・ムーアやウォーターハウスというヴィクトリア朝古典主義の代表者たちを加えて、一つの流れと見る。