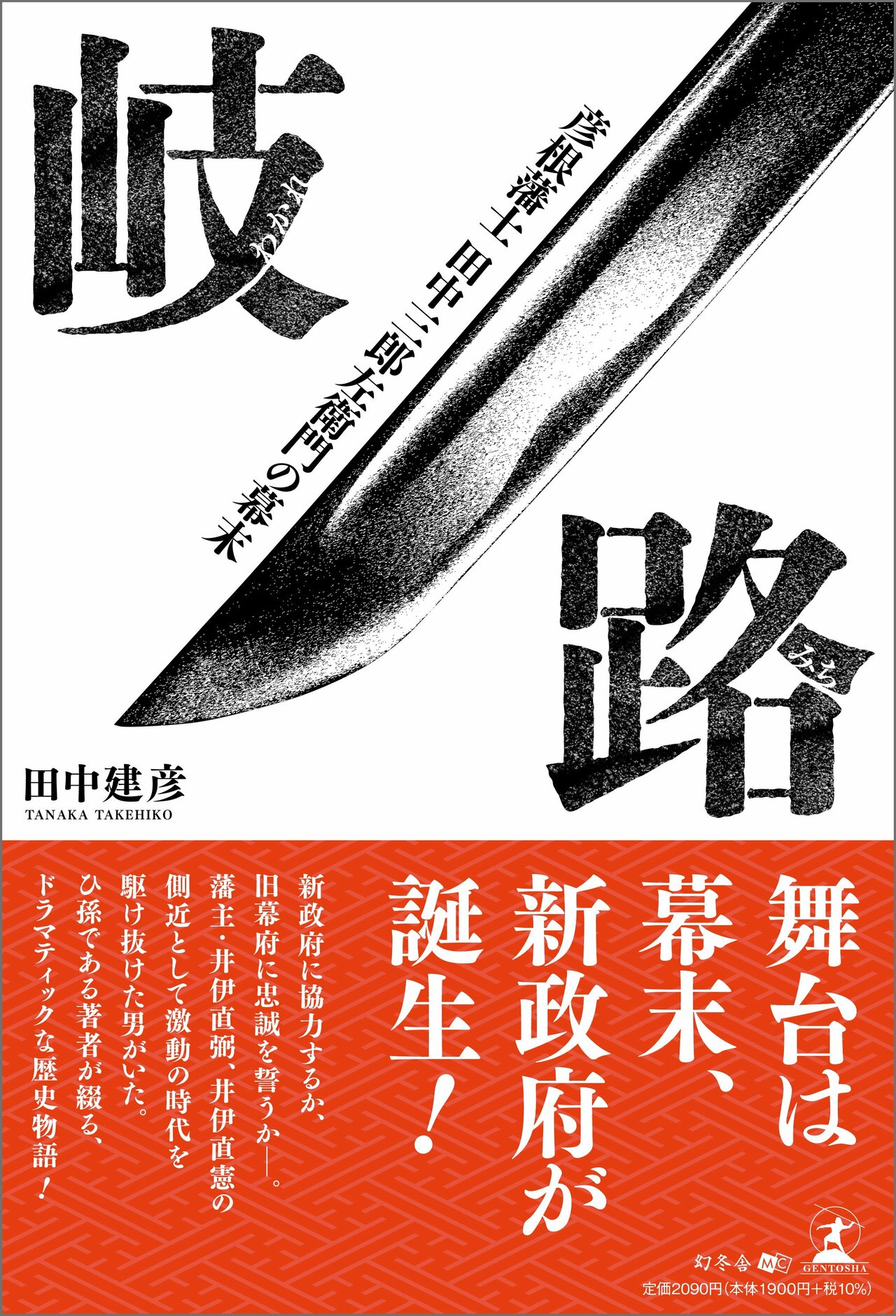彦根藩では小姓になると役料として百俵八人扶持(ふち)が与えられる。特に定員はなかったが、扶持を与えるので藩の経済上無限に小姓の数を増やすわけにはいかない。
徳三郎はいわば空き待ちの状態だったのである。なぜ江戸に呼ばれるのか分からなかったが、小姓としての召出しの可能性が高い。
彦根藩士には知行取りと言われる知行地を与えられている藩士が約五百人いたが、その内三百石以上の武役席に属するものは約百人であった。
父は、二百五十石であったが、特に「三百石以上の扱いを許さる」ということで、武役席に属していたのである。
というのも、もともと田中三郎左衛門家は家禄として三百石の知行を与えられていたが、父の先代が今村源右衛門家から来た養子で、家庭内で何かごたごたがあったのであろう、田中家を出て今村家別家を立てることになって家を去っていった。
そのためやむを得ず松居助内家から幼年の熊次郎を養子にもらい受けて田中家を存続させることになった。この時、幼年養子ということで三百石から二百五十石に減らされたのだった。
しかし武役席としての待遇は維持された。その熊次郎の子である父は少年時代から藩校での成績がよく、早くから近習に召し出され、以後中屋敷留守居・筋奉行・小納戸役・表用人などを歴任し、この時また小納戸役に戻っていた。
武役としては母衣(ほろ)役・鉄砲足軽三十人組を預かる物頭 (ものがしら)であった。
父は近習として、藩主井伊直亮 (なおあき)と共に行動し、この数年は一年おきに江戸と彦根の間を行き来していた。
すなわち天保六年藩主は就封し彦根にいたが、この年は中筋奉行、翌年殿が参勤のために江戸に赴くと、小納戸役として随伴し、その年には江戸で表用人を務めていた。さらに、翌八年殿が就封し彦根に戻っている間は大津藏屋敷奉行に役替えとなった。
翌十年の九月、父は再び小納戸役となり、江戸に行く殿の御供を命じられたが、徳三郎が江戸に呼び出されたのはその翌年の二月だった。