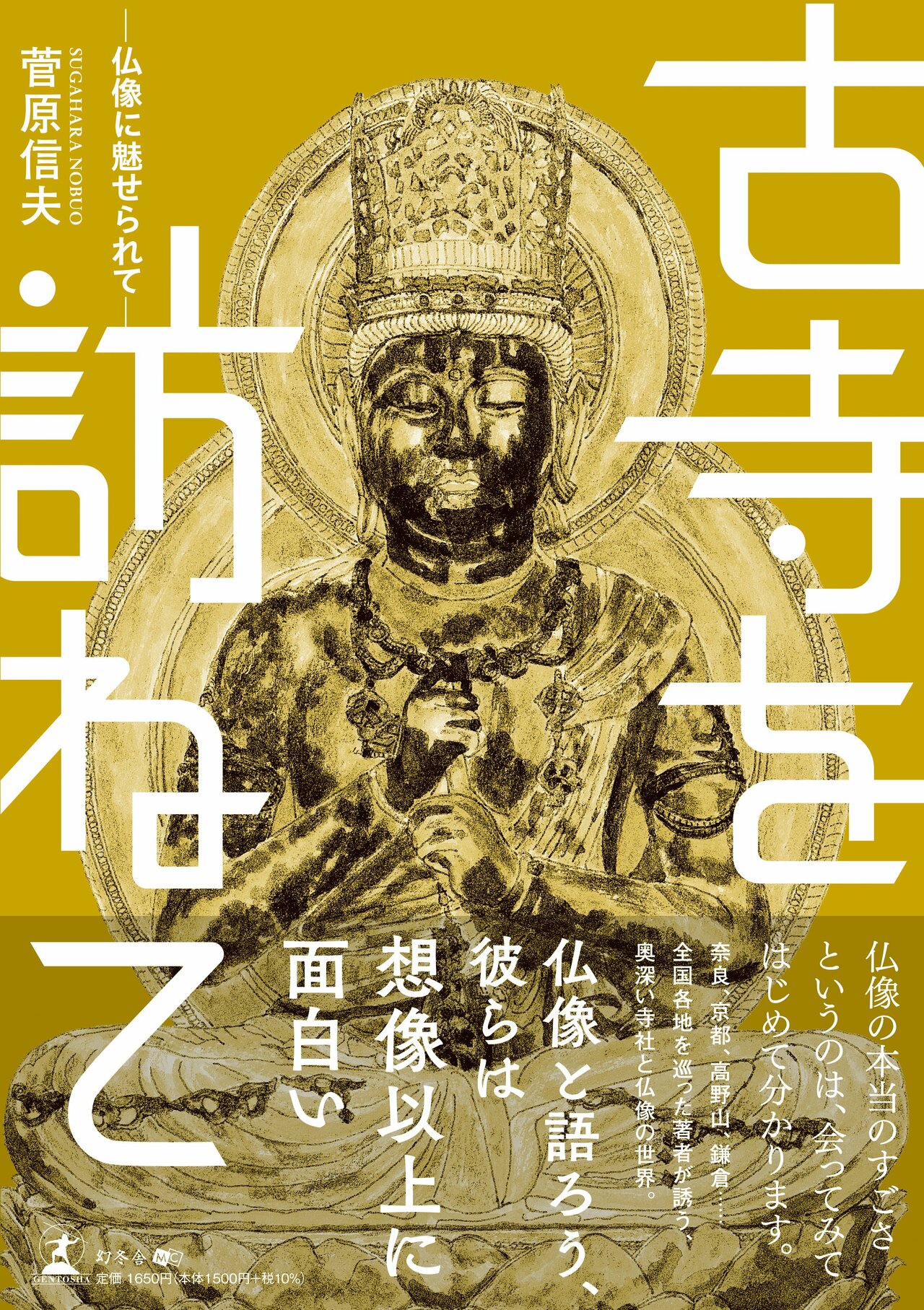此岸から彼岸に向かい、九体阿弥陀堂に入れば、2体は修復中ということで、ひときわ大きい中尊の左右に3体ずつ阿弥陀如来が並ぶ。それぞれの仏の真向かいに座って、その姿を間近に拝むことができる。阿弥陀如来の印相は九つの段階に応じて異なると思っていたが、実際はそのような作例は少ないらしく、ここの中尊は来迎印(らいごういん)、他はみな阿弥陀定印(じょういん)を結んでいた。
堂内には他に、四天王(してんのう)(国宝)の持国天(じこくてん)と増長天(ぞうちょうてん)が安置されている。広目天(こうもくてん)は東京国立博物館に、多聞天(たもんてん)は京都国立博物館に出向(しゅっこう)されているらしい。
また、厨子(ずし)が開扉(かいひ)され吉祥天(きっしょうてん)が特別公開されていた。どっしりとした阿弥陀仏とは対照的に小ぶりだが、色白でふくよかな顔をしている。私はこんなに肌の白い仏像は拝見したことがない。秘仏として保存されてきたためか、衣の色も鮮やかに残っている。
当尾の里にはたくさんの石仏が点在する。昔、東大寺再建のために宋から多くの石工(いしく)が来日した。彼らは花崗岩(かこうがん)の彫刻技術に長(た)け、再建後、花崗岩が多い当尾で、彼らやその子孫が石仏を彫ったといわれる。
まず木津川市コミュニティバスで岩船寺(がんせんじ)へ向かい、岩船寺から浄瑠璃寺へ戻るように石仏を巡ることにする。岩船寺には、本堂に本尊阿弥陀如来と四天王、普賢菩薩(ふげんぼさつ)、如意輪観音菩薩(にょいりんかんのんぼさつ)、十一面観音菩薩(じゅういちめんかんのんぼさつ)、十二神将(じゅうにしんしょう)などが祀られていた。
岩船寺から山道を上り、まず三体地蔵磨崖仏(じぞうまがいぶつ)。過去、現在、未来を割り当てた地蔵菩薩が岩肌に彫られている。ゆるやかに下って、巨岩に線彫りされた弥勒(みろく)磨崖仏。やさしい微笑みで「わらい仏」といわれる阿弥陀三尊(さんぞん)磨崖仏。隣に首まで土に埋まった地蔵菩薩。こちらは「眠り仏」と呼ばれている。
次に阿弥陀・地蔵磨崖仏。そして、岩に舟形の光背(こうはい)を彫り込み、地蔵菩薩と十一面観音、その左に阿弥陀仏と、珍しい配置の石仏といわれる三尊磨崖仏を最後に浄瑠璃寺に戻る。
浄瑠璃寺からバスに乗って近鉄奈良駅で下車し、今夜の宿へ向かう。明日は吉野の金峯山寺(きんぷせんじ)を訪ねる。