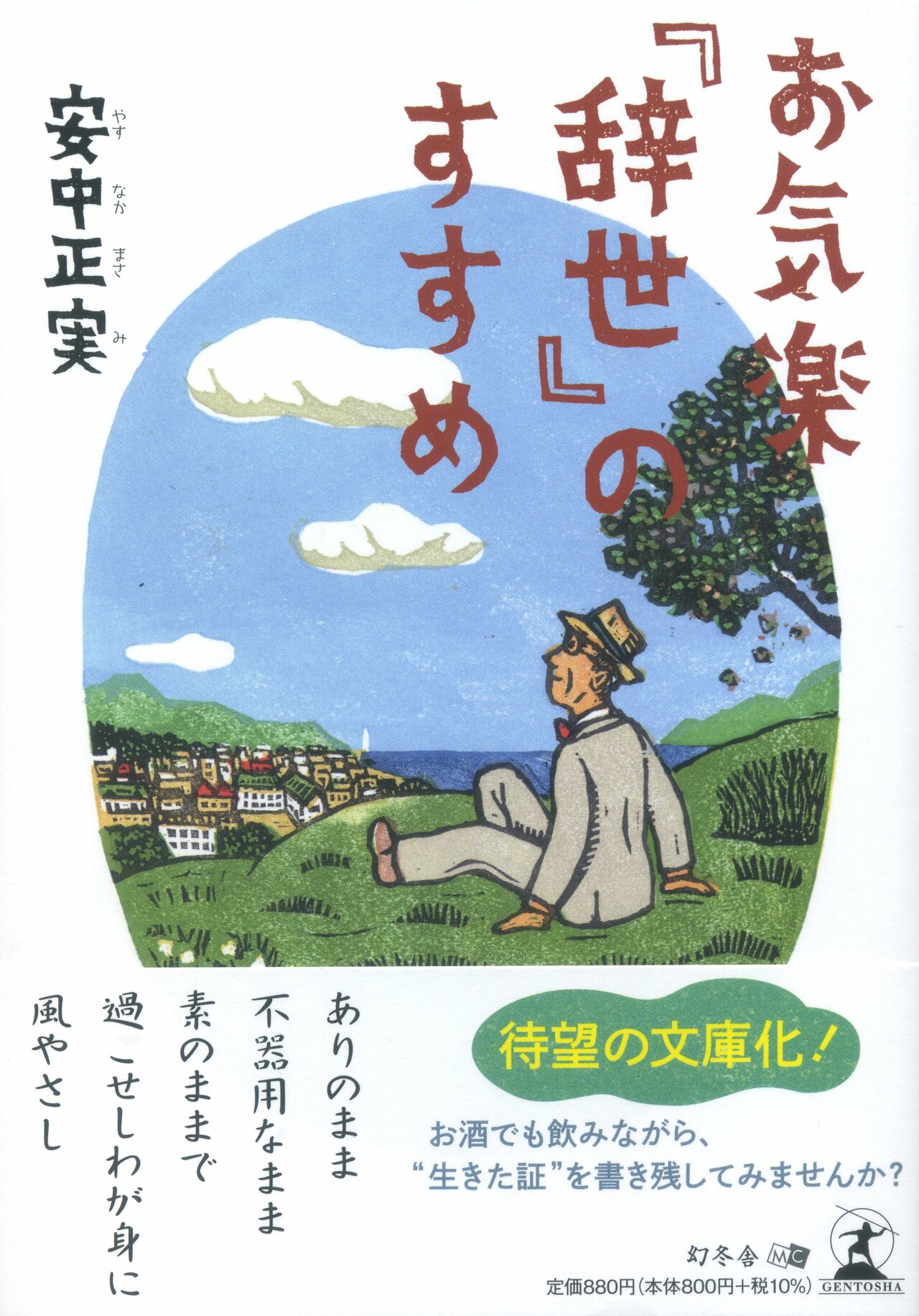そのように考えると、生きた証しというのは、個人的に子や孫に残すのではなく、まず、自分の心の中に刻み込み、場合によっては、自分の名前とともに世の中に広がり、さらに場合によっては、それが後世にまで残ってしまう、という代物のようである。
勲章に「死亡叙勲」というのがあるが、奥さんが代わりに授与されて「へぇ、あの人偉かったのネ。」と思ってもらっても、本人はすでにお亡くなりだから、嬉しくも何ともない。
やはり、「生きた証し」とは、どんな些細なことでも生きているうちに、少し誇らしげに自分を誉めて、自分に祝杯をあげることができれば「それで良し」程度を目指すのが、無理がないのだろう。この程度であれば、皆さんの中には、すでに生きた証しと言えるものを残されている方もおいでだと思うが、いかがであろうか。
「生きた証し」が何であるかは、自分が満足できるものを自分で決めればいい、という程度までハードルを下げてみた。そうであれば、子や孫もなく、ましてや社会に残すものも何もないと少し悲観されている方も、‘ぼちぼち’を意識されたとき、遊びだけでなく、いや遊びながら「生きた証し」を創作されればいい。
そんなに難しいことではない。手始めにネットで自分の名前を検索してみれば、思わぬ情報が引っかかったりする。何もないと思っていても、たとえばサークルやスポーツクラブ、あるいは町内会のホームページに、あなたの名前と活動記録が載っていたりする。それらの記事は、削除されない限り残る。
それで満足されれば、自分の生きた証しは、何とかクラブのホームページにあると仰ればいい。これは生きた証しとは言えないと思われれば、遊びを兼ねて何かを始めればいい。そのときは、純粋に遊びを楽しむことに加えて、結果として生きた証しが残せるという思いが加わり、その遊びの楽しさは倍増する。
子や孫になど何も残さなくていい。あなたの人生の締めくくりに、どんなものであれあなたでなければできなかった生きた証しを、あなたの満足とともに残せたら、それで上等である。加えて、あなたの残した「生きた証し」のおかげで、誰かが少し喜んでくれる、何かが少し良くなっている、なんてことがあれば、それは最上等である。