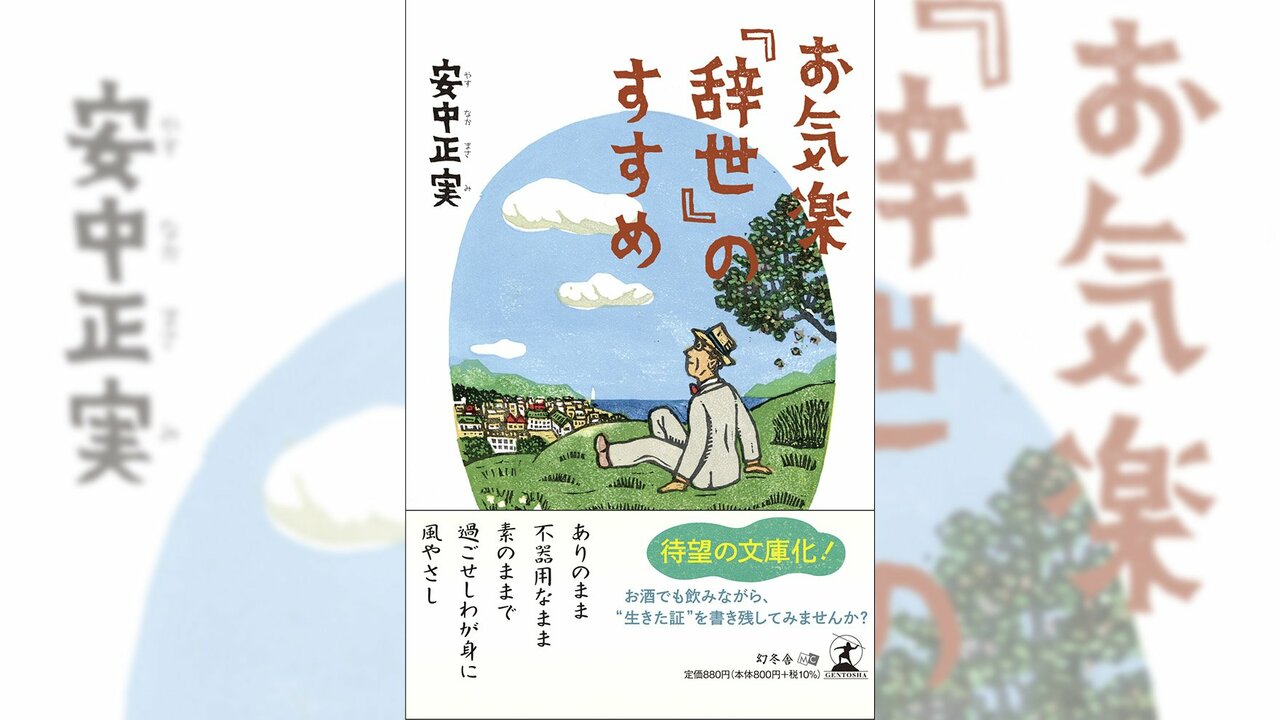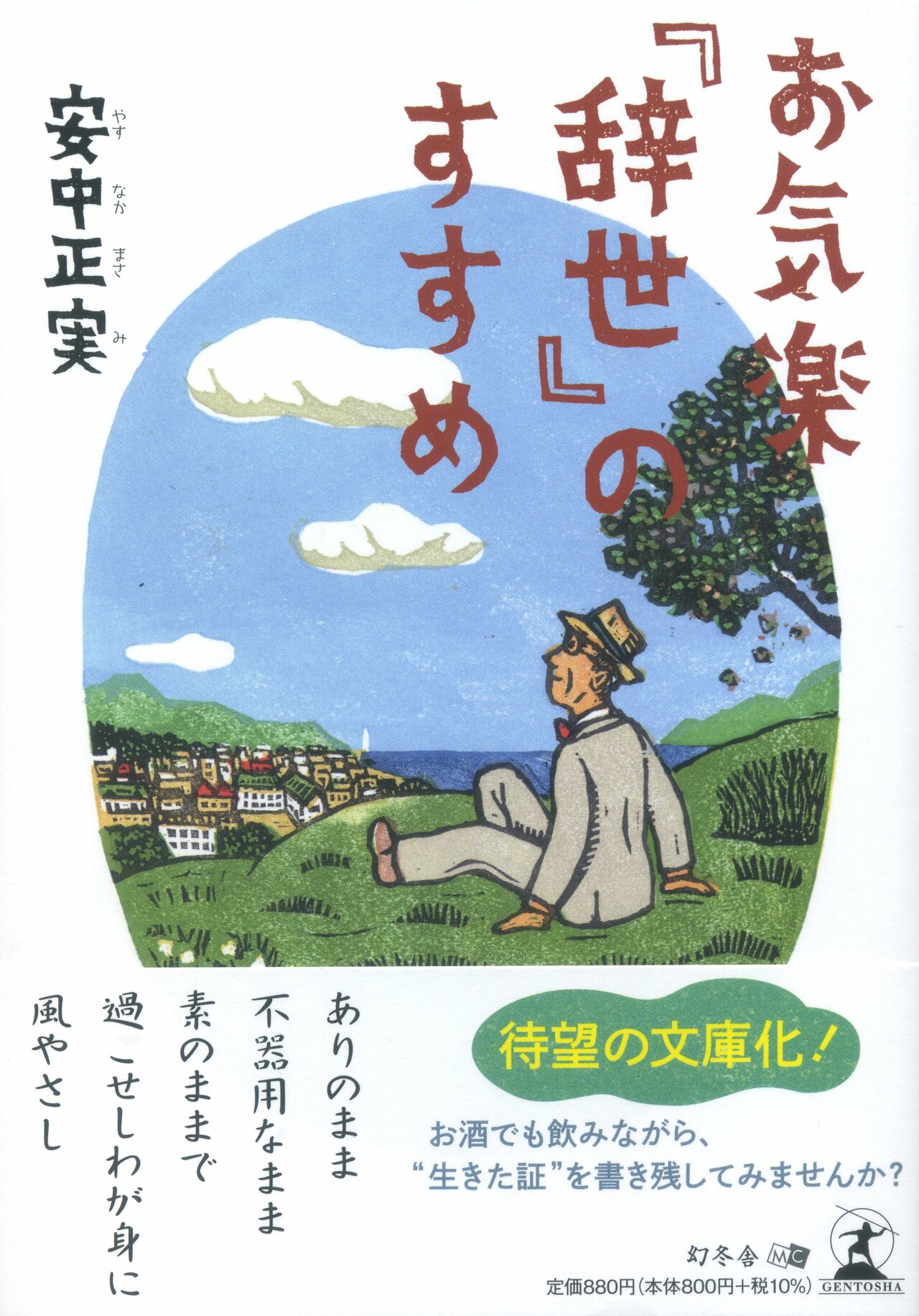【前回の記事を読む】情報の整理はエンディングノートにまとめられるが、あなたが大切に管理している雑多なモノは、残された人にとってゴミ同然だ。
1 さて、お別れに、何を残そうか……
(5)ぼちぼちかなと思うとき
この話を知ったとき、古典落語「死神」の命のろうそくに当たるものが、現実にあるのかと驚いたものである。この落語は、ひょんなことから死神が見えるようになった男が、病人の足元に死神が座っていればその病人は助かることを教えてもらい、金儲けをするという話である。
大金を積んだ旦那の見立てに行くと死神が枕もとにいる。男は、死神をだまして旦那を助け大金を得るが、それは自分のろうそくを旦那に継ぎ足したことになり、ろうそくの火が「あ~消える」というあらすじである。
人間の寿命は、それぞれのろうそくの長さで決まる。その火が燃え尽きたら死ぬ、というのは、そのままテロメアを意味するようにもとれる。
しかし、テロメアやろうそくの長さを気にして生きるのは、空しいと思う。明日、消えるかもしれないろうそくの命で、10年後あたりにʻぼちぼちʼを考えなければいけないなと思いながら、楽しいことを企てて生きるのが、人間の愛おしいところではないだろうか。
(6)あなたの生きた証しは何? ――「残す」ということ
おことわりをしておくが、私は死に臨んで何かを残すということは女々しい(女性の方々、ごめんなさい)と思っている。ひとりで裸で生まれてきたのだから、ひとりで何も残さず静かに死んでいくのがカッコイイと思っている。しかし、残念ながら私にはすでに子供も孫もいる。ということで、子孫は残してもいいということにする。
話の流れで自己弁護のようになるが、子孫は残すのが当たり前であった。我が国では、「家を継ぐ」ことが重大事であり、男は妻を娶って男児を儲けることで体面を保つことができ、それで一人前という考え方がついこの前まで常識であった。
継ぐべき家名や家業を背負わされる方は、それを喜びとしたのか、迷惑と思ったのか、あるいは何も考えず当たり前と思ったのか、私には分からない。
我が国で特記すべき世襲は天皇家であるが、他にも、歌舞伎や能など子供のときから訓練が必要な芸能、神社の神主やお寺の坊さんなどで、世襲の習慣があった。そのような親譲りの仕事をしている人たちは、それなりに誇りや意義を見出しているようで、迷惑に思っている人は少ないようにも思える。あながち、世襲も悪い制度ではない。