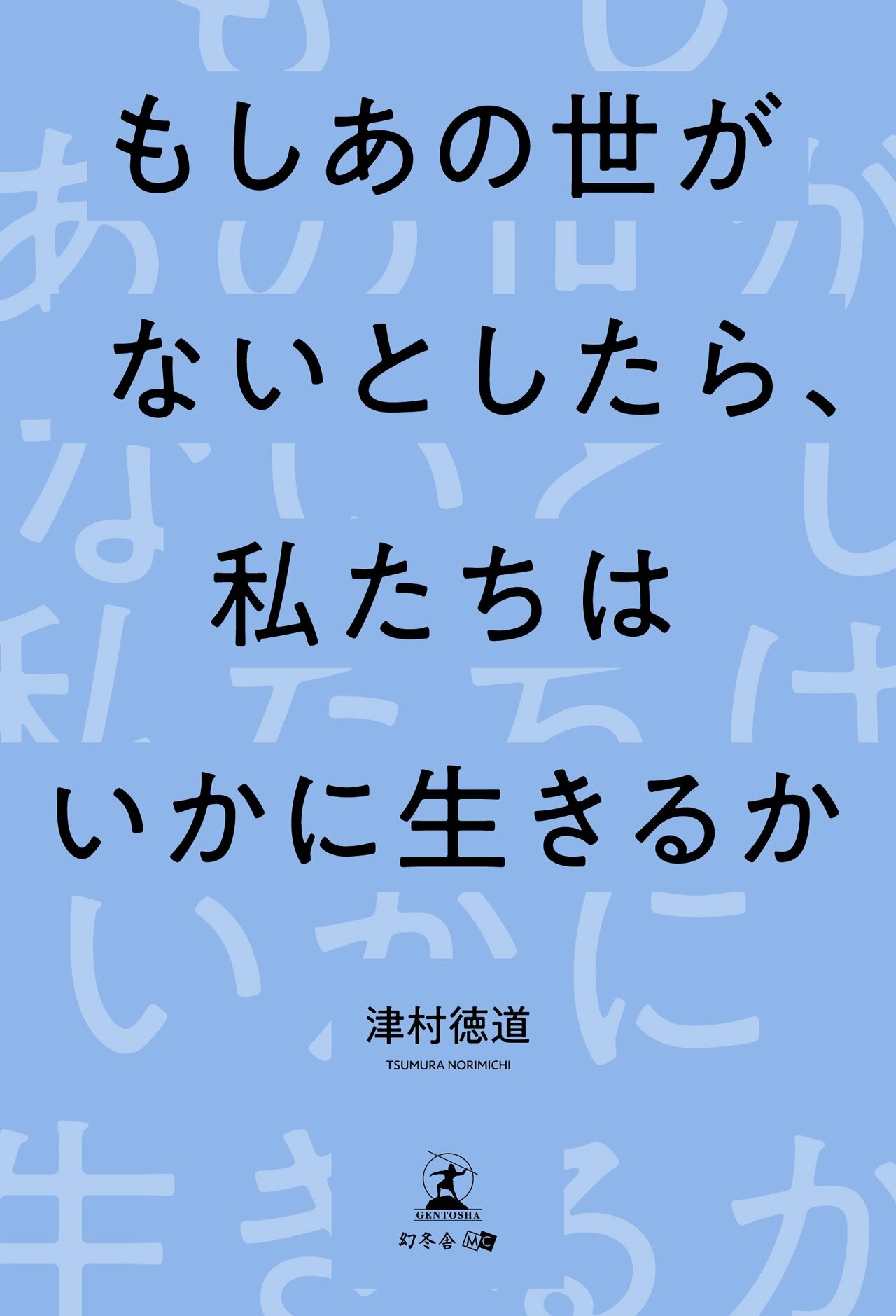津村:はい、人間です。人間は地球上で淘汰の歴史を生き残って、生物の頂点のような位置にいます。淘汰の歴史を紡ぐ中で、私たちはいろいろなものを身に付けました。
人間としての体、本能などは生き残る上で重要でした。本能の重要性を簡単に説明すれば、足を大けがして流血しても痛みを感じず、まだ活動する人間は大量流血で死んでしまい、淘汰の歴史から消えてしまいました。痛みの感覚など、淘汰の歴史から生み出されたこのような仕組みの話はたくさんあります。
学生:確かにそうですね。本能は生物が生きる上で重要ですね。
津村:でも問題もあります。同じ話で続けると、痛みというのは人間にとって貴重です。でも、その痛みが余計なところで人々を苦しめます。痛みで病を認識するのはよいのですが、その痛みを病の間は背負っていかなければいけない場合も多々あります。大変つらいですよね。
学生:痛みを感じることは生存に重要ですが、どうしてもその痛みが副作用として人を苦しめるということでしょうか?
津村:そうです。実は、痛みを感じないようにトレーニングすることも可能な場合もあるのですよ。痛みは脳で感じているので、それを感じないように、学習することも可能なのです。スポーツで集中しているとき、怪我をしていても痛みを感じないときがありますよね、あれと似たような感じが一つの方法であると私は考えています。
また人類はこのトレーニング方法を開発できると私は考えています。したがって、痛みの利点は生かしつつ、痛みの副作用を抑えることは可能だと思います。
学生:ぜひそのトレーニング方法を知りたいです。
津村:残念ながら、まだ民間療法的な感じで、経験的なものです。本能と環境の相互作用などをもっと科学することで、より良いトレーニング方法が出てくると思います。本書の続編でぜひまとめることができればと思います。
学生:まだなのは残念ですが、今後に期待しています。
津村:本書では、より良いトレーニング方法を考えるために、まず自殺について話します。
学生:またまた、極端な展開をしますね。
津村:極端な例から考えることは一般化への近道だったりするのですよ。