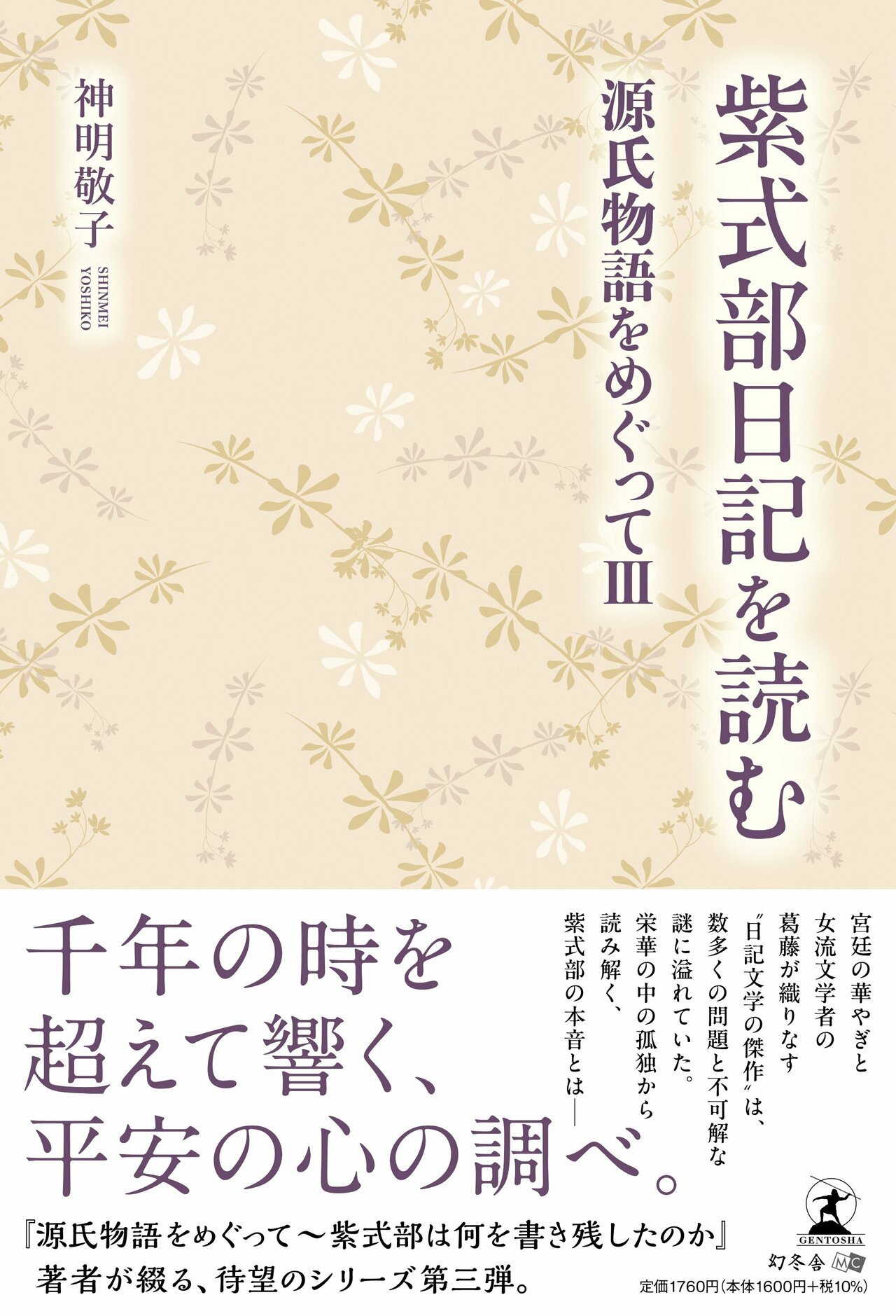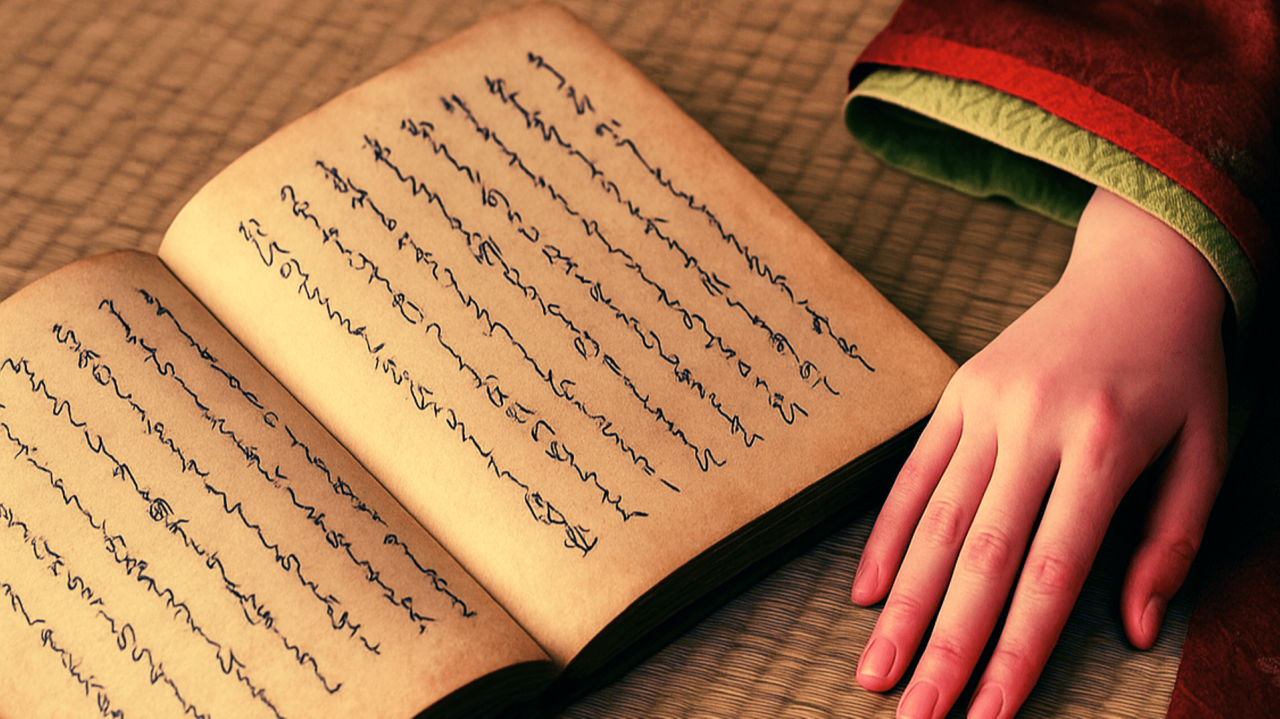大式部のおもとについて、「殿の宣旨」だと説明しているが、土御門邸の内部の人であれば、知っているはずである。大式部については、また次のように説明している。
大式部は陸奥(みちのくに)の守(かみ)の妻(め)、殿の宣旨よ。(一四四)
次の赤染衛門の説明も、相手が土御門邸の外の人であることを思わせる。
丹波の守の北の方をば、宮、殿などのわたりには、匡衡(まさひら)衛門とぞいひはべる。(二〇一)
作者は日記に登場する多くの人物について、相手が知らないと思われる人物について、詳しく説明している。
大左衛門のおもと仕うまつる。備中の守むねときの朝臣のむすめ、蔵人の弁の妻。(一三七)
少将のおもとといふは、信濃の守佐光(すけみつ)がいもうと、殿のふる人なり。(一四五)
別当になりたる右衛門の督、大宮の大夫よ。(一五九)
式部のおもとはおとうとなり。(一九一)
女房批評の箇所で、主な女房について詳しく説明しているのも、普段一緒にいない人
であるからだと考えられる。相手は、土御門邸の内部の様子も詳しくは知らない。
渡殿の戸口の局(一二五)と説明している。相手は作者が渡殿の局にいることは知っているかもしれない。ここでは、「戸口の局」であると、説明を加えたのではないかと思われる。
また、この渡殿の東(ひむがし)のつまなる宮の内侍の局(一六一)と言う。相手は宮の内侍の局が渡殿の東の端であることを知らない。知っていれば「宮の内侍の局」と言えばすむはずである。