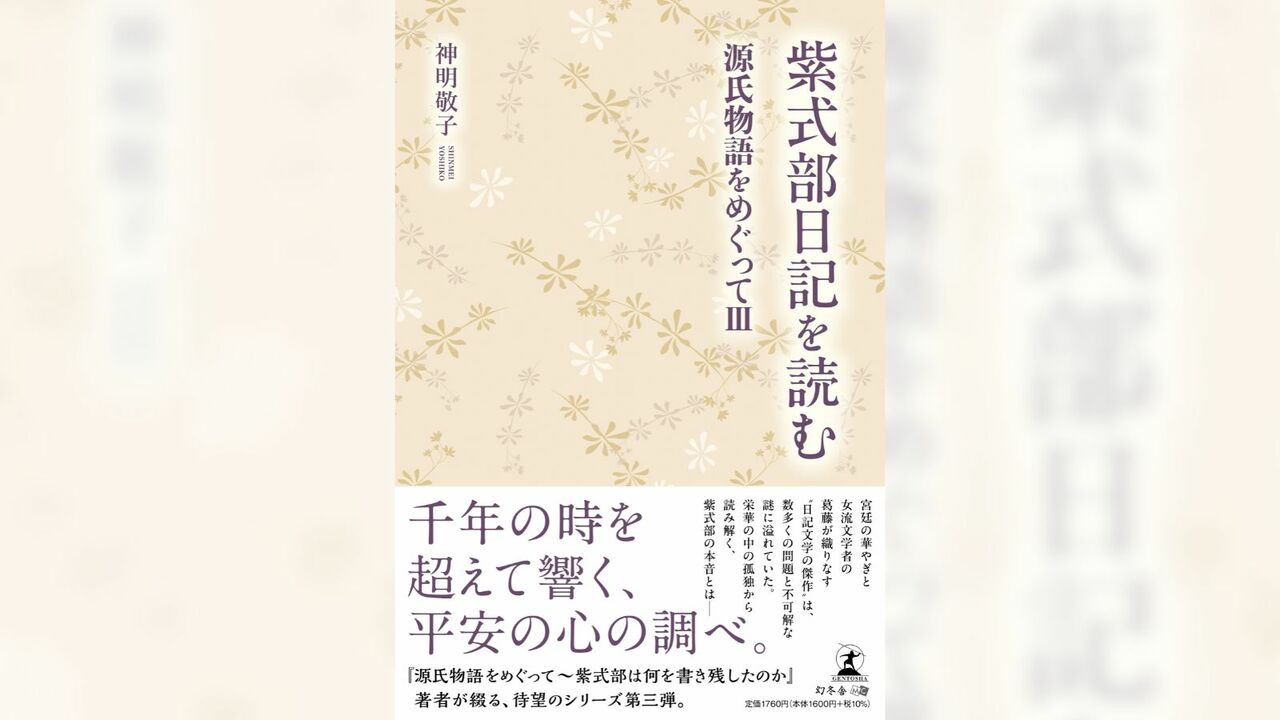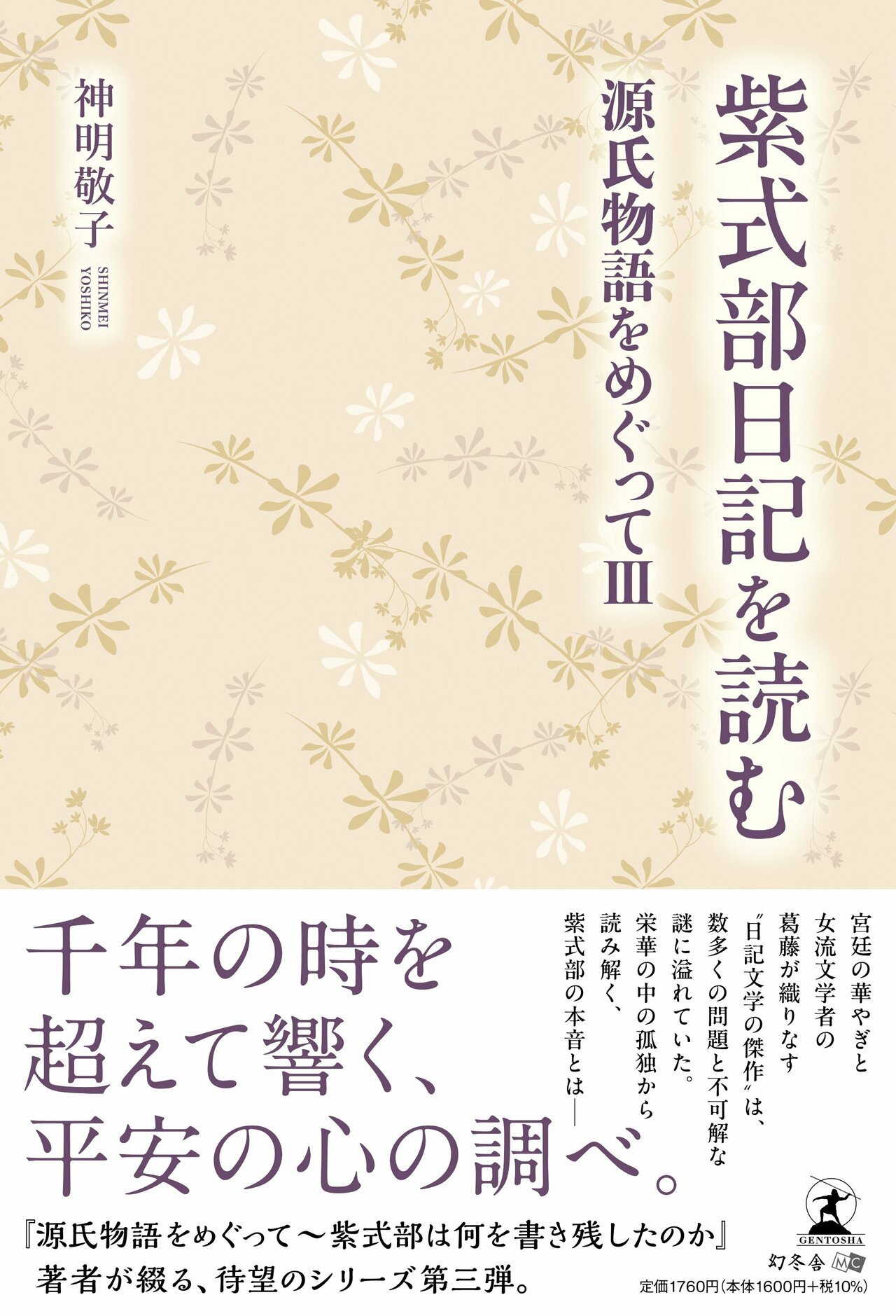【前回記事を読む】【紫式部の謎】生没年不明。出仕の年も確定せず、『源氏物語』のどの部分をいつ書いたかも不明。さらに『紫式部日記』には…
第一章 紫式部日記
一 現行日記に沿って
冒頭
日入り方になりゆくに、空のけしきもあはれに霧(き)りわたりて、(略)前の前栽(せんざい)の花どもは、心にまかせて乱れあひたるに、水の音いと涼しげにて、山おろし心すごく、松の響き木深(こぶか)く聞こえわたされなどして、不断の経読む時かはりて、鐘うち鳴らすに、立つ声もゐ代はるもひとつにあひて、いと尊く聞こゆ。(④四〇一)
「椎本」に、宇治の姫君たちを描く次の場面がある。この場面も、日記冒頭に似ている。
八月二十日のほどなりけり。おほかたの空のけしきもいとどしきころ、君たちは、朝夕霧のはるる間もなく、思し嘆きつつながめたまふ。有明の月のいとはなやかにさし出でて、水の面(おもて)もさやかに澄みたるを、そなたの蔀(しとみ)上げさせて、見出だしたまへるに、鐘の音かすかに響きて、(⑤一八八)
冒頭に似た情景が、「夕霧」「椎本」にあるので、冒頭の情趣は、第二部、宇治十帖に近いと考えられる。
「藤袴」の、八月中ごろの、柏木を描いた箇所に、
月隈なくさし上がりて、空のけしきも艶なるに、いとあてやかにきよげなる容貌(かたち)して、御直衣の姿、好ましく華やかにていとをかし。(③三四二)
とあり、このころの、月が出た空が艶だとされている。冒頭の艶なる空も、月が出ていて夜であることが考えられる。
日記の十一日の暁の箇所では、彰子が御堂に詣でるが、作者は、
それにはおくれて、ようさりまゐる。(二一二)
と夜になって参上している。十一日の暁の日記に描かれているのは、十一日の夜から十二日の暁にかけての出来事である。
はじめてまゐりしも今宵のことぞかし。(一九四)
と、初出仕も、寛弘五年十二月の出仕も、夜になってから参上している。
夜からの行事や、翌日の行事のための出仕は夜からであり、また夜を徹して仕えるための出仕も夜参上したと考えられる。冒頭の出仕も夜からであり、日記は夜から書き始められていると考えられる。