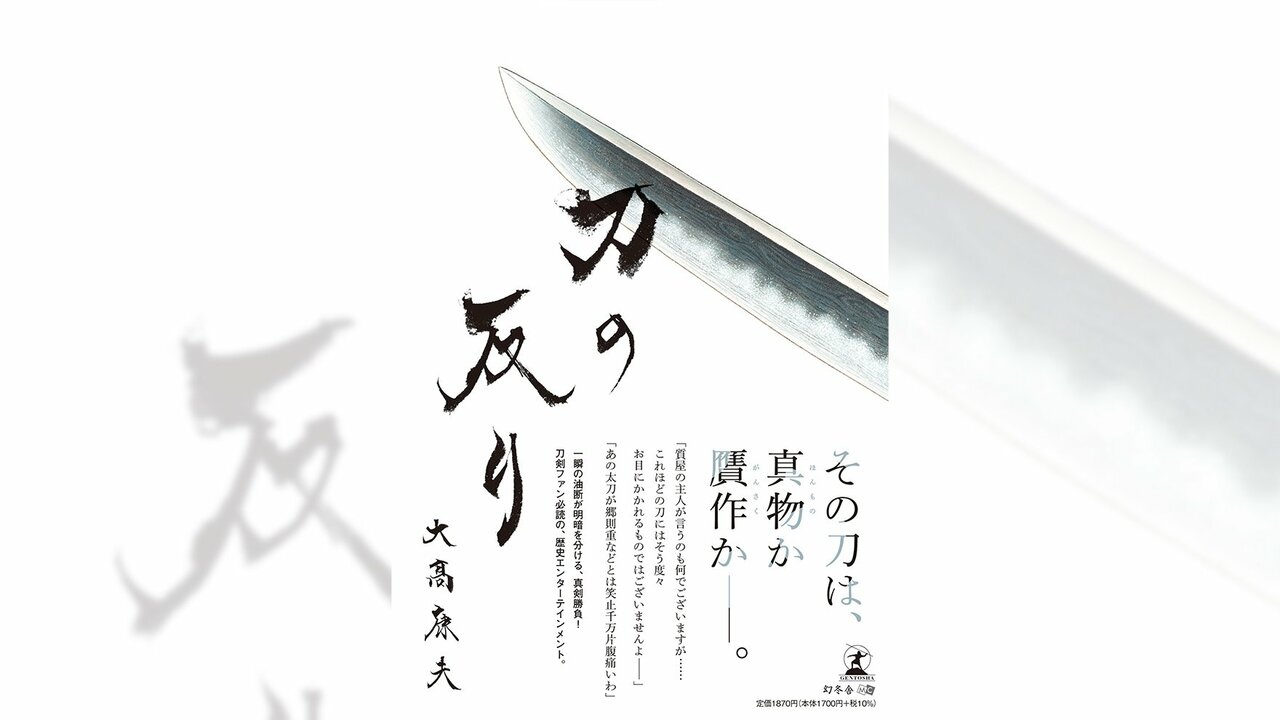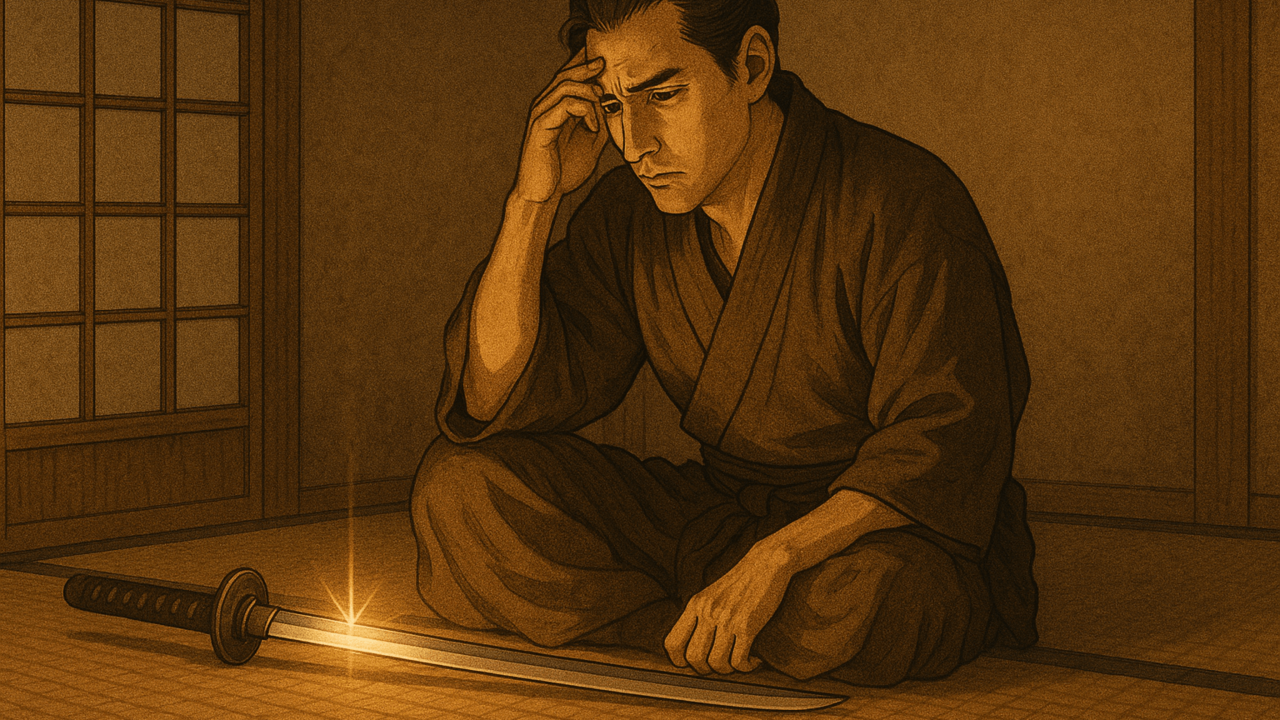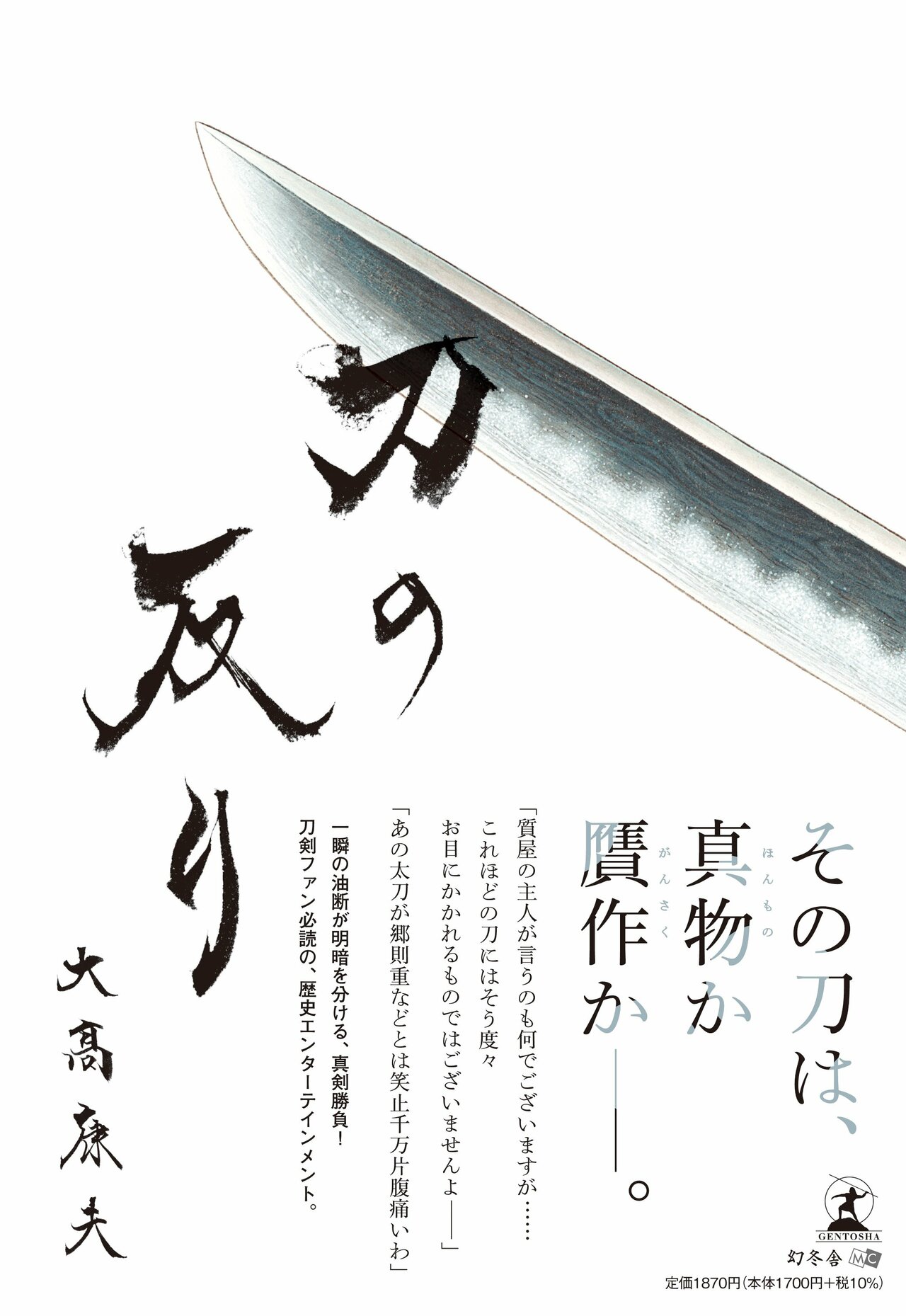【前回の記事を読む】「輿入れたときから覚悟していました。両家に何事か起ころうとも、この家を決して裏切るまいと。」夫が私の兄を斬ったとしても…
兆し
店賃(たなちん)の催促をしに来た大家の吉兵衛が帰って行く後姿を見ながら、ふと出奔した国元のことが猛之進の脳裏に浮かび上がった。
月日が過ぎるのは早いもので、あれから二年の歳月が過ぎようとしている。
江戸に着いて身の置き場所を見つけても懸念は払拭できず、郷田藩江戸藩邸の様子を窺ったりしていたが、今になっても国元から討っ手が出府したそれらしい気配はなかった。藩が差し向ける討っ手が誰なのか凡その見当はつけているのだ。頭に浮かぶ相当の剣の遣い手は郷田藩にも何人かはいる。
だが、手練(てだ)れといわれる男たちが何人差し向けられようと手当たり次第返り討ちにしてくれよう。脱藩し落ちぶれようとも国元では小天狗と持て囃(はや)された一頃もあったのだ。その当時に比べ腕の覚えに多少の衰えがあろうと、弥十郎という遣い手がいなくなった今、猛之進は恐れる者などいないに等しいと思えるほどの自信に満ちていた。
当然それは積み重ねてきた剣技に裏打ちされたものでもあった。果たして討っ手は身近に迫っているのだろうか。それとも国元で変事が起こり、猛之進ごときに構ってはおられなくなったということなのか。
いや、それはあり得ぬことだ。藩が討っ手を差し向けることを躊躇(ためら)おうとも、谷口の家では弥十郎の仇討をしなくては生き恥を晒(さら)すことになる。また、藩もそれを許さぬであろう。戦国期の慣わしが今尚残る郷田藩としては武門の一分(いちぶん)が立たないからだ。それに、あの谷口の家が弥十郎の仇討を諦めるようなことは決してあるまい。来るのは弥十郎の弟万次郎に違いなかろう。
彼(か)の男など何人来ようと物の数ではない。藩では助太刀をと考えるやもしれぬ。来るなら来れば良い。万次郎に助勢する者がいかに行く手を阻もうと片っ端から斬り捨ててやる。それに、谷口の血筋に弥十郎に勝るとも劣らぬ剣の遣い手がいるとは聞いたこともない。