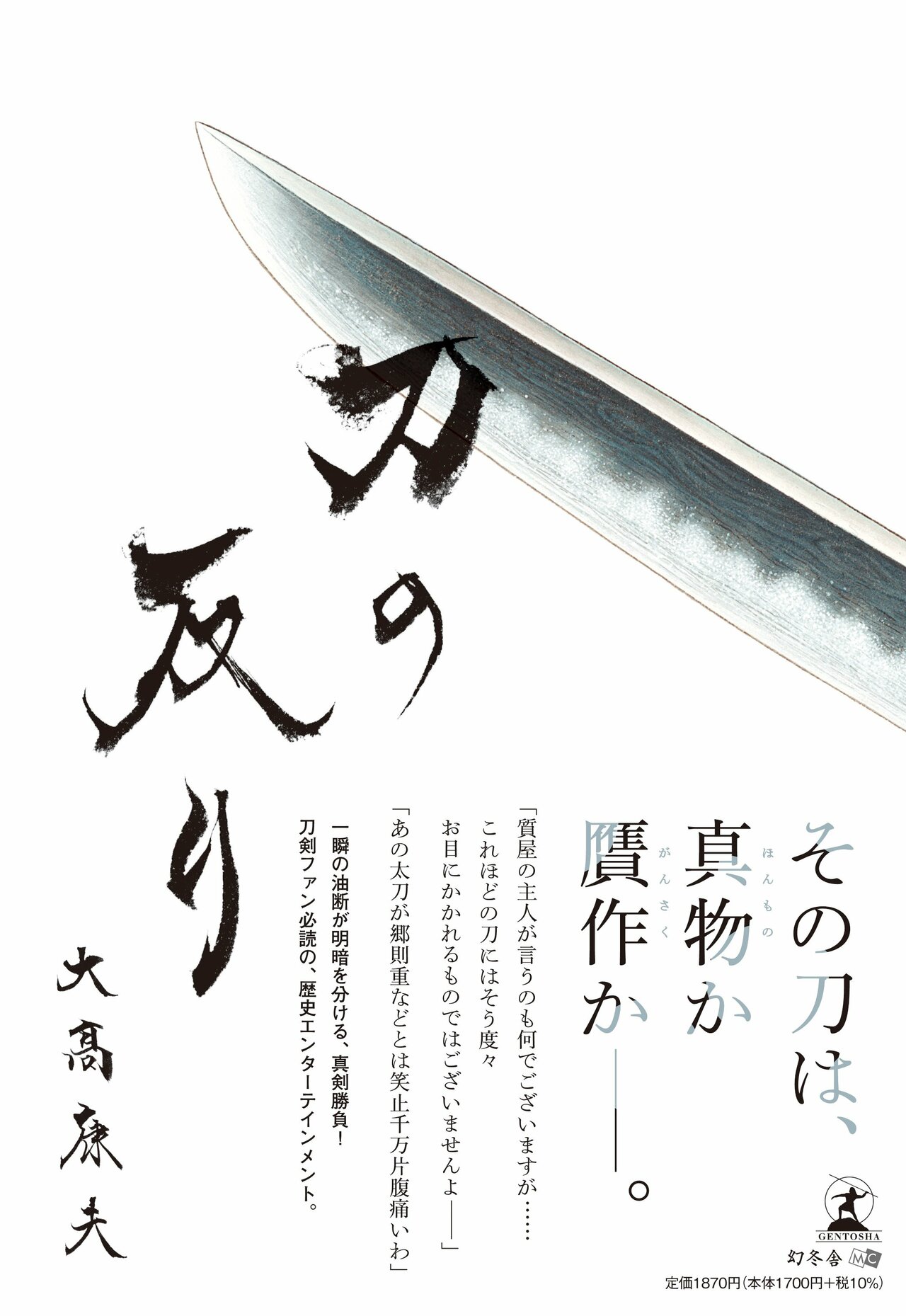【前回の記事を読む】「たった今、人を斬ってきた」「いったい誰を?」答えないまま、夫は私の手を取った。荒い息遣いで布団の上に押し倒され…
命運
「いいえ、わたくしは須田の家の者です。おまえ様の振る舞いはわたくしの振る舞いなのです。それに、須田の家に輿(こし)入(い)れたときからある覚悟を決めて参りました」
「覚悟……何だそれは……」
「両家に何事か起ころうとも、わたくしは須田の家を決して裏切るまいと誓を立て輿入って参ったのです」
「ほほう、それは結構なことだ」
この時代、婚姻には互いに好き嫌いなどの感情は余計なものであった、況してや武士の家ともなれば世継ぎを重要視しており、女子は子を産む道具に等しいものであったことは是非もないことである。
「おまえ様……大目付の村上様にはお届けになるのですか」
「いや、届け出はせぬ」
「それではどうなさるおつもりなのです」
瑞江は思わず咎め立てる様なきつい口調になる。
「どうするも何も……藩では私闘を固く禁じておるのはそなたも承知しておろう」
「はい、届け出れば何らかのお咎めは免れないとおもいます。まずは良くて両家に閉門。悪しき事となれば、喧嘩両成敗にておまえ様はお腹を召すことになるやもしれませぬ。そうなれば須田の家は断絶」
瑞江の目から見た猛之進の顔が歪んだように感じられた。
「どちらにしても須田の家が滅ぶのは免れまい。この場でそれがしが腹を切れば谷口の家はそのままで済むかもしれぬな」
猛之進はそう言ったまま懐手(ふところで)をすると目を閉じた。暫くじっと考え込むように沈黙した後、目蓋を開けると意を決したように言い放った。
「わしは出奔(しゅっぽん)する。それが一番良い方法だ。弥十郎を襲ったあとそれがしが藩を出奔したとご重役方が知れば谷口の家には何の沙汰もあるまい。咎めは我が須田の家だけで済むであろう」
猛之進にしては意外な言葉を口にしたのだ。瑞江は内心で驚いていたが、そうしてもらえればとひとまずは安堵したのだった。まさか猛之進が谷口の家のことまで気にしていたとは思わなかったのである。