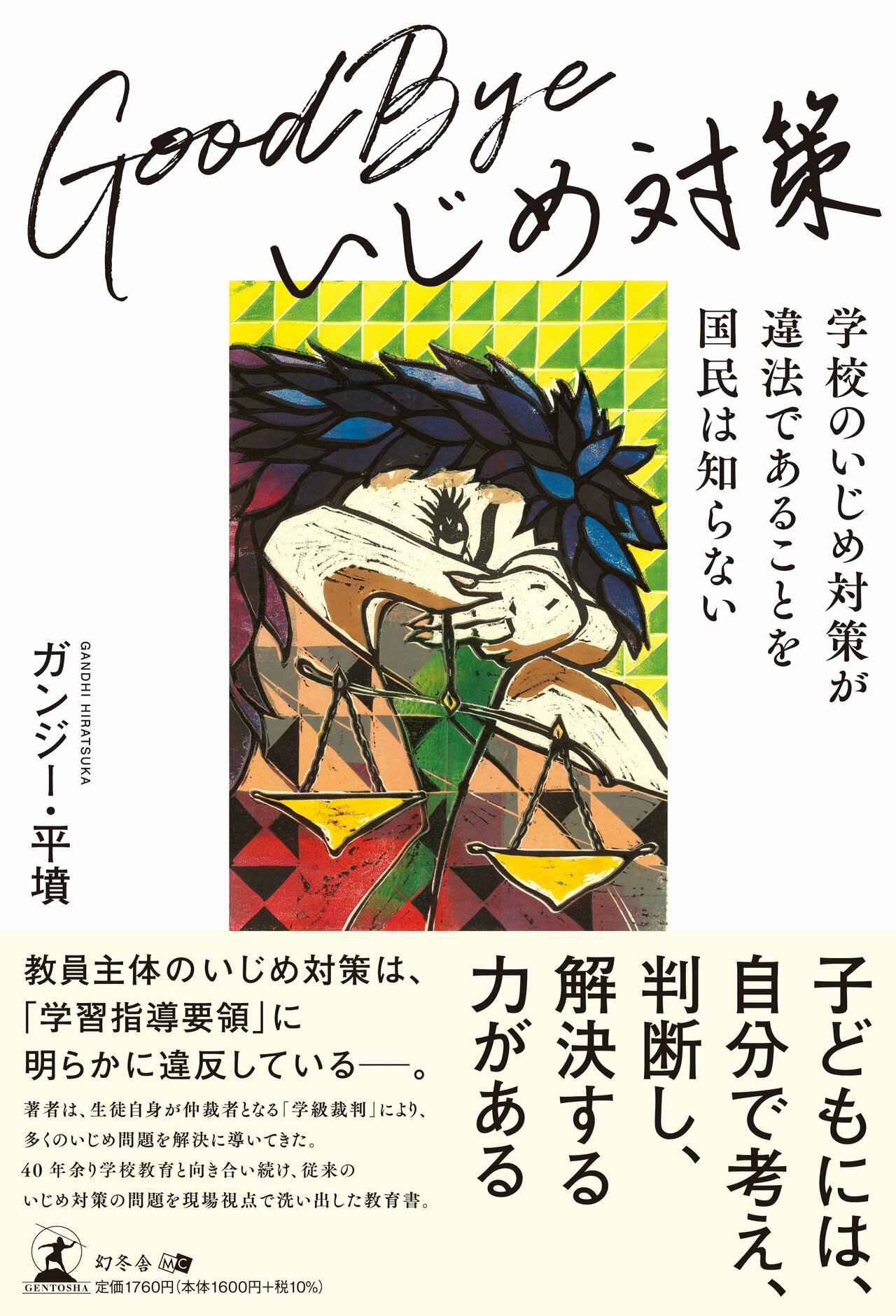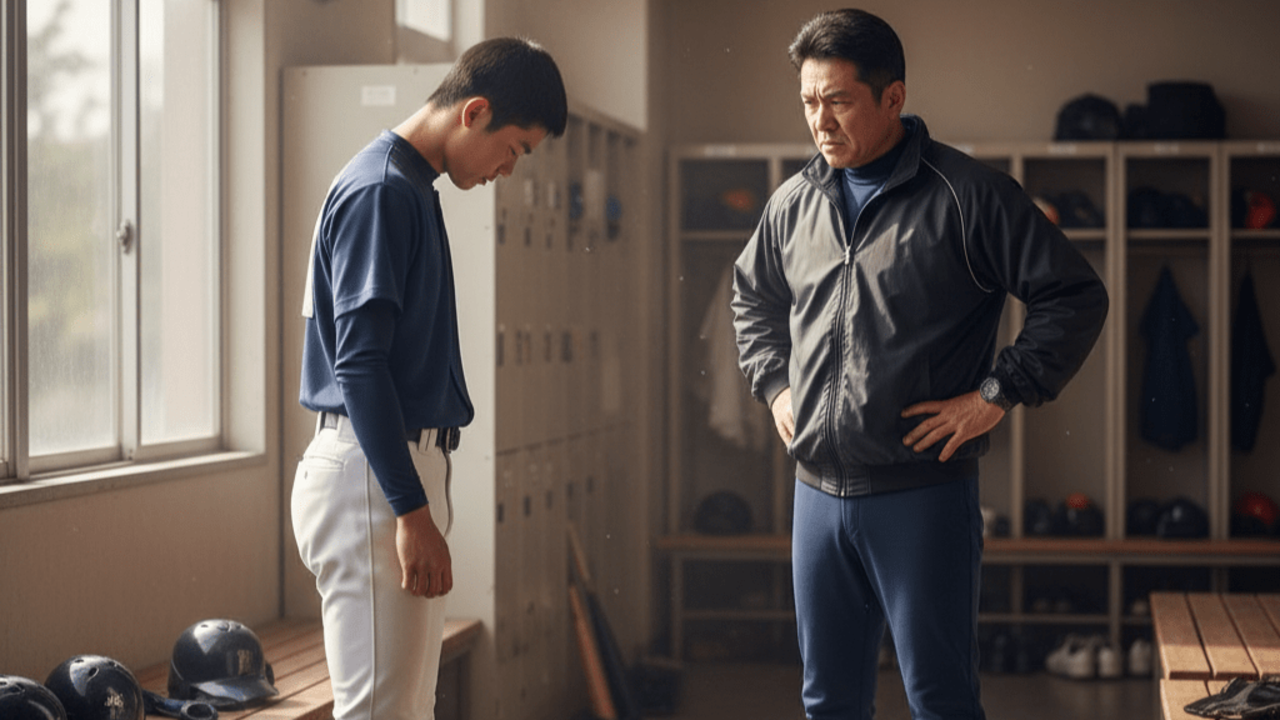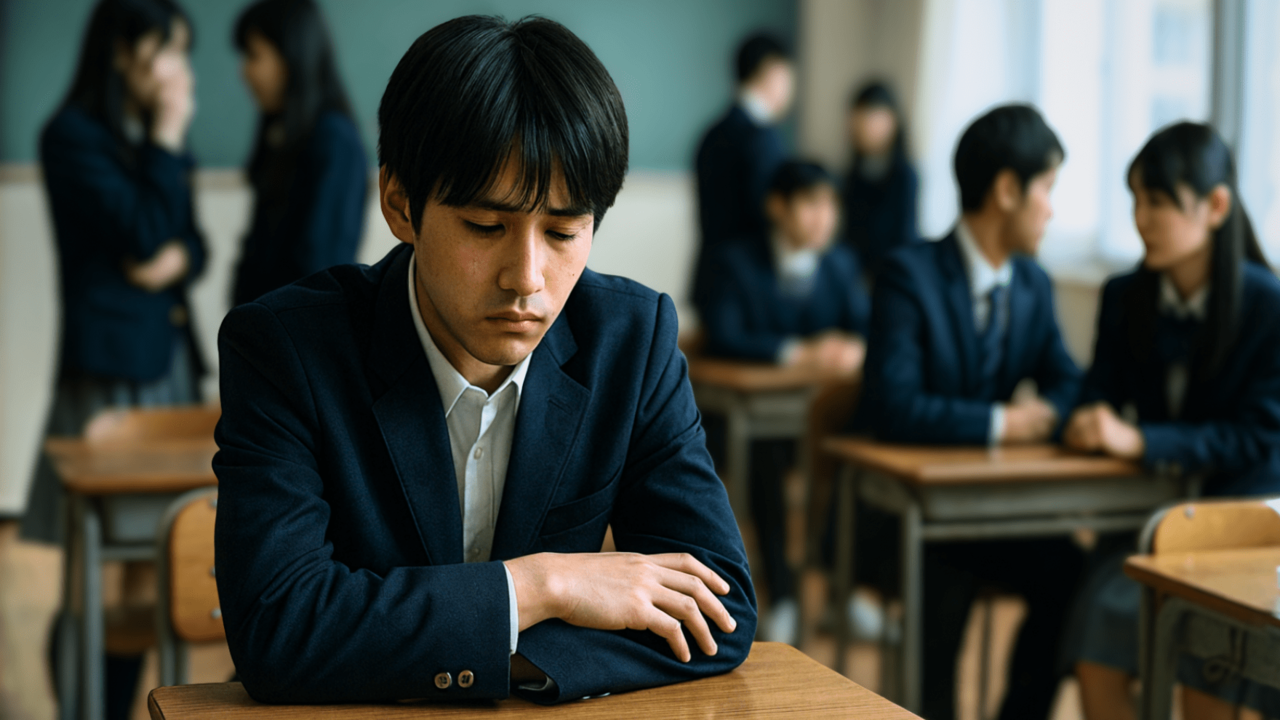迷走するいじめの定義と振り回される学校
では、その内容を見てみましょう。学校いじめ防止基本方針の冒頭にかならず記載されているのが「いじめの定義」です。
学校はいじめの定義から、「これはいじめだ」とか「これはいじめではない」などと判断して子どもの指導にあたります。
いじめの定義はこれまで昭和61年度、平成6年度、平成18年度、そしていじめ防止対策推進法の施行にともない平成25年度と計4回の見直しが行われてきました。
昭和61年度の定義は、「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とされました。
しかし先生たちからは、「確認しなければいじめと認めなくていいのか」とか「教師一人ひとりでいじめの判断が違う」などの問題が噴出しました。
その後、何度も削減や追加が繰り返され、現在の定義はいじめ防止対策推進法第2条の「児童等に対して~(略)~当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と落ち着きました。
この改訂により、被害者が心や身体に苦しさや痛みを感じたら、「いじめ」と判断されるようになりました。
つまり、ふざけや遊び半分といった行為であっても、被害を受けた側の子どもがつらさや苦痛を感じれば、学校は「いじめである」と判断するようになったのです。これによりいじめの範囲は「いじめに関係のないもの」や「いじめと疑いのあるもの」までも含まれることになり、指導する領域は格段に広がることで教員の一段の多忙化へと繋がりました。
では、これで一件落着と思いきや、子どもの世界はそんなにあまくはありません。子どものなかにはいじめの定義を逆手にとって、気に入らないことがあると「つらい苦しい、いじめだ、いじめだ」と口にする強者も現れました。
明らかにおかしいと分かっていても、先生としては後々、保護者や管理職から何といわれるか知れたものではなく、動かざるを得ずに先生の仕事は際限なく拡大し続けます。