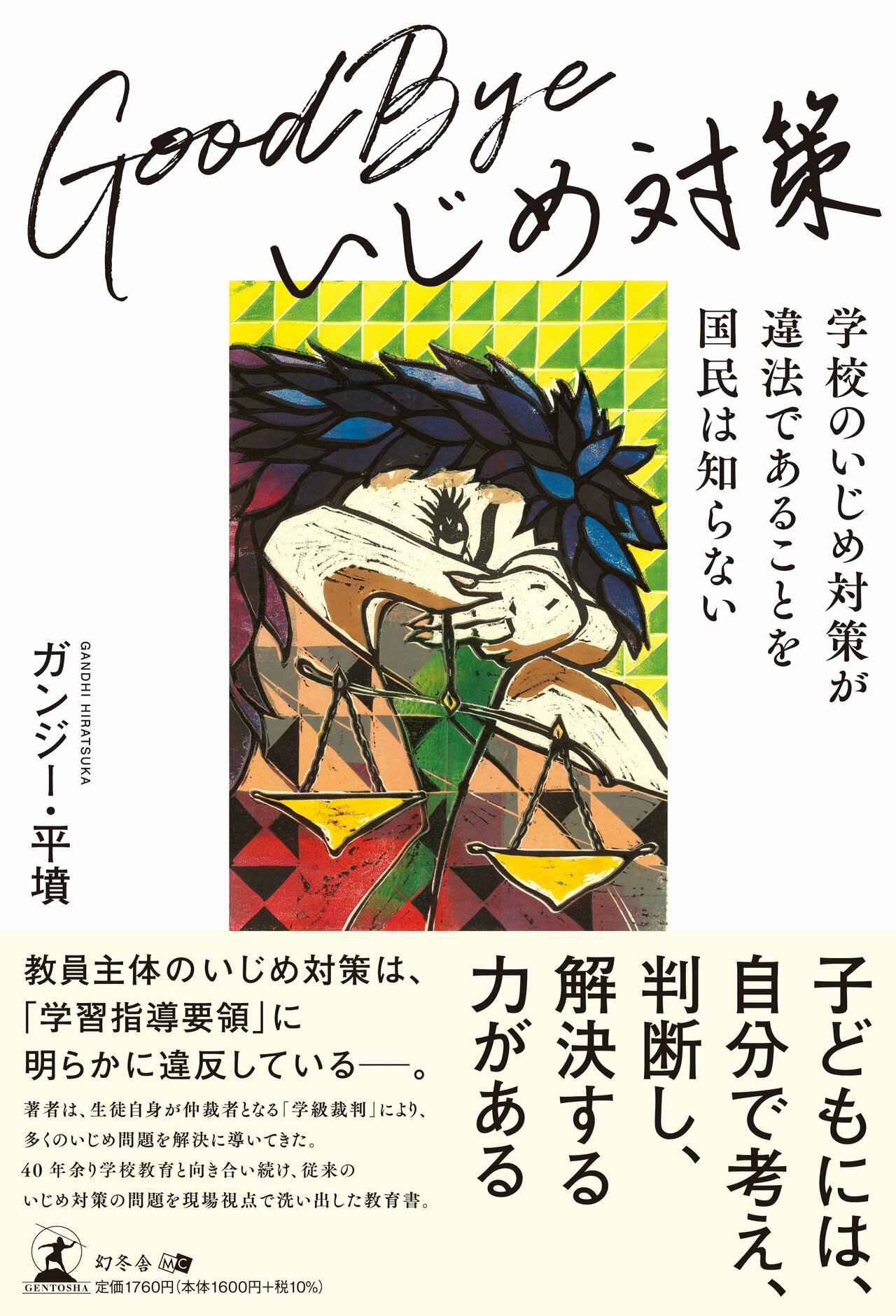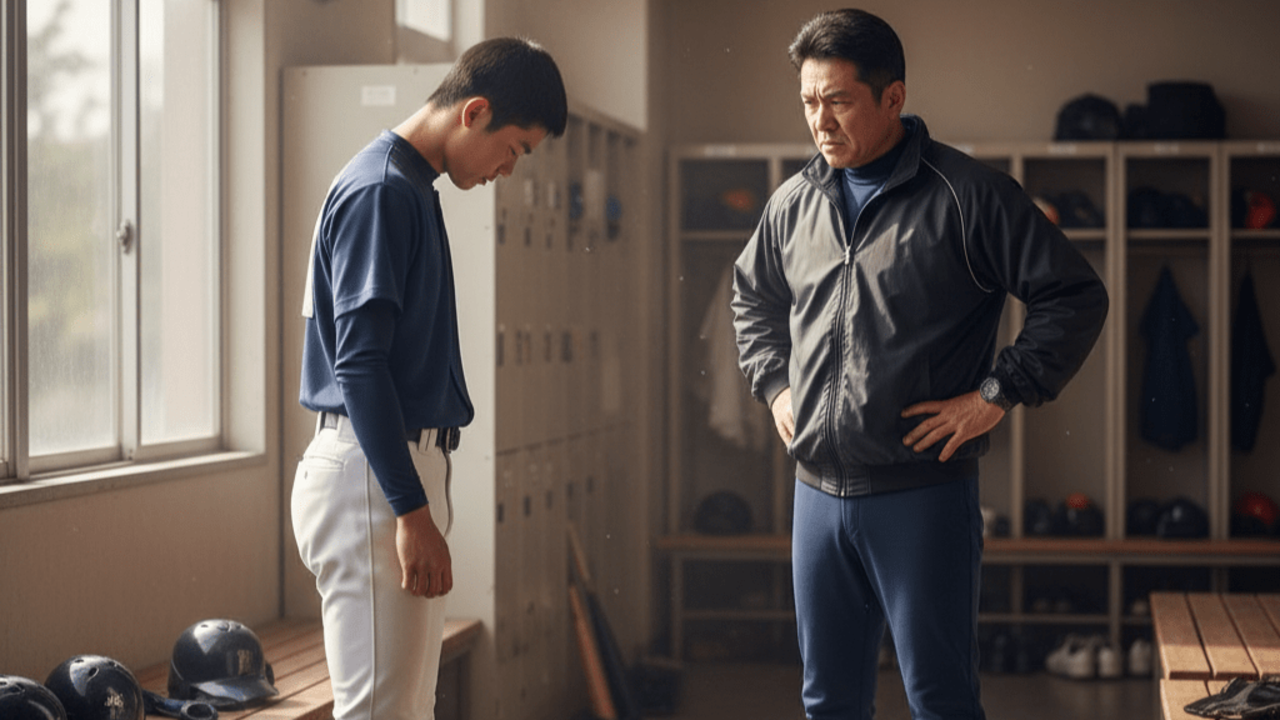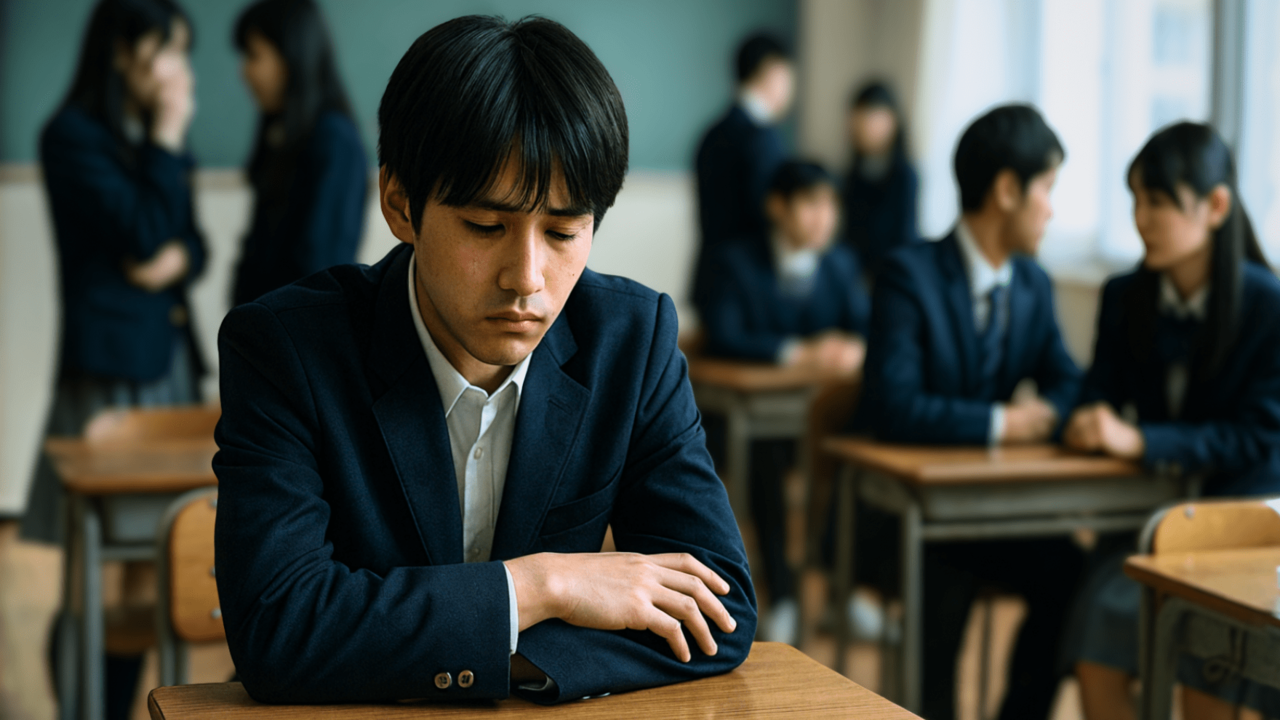【前回の記事を読む】いじめの実態を見落とす教師の思い込みが生んだ悲劇とは? 国の調査が明かす“見当違い”の危険性と教育現場の課題
第二章 国民を欺く違法ないじめ対策
―学校いじめ防止基本方針の欺瞞―
生徒排除のいじめの対応手順
【対応の大まかな順序】
⑤ いじめを受けた側の生徒のケア ◇必要に応じて、外部専門家の支援を得る
⑥ いじめた側の生徒への指導 ◇背景についても十分踏まえたうえで指導する
⑦ 被害・加害(双方)の保護者への報告と指導についての協力依頼◇いじめた側の生徒及び保護者への謝罪の指導を含む
⑧ 校長による、いじめた側、いじめを受けた側双方への指導
⑨ 関係機関との連携 ◇市教育委員会への一連の報告(指導後・1週間後・1ヶ月後・3ヶ月後)◇警察や子ども相談センター、スクールロイヤーとの連携
⑩ 3ヶ月間は校長やいじめ対策監が毎日声をかける等、経過の見守りと継続的な 支援(保護者と の連携)
以上、内容を分かりやすくまとめると「教員によるいじめの発見」➡「教員による聞き取り調査」➡「教員による被害者のケアと加害者の指導」➡「学校と警察などとの連携」となります。
ここには、「生徒による解決」や「生徒の参加」は表記されていません。まさに生徒排除の基本方針で、学習指導要領の趣旨から逸脱しています。