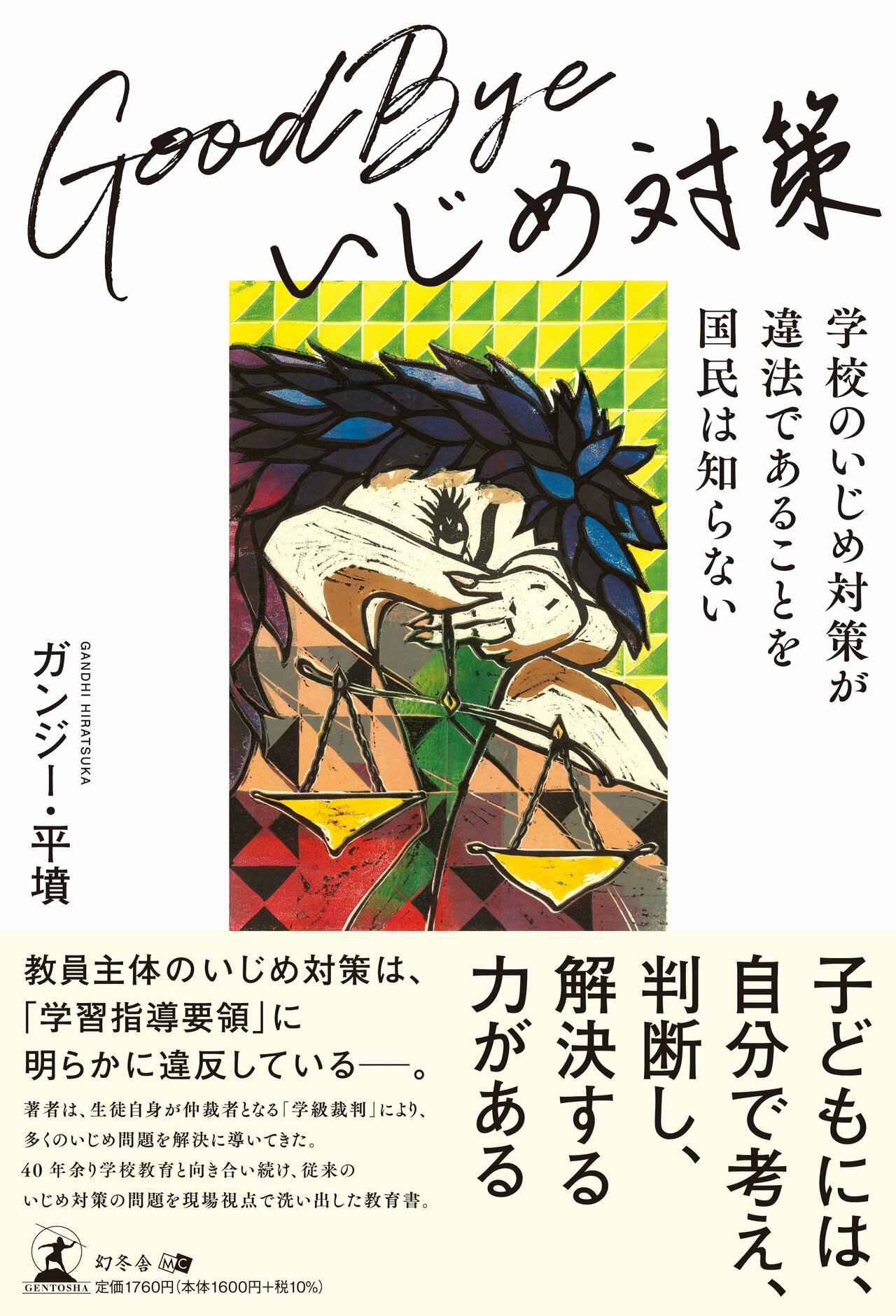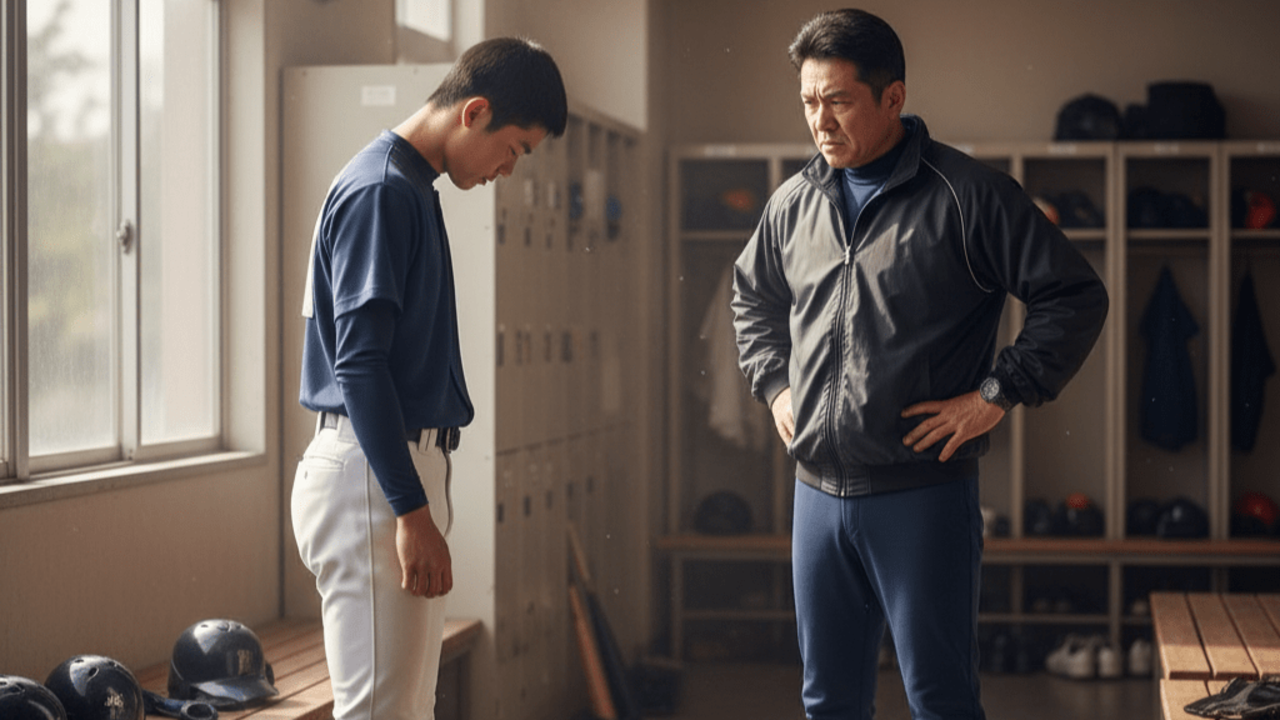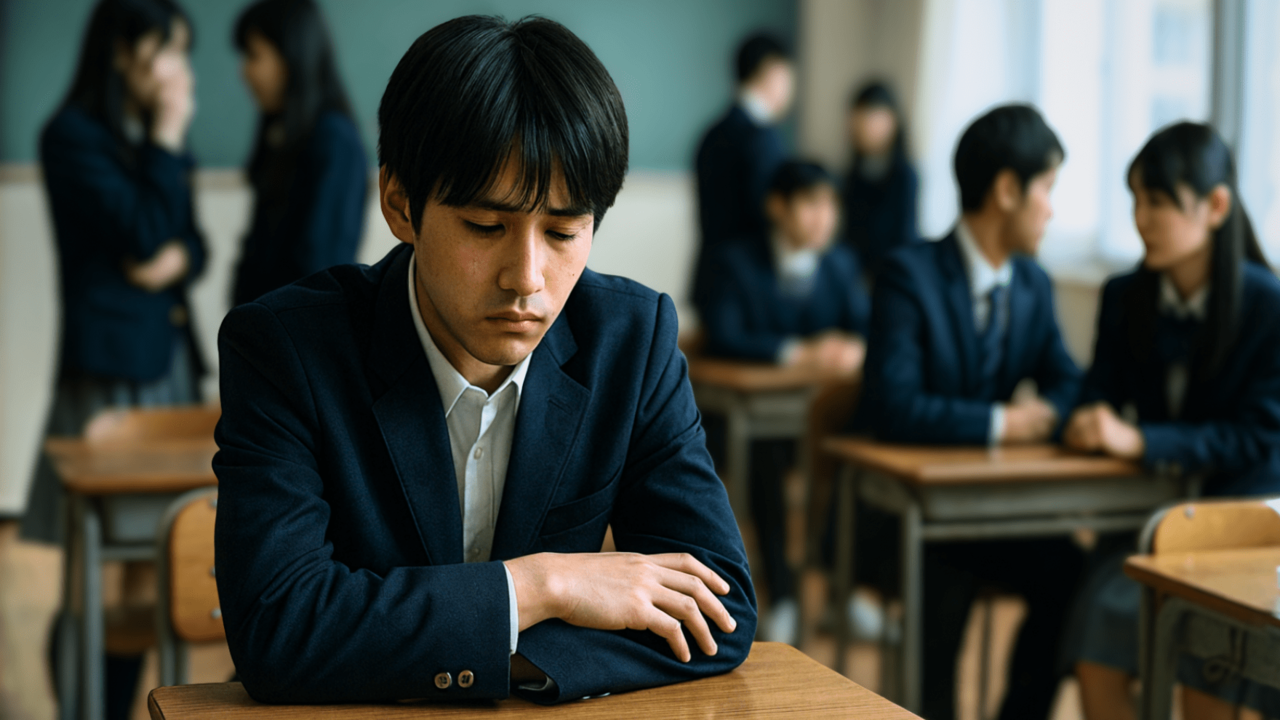生徒の役割は“チクリ魔”
学校いじめ防止基本方針には、「いじめ防止年間計画」に生徒の活動が記載されています。
2023年、大阪府泉南市で市内の中学1年生の男子生徒がいじめを苦に自殺しました。同市には「子どもにやさしいまち」の実現を目指す条例と子どもの権利条約委員会があり、この委員会は条例違反があれば、市長に報告できる独立した組織で、ほかの自治体と比較しても、子どもの権利実現に積極的な取り組みがうかがえます。
同市には4つの中学校がありますが、どの学校のいじめ防止基本方針にも大差はありません。
各校のいじめ防止年間計画には、生徒の活動として「職場体験学習」「体育大会」「文化祭」「修学旅行」「合唱コンクール」「人権学習週間」「ふれあい週間」などが計画されています。
これらはいじめ対策というよりは、集団活動の育成で焦点ぼけしています。生徒のいじめ対策としては、どの自治体でも「いじめ防止の標語やポスターの作成」「いじめ撲滅宣言」などに取り組んでいます。
「いじめ撲滅宣言」は、いじめ防止に向けてクラスなどで「わたしたちはいじめを許しません」とか「いじめを見て見ぬふりをしません」などと宣言する取り組みで、2013年の「全国生徒会サミット」では下村博文文科大臣(当時)が「いじめ撲滅」を宣言した学校に「感謝状」を贈呈しています。
しかし学校でいじめが発生すると、先生が「自分たちで決めたいじめ撲滅宣言がなぜ守れないのか」と子どもを叱責し、双方の関係が損なわれるケースが起きています。
また、北海道のある中学校のいじめ防止基本方針には、「『傍観者』から『仲裁者・制止者』になるのが難しくても、『通報者』になることでいじめの深刻化を防ぐことができる」と生徒の役割を定めた学校もあります。
いじめを先生に通報した生徒が、クラス員から“チクリ魔”といわれ仲間外れになった例は数多く報告されていますが、これでは第2、第3のいじめ被害者を生みかねません。
【イチオシ記事】帰ろうとすると「ダメだ。もう僕の物だ」――キスで唇をふさがれ終電にも間に合わずそのまま…
【注目記事】壊滅的な被害が予想される東京直下型地震。関東大震災以降100年近く、都内では震度6弱以上の地震は発生していないが...