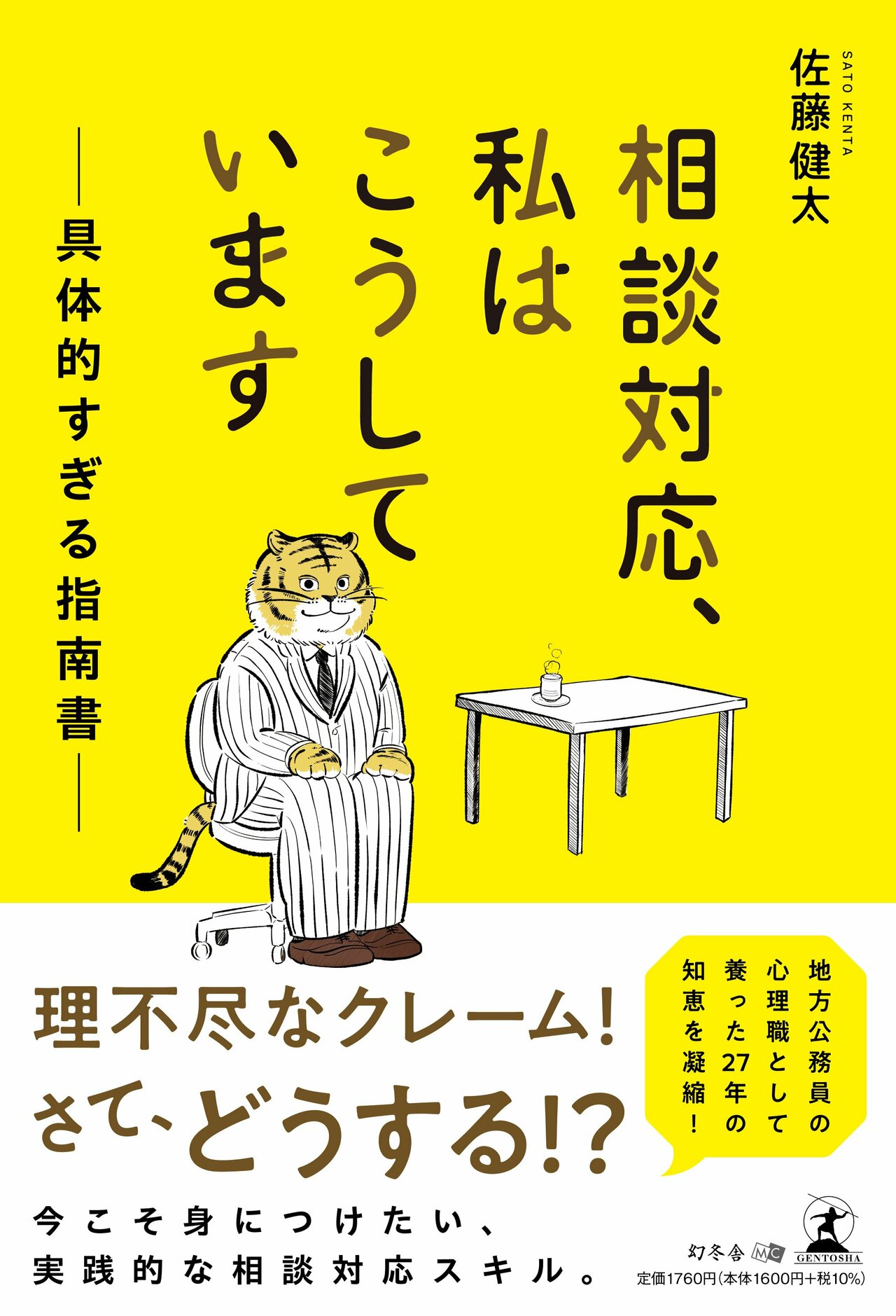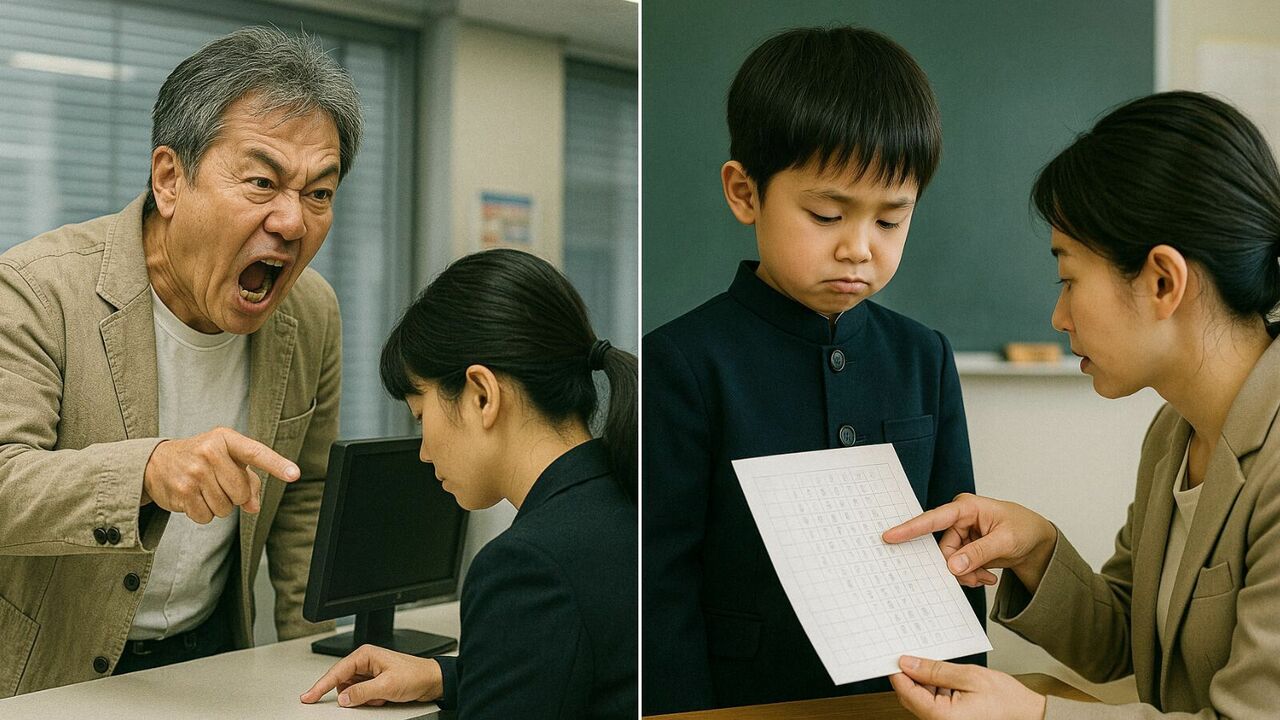事例6の対応方法 さて、どうする?
・相手の中に答えを見つける
その人の中に答えがあることに気づいてもらうように話をつないでいくと、価値観の押し付けにはならないはずです。このように対応できることが、「相談」という場面において「寄り添う」ことになるのではないでしょうか。
私は、その避けられている状況について、「もう少し詳しく教えてもらっていいですか」と相談者の発話を促し、どうなると私と話ができて良かったと思ってもらえるのかを探りました。
結果的には、避けられているとしても、数少ない話せる仲間としてつなぎ留めたいという気持ちがある、ということを共有できました。困っていることを解決できたわけではありませんが、「わかってもらえただけでも話した甲斐があった」とおっしゃっていました。
事例6のまとめ
[結果]
・「わかってもらっただけでも話した甲斐があった」と言ってくれた。
[ポイント]
・ 相談内容の表面だけをすくうのではなく、どんな話ができると、相談して良かったと思ってもらえるのかを探ることが大切。
・対応者の過去の経験からのアドバイスが正解とは限らない。
【事例7】
相談内容:「中学生の子どものことで相談したい」という母親からの相談。
相談者:40代女性
対応者:著者
対応場面:対面での相談対応
※著者は、この時児童相談所に在籍
相談者が、「ある相談機関に、子どものことで相談したい」と問い合わせたが、本人を連れて来ないと相談にならないと言われた。本人は不登校とひきこもりであるため、外に連れ出すことは困難。