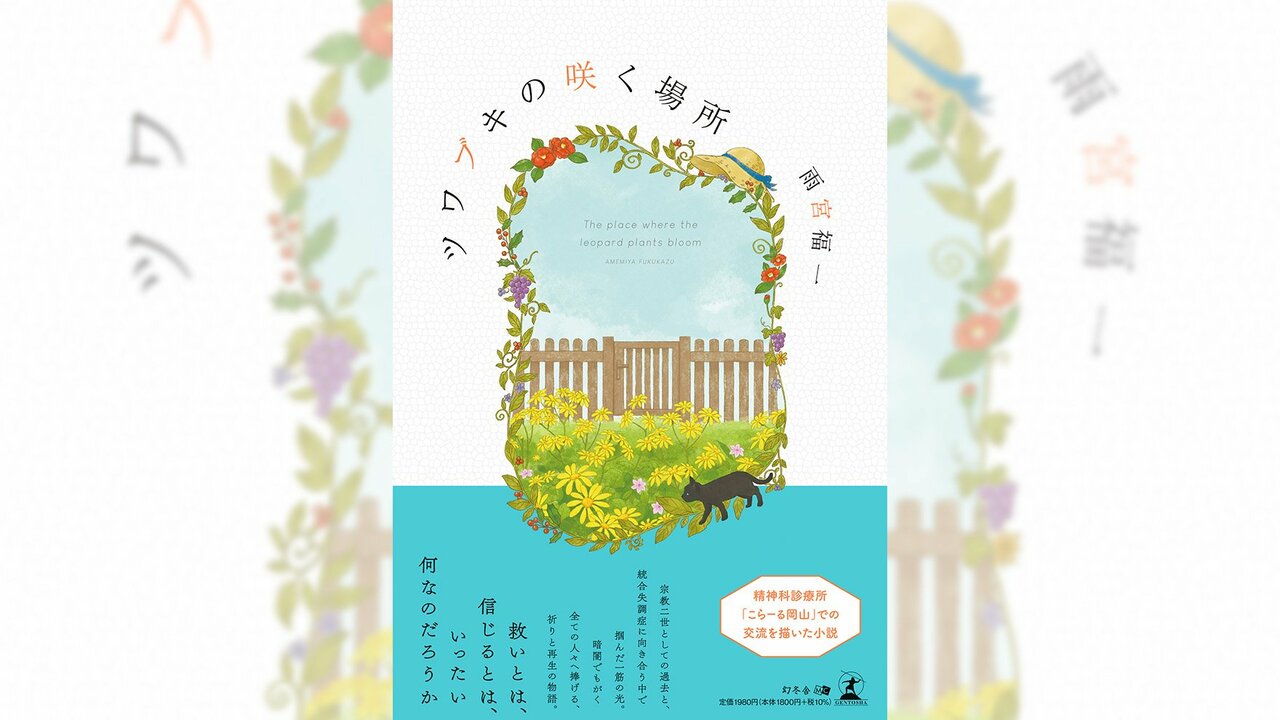【前回の記事を読む】いつか中を見てくれ…心不全で亡くなった親友が残した段ボール箱。そっと開けると、そこには聖書が入っていて…
第一章 靴
【 三】
腕を引っ張り、起き上がるよう促される感触を覚え、私は驚いて目を見張った。
腕をつかんでいたのは永ちゃんであった。玄関から吹き付けた風にあおられて、はっとして我に返る。手持ちにしている聖書に、永ちゃんが目を留めた気がした。
「全く! ちゃんと眠ったか気になって来てみたら、玄関の戸を締めてすらないじゃないの」
むろん、永ちゃんがそう言ったということは聞き取れる。しかし肝心の言葉の意味が理解できないでいる。ただもうひたすらに眠気がさして、脳がカステラへでも変化したみたいだ。
「あっ、あれぇ? お、おはよう」
正体なく返事すれば、さっきより強く、永ちゃんが私の腕を引く。
「よし! ちょっと付き合ってくれ」
何か決意した様子で、永ちゃんが私を外に連れ出す。あれよあれよという間に、車へ乗せられてしまう。
あまりに眠くて、返事もろくにできない。永ちゃんの運転する車の中には、本人が吸う煙草の香りが立ち込めていた。点けっ放しにしたラジオからは、明るい朝の挨拶が聞こえてくる。よく通る美しい声をした女性パーソナリティが、今日の天気予報を歯切れよくアナウンスしてゆく。
「以上。岡山市の本日のお天気でした。間もなく午前六時となります」
そうか。早朝ともなれば、見覚えのあるはずの街の薄明るい風景も、こんなに静かだったのか。
(そうだ。昨日、あのまま眠ってしまったんだ)
菅野さんのことを想ううち、ラファに頭をなでられていつの間にか眠っていた。意外と疲れていたのだと思う。
車窓から見える風景には一面朝靄が広がっている。そわそわして仕方ない気持ちを紛らわすため、早朝の街を一度か二度、散歩したことがある。
でも、永ちゃんの車で通り抜けてみれば、朝の街の印象はその時とはまるで違っていた。清く静かで、澄んだ空気に包まれて存在しているように見える。
ラジオの音は穏やかな響きのする音楽に変わり、永ちゃんがどこを目指して走っているのか、知ろうとする気力が起きてきた。
どのくらいの間、走ったのだろう。普段車に乗らないから時間経過が分からない。
見慣れた店がいくつかあるので気が付いた。
(これ、こらーる岡山診療所へ行くときに通る道じゃないか)ひょっとしたら、私の様子を見て山本先生の所へ連れて行こうと思ってくれたのだろうか。永ちゃんのことだ、それはあり得る。
そんなことを考えるうち、永ちゃんの車は駐車場に駐まった。
「着いたぞ、涼。降りられるか?」
永ちゃんに言われ、まだ眠気の残る頭で頷く。車を降りる。そこはまるで知らない場所だと気が付いた。