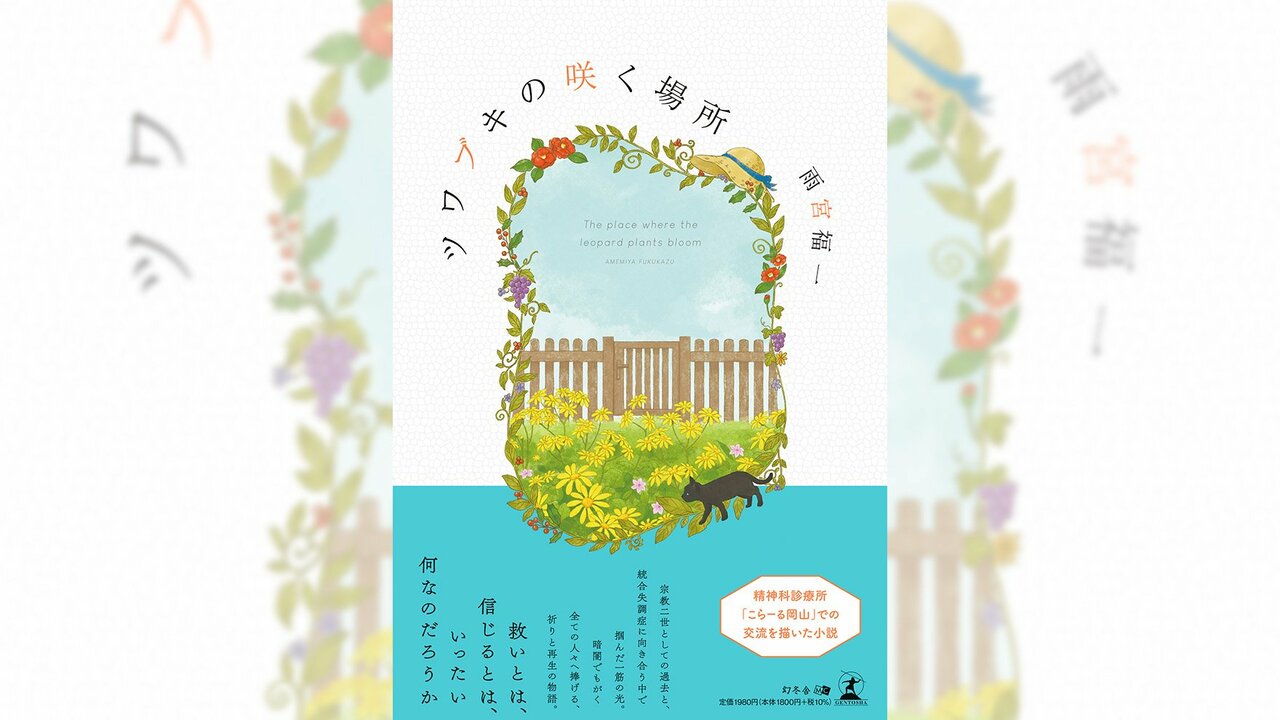【前回の記事を読む】ハムスターに嫉妬し、小さな命をそのまま土に埋めた。その後、主治医から家族と離れて暮らすことを提案され...
第一章 靴
【 二 】
手元のスープが冷めていくのが分かっていても、彼の思い出はとまらない。一緒に行ったクリスマスパーティー、蛍を観に行った日のこと、夏祭りのにぎわい、正月参りの人混み、夜更けの何でもないメールに、どうでもいいことで盛り上がる昼餉(ひるげ)の語らい。
でも。
(一度に思い出しすぎた気がする。そう。亡くなってからというもの、菅野さんのことはできるだけ思い出さないようにしてきたし)
ふと、私は先生にもらった教会の案内がカバンから落ちて床に投げ出されていることに気が付いた。案内を拾い上げようとして、束ねられたままの状態で積み重なった段ボールの山に目を留める。
(あっ!)
頭の中で思い出がはじける。そうだ。
あれはたしか……スープが残った椀をテーブルに置き、壁際にある大きな備付けの木製のタンスのところへ行ってみる。
かつてこの家に居住した人たちは、このタンスに着物をしまい込んでいたのだろう。私一人では半分も使い切らないようなサイズのタンス。その一番上の引出しを開けた。
普段は人目につかないようにしてある段ボール箱を取り出す。埃が立ち、日差しを受けてきらきらと舞う。
菅野さんがこの家に来た時、「いつか中を見てくれ」と言い残して置いていった段ボール箱。一度は開けてみたけれど、中身をあまり深く考えたくなかった。だけど、菅野さんが置いていったその箱を、私はどうしても捨てられずにいた。箱をそっと開ける。
「……聖書」
ふるくからの友。懐かしさに、胸が一杯になる。
これは、菅野さんの私へのメッセージだったのだろうか。彼が「いつか」と言い残したのは、もしかしたらこの時のためだったのかもしれない。
「わぁ、埃まみれの本ね」
「ら、ラファ!」
唐突に声を掛けられて、すこし驚いた。ラファは頬杖をつきながら、私の横にしゃがみ込み、聖書を見つめていた。「こんな本をどうしてくれたのかしら。あなたにもいつか、聖書を読んでもらいたかったのかしら」
「分からない」
「そうよね。もう死んでしまったんだもの」
「うん。菅野さんにじかに聞いてみたいものだな」
「もっと早くに取り出しておけばよかった、そう思っているのね。大丈夫。きっと今日が、この本を取り出すべき日だったのよ」