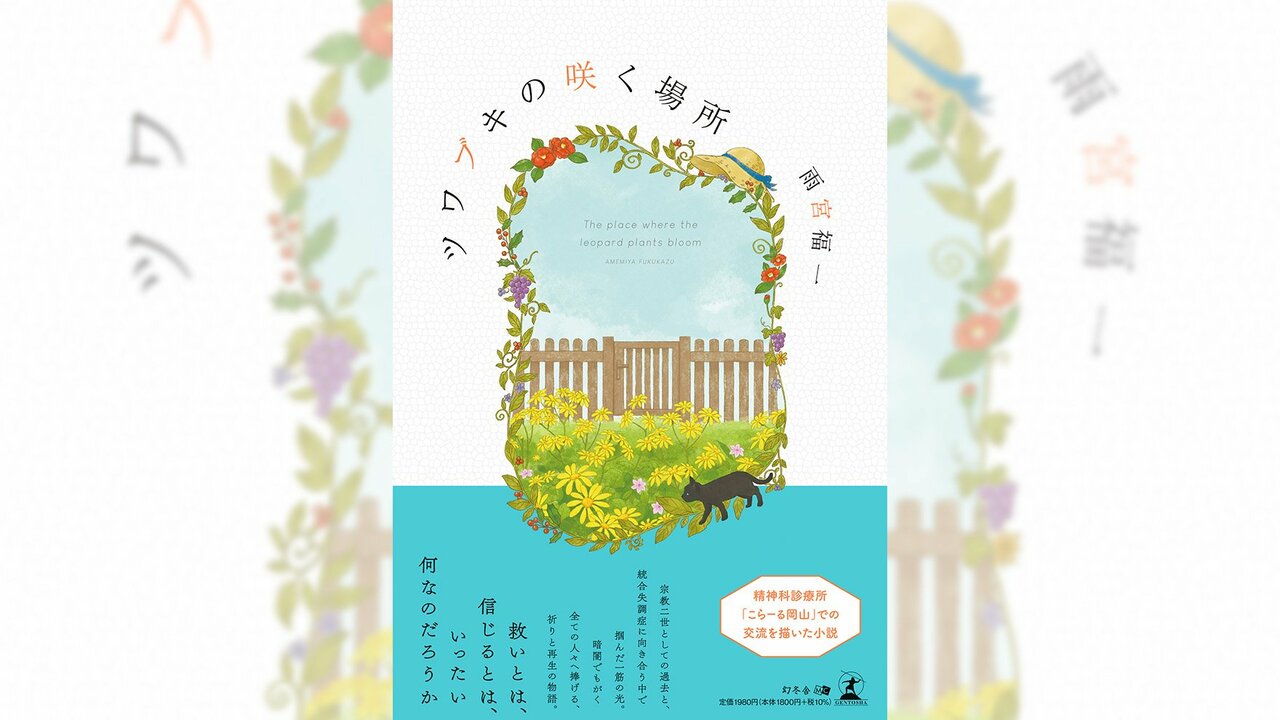【前回の記事を読む】ペットのハムスターを庭に生き埋めにした。手のひらに、脈打つ小さな心臓。皆が私の方を見た。私を、見てくれたのだと思った。
第一章 靴
【 二 】
「君がこのまま家族とかかわり続けることは、互いにとってけっして良いことではないと思う。どうだろう。家族と離れて暮らさないか? 岡山であれば、私も協力できるから」
まさに入院の一歩手前。そう告げた主治医のおかげで、家族から距離を置くという選択肢があることを、私は初めて知った。主治医がその時、その選択肢を示していなかったとしたら、私は今も病院に入院したままだったろう。
ずっと冷たいままだった指先へ、ほのかなぬくもりが感じ取られた。
私はあの日のことを思い出しながら、新しい便せんを取り出す。そして一文字、また一文字と文を綴っていく。
「親愛なる妹へ。私は、家族と一緒に暮らせなくなるような、自分の力だけではどうにも変えられない経験をいくつもして生きてきました」
無事生きていたペットのハムスターの記憶を、妹はあの時のまま、心にしまい込んでいるだろうか。
ぐつぐつと、鍋の煮える音がする。
「あっ……っと。煮えすぎ、煮えすぎ!」
慌てて火を止め、鍋を下ろす。おたまでスープをすくって味を見れば、塩がすこし足りない。塩を足してから、出来上がったスープを椀に注ぐ。
簡単な野菜スープは、私の料理の定番なのだ。安く済むし、飲めば小腹が満たされる。
スプーン片手に椅子へ腰掛けたら、私の目の前に頬杖をついたラファの姿が浮かび上がった。
唇を尖らせておちょぼ口を作り、気取ったような様子で言う。
「そんなにつらい出来事を思い返すくらいなら、今の幸せに浸っていてもいいと思うなぁ」私はこの言葉を聞いて、どう答えていいか分からないでいる。
ラファが言いたいことも分かるような気がするけれど、だからといって妹のことをこのままにしていいのだとは思わない。
私が押し黙っていることをつまらなく思ったか、ラファはかまどの方に歩み寄る。そ
して、かまどの蓋を取ると、煤まみれになりながら、すぽんと中に入ってしまった。ああなったら、しばらくは出てこない。
(すねてしまったかな)と、その時である。