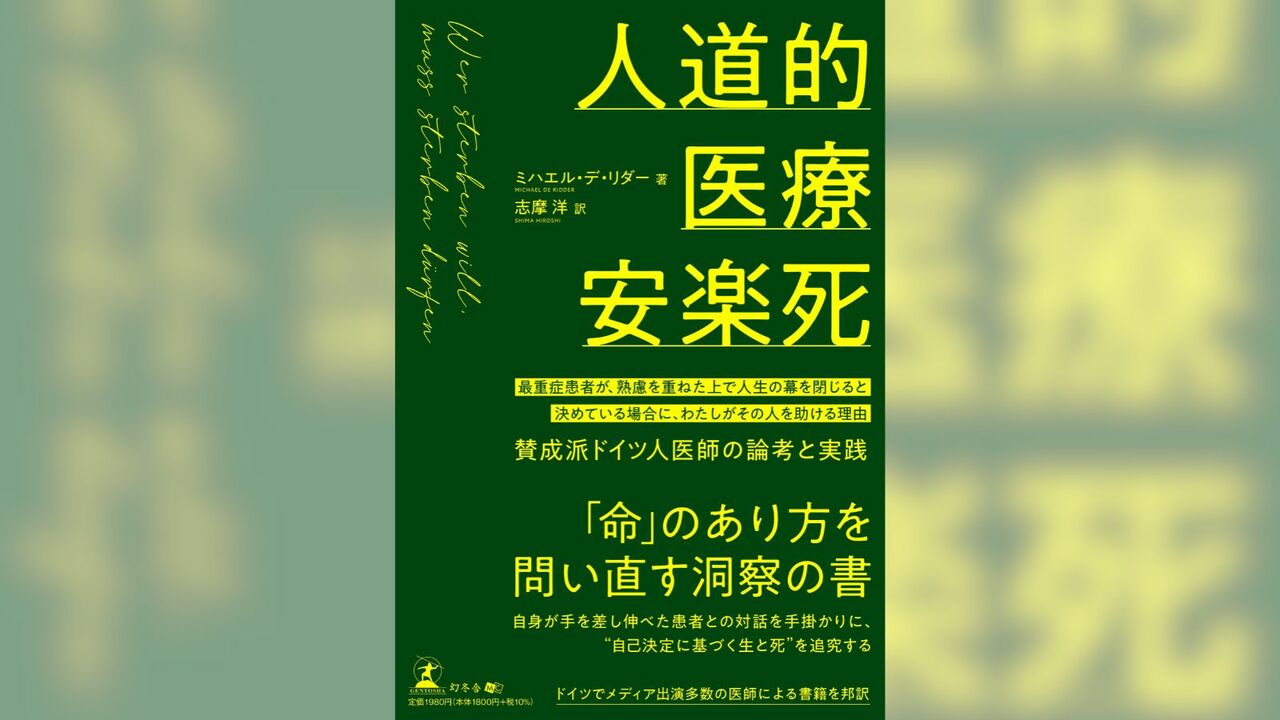【前回の記事を読む】【人道的安楽死】賛成派医師の論考――フロイトとカフカの病気と死から考える。二人の共通点は「耐え難い苦しみを終わらせてほしい」
第1章 序章:ジグムント・フロイトとフランツ・カフカ
―その病気と苦悩と死
カフカの病気に対する認識とその対処法は異常であった。そして、病気の深刻さと脅威は、徐々に本来の姿を示し始めたのである。当初、カフカは専門家による治療よりも姉の説明に関心を寄せていた。
カフカは、姉の説明に意味を見出して、そこから何らかの前触れを読み取ろうとしており、さらに、自分の病気を過度に道徳的な次元で捉えていた。
姉のオットラは、結核のことを、霊的な病気とか最終的敗北と名付けて話していた。また、ブロートとの会話では、婚約者フェリーチェ・バウアー(1917年に別居)に対する罪の意識から来る罰に違いないとも述べている。
カフカは文学者仲間の友人フェリックス・ウェルチへの手紙のなかで、自分の病気は授かった病であると語っており、自分は病気によって躾けられているとも書いている注1。
1918年の秋、カフカの結核性肺尖部(けっかくせいはいせんぶ)カタルは、かなり落ち着いていたが、その一方で、スペイン風邪が大流行しており、当時は全世界で2千万人以上の犠牲者が出ていた。
その後、カフカの病状は、喀血や高熱を伴う重い肺炎へと悪化して、数週間ベッドで寝たきりとなり、家族に看病されながら過ごすことになった。有効な薬はなかった。
カフカの病状は、一進一退を示していたが、実際には、新たに進行した肺結核は、誰が見ても回復することがないほどの打撃を与えていたのである。
1920年12月、カフカは、ハイ・タトラ山脈の温泉地マトリアリーにある結核療養所を訪れていた。カフカは、そこで、自分と同じユダヤ人で医師を志している年下のローベルト・クロプシュトック(衛生兵)と出会った。
彼も、カフカと同様に肺結核を患っていた。二人は、互いに惹かれ合い親密で信頼し合える友情を育んでいった。姉のオットラしか知らなかったような方法で、クロプシュトックはカフカを気遣った。
文学への片思いと未練に悩むクロプシュトックは、カフカから父親のような助言と励ましを受けていた。クロプシュトックは、その後、友情を超えてカフカの主治医となり、死ぬまで主治医であり続けた。
カフカは、死の数週間前に両親に向けて「クロプシュトック君の傍にいれば、まるで天使の腕のなかにいて救われているように感じている」注2 と書き送っている。