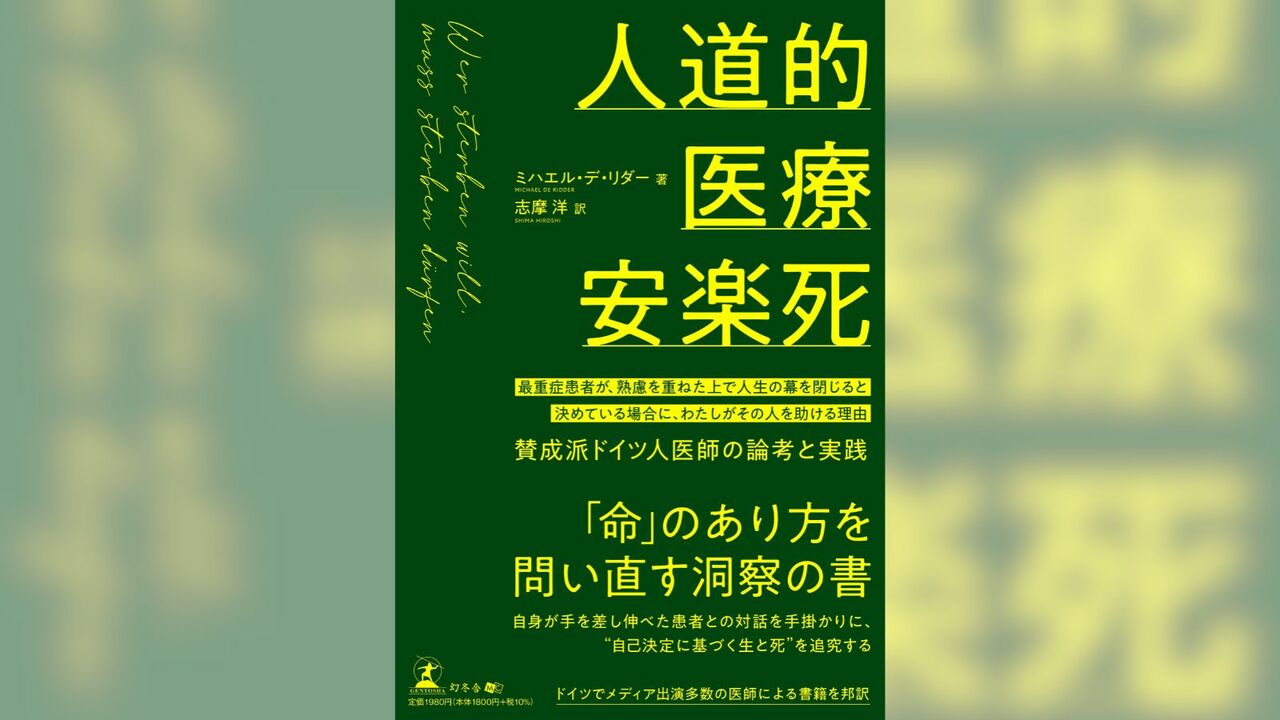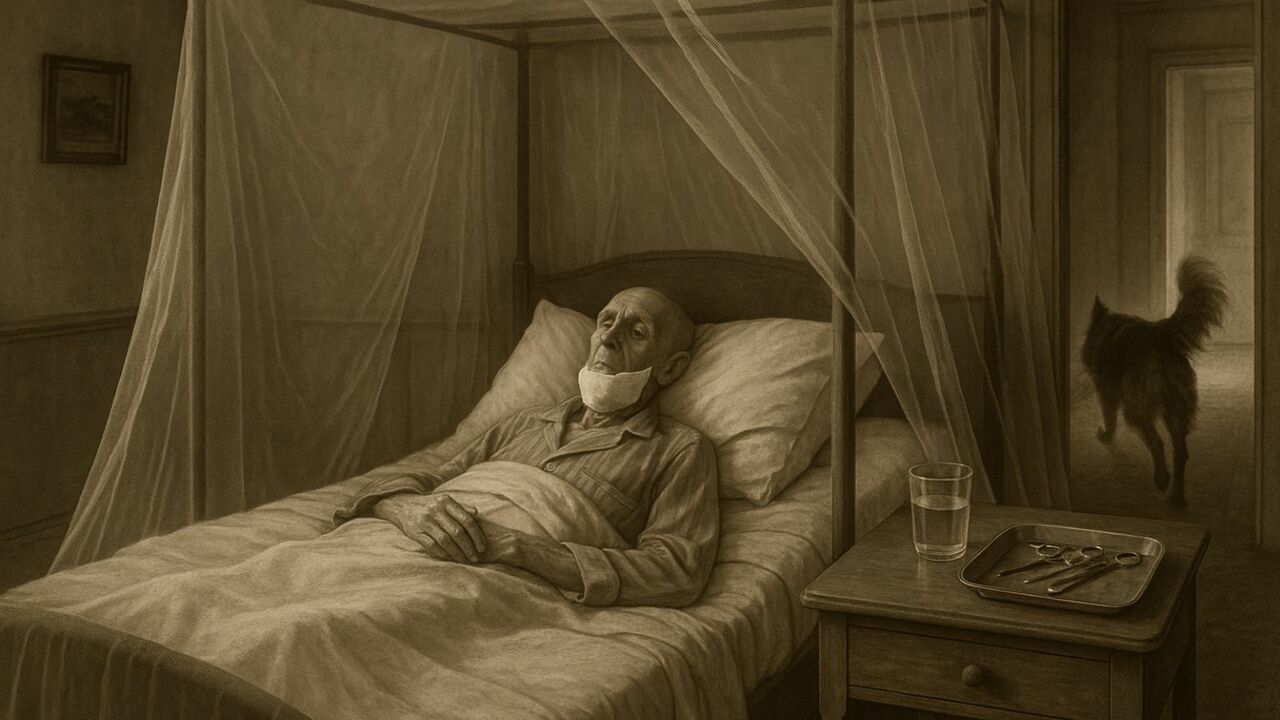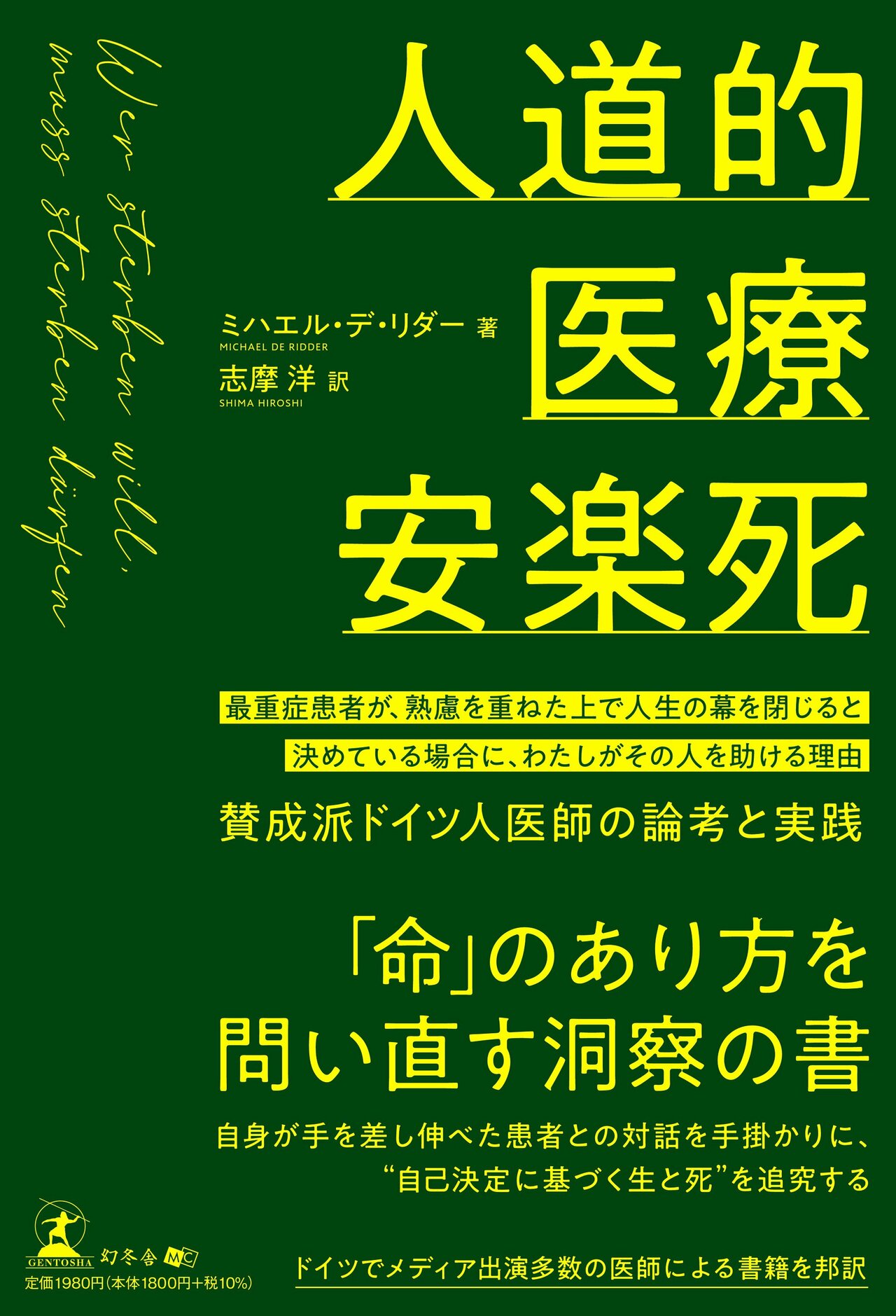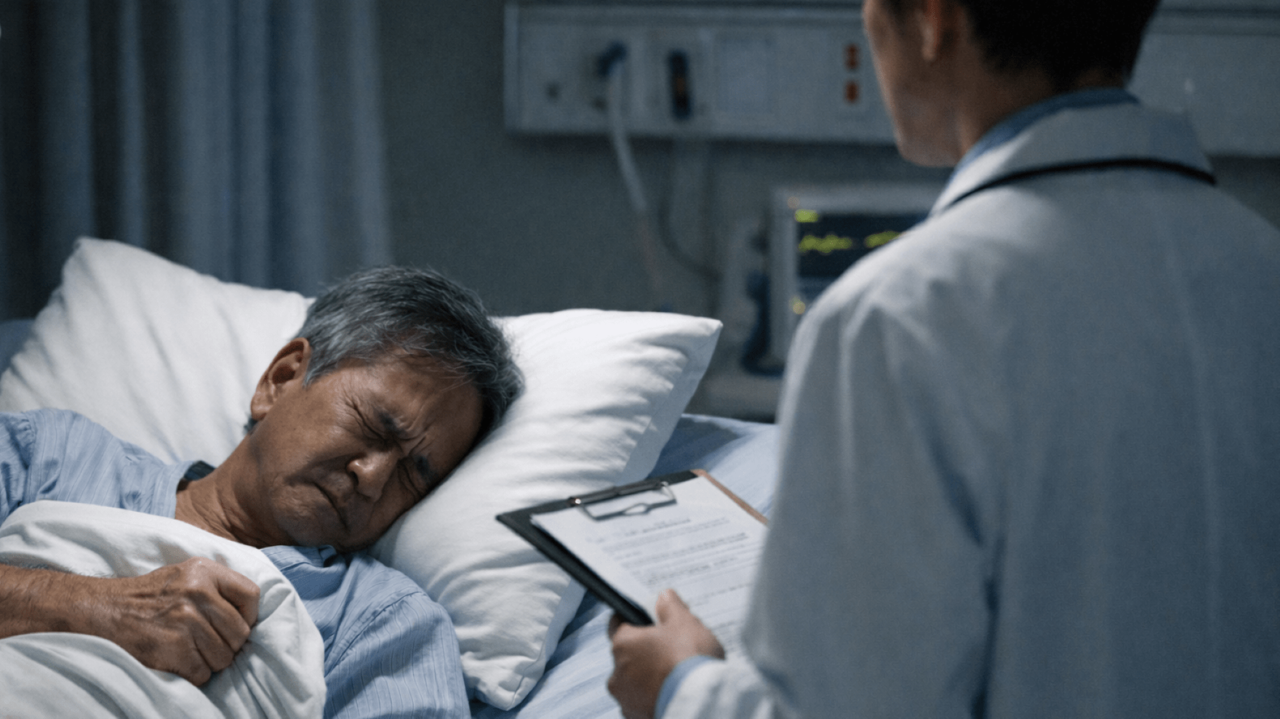【前回の記事を読む】カフカは、看護師を無愛想に部屋から追い出し、体にはりついていた管を激しく引き抜いた「もうこれ以上苦しむのはごめんだ!」
第1章 序章:ジグムント・フロイトとフランツ・カフカ
―その病気と苦悩と死
1939年に亡くなるまでの数年間は、フロイトの人生にとっては、圧迫感と苦悩に満ちたオデュッセイア(訳者注:オデュッセイアは、ギリシャの詩人ホメロスの英雄的叙事詩。主人公オデュッセウスのギリシャ軍のトロイ攻略後の波乱に満ちた帰国物語、24巻)のようであった。1923年から1939年までの16年間に、フロイトは、33回の手術を耐え忍んでそれらを克服していた。
そのうちのいくつかは局所麻酔で行われ、さらに、ラジウムの挿入、エックス線照射、電気的外科処置が施されており、その結果として、骨に欠陥が生じたために、何度も痛みを伴う補綴(ほてつ)物の調整が必要であった。口腔域と鼻腔域を隔てる補綴物を入れることで、何とか会話や嚥下に耐えられるようになっていたのである。
これらの手術は、最終的には、すべて右側聾(ろう)につながる可能性があったので、ウィーンの経験豊かな口腔外科医ピヒラー教授が、その治療に当たった。ピヒラー教授は、カフカの治療も行ったことがあり、フロイトは、彼に大きな信頼を置いていた。エルンスト・ジョーンズの報告によれば、ピヒラー教授は、ほとんど常に手の届くところにいてくれたそうである注1。
フロイトの著作や書簡が示しているように、彼自身の病気に対する態度は、前向きと後ろ向きの二つの顔を持つ双面神ヤヌス顔負けであった。
一方では、それを直視する勇気があり、感傷的でなく、科学的医学を信頼しており、他方では、有機的なもの、すべての有限性とその崩壊と死が、フロイトの愛する古い「がん」という言葉のなかに、冷静に浮かび上がることを許す運命論に身を委ねていたのである注2。
初期のフロイトの論文や手紙には、自分が人生の終わりになって創造的な力を失うことになるのであれば、もはや苦しむことを望まないという言葉や、同様のヒントが数多く見られる。1885年、フロイトは妻のマーサに対して「人間は、生きていることだけを願っているのならとても惨めだ!」注3 と記している。