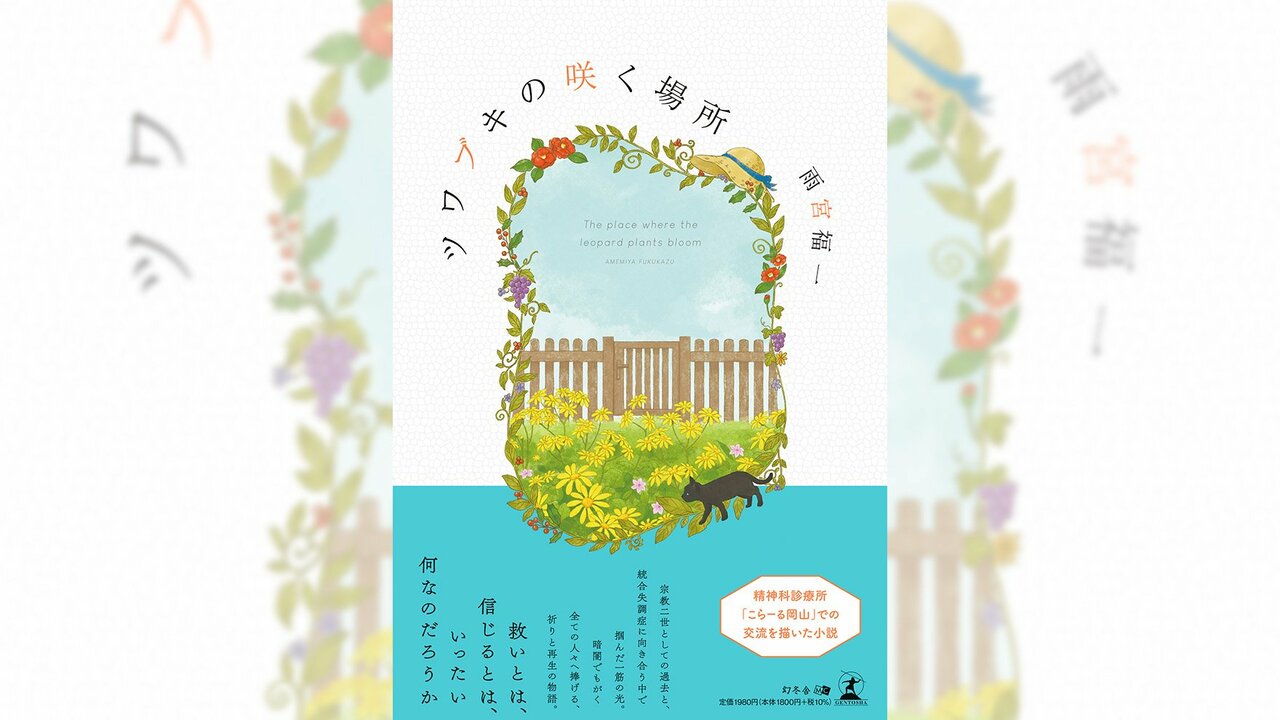【前回の記事を読む】「遊びに、行くのですか?」教会へ行くのって、そんなものなのか。キリスト教から想起するのは、かつて関わったカルト教団。
第一章 靴
【 二 】
古い民家の建付けは、けっして良いものではない。がたがたと音をさせながら玄関の戸を引き、家の中に入る。急に、ひどい空腹を覚えた。
「あ、そうか……」
起き抜けに急いで家を出たので、昨日の昼に永ちゃんと食事してからというもの、何も食べていない。
水を入れた小鍋を火にかけ、残っていた野菜を一口大に刻んで煮る。野菜スープを作るのだ。古いかまどを使うこともまれにあるが、今の腹具合である。
薪を一からくべるのは待てそうにもない。コンソメキューブを投入し、冷蔵庫にあった茸を混ぜ合わせる。コトコトという音がし出せば、待合室で声を掛けてくれた女性の声が頭の中をよぎる。
「……お寺や神社のように、気軽に行ける場所か」
そんな風に言われてみれば、そうなのかな、とも思われるが、気持ちに整理がつくかというと、それはまた別の問題だ。
家族と行けるくらい安心できる所、という意見にも、まるで納得がいかなかった。
「……家族と、安心」
私は、ある日のことをふっと思い出した。
それは、私と母親に、決定的なすれ違いが生じた日。
その事件の引き金は、私が八歳になり、日本での生活にどうにかなじもうとしていた矢先に起きた「いじめ」であった。
東京近郊の小学校へ通うようになって、初めは学区外から通学する私を物珍しそうに見ていた同級生も、声を掛けてくれるようになっていた。
「え、生まれた所?」
ありふれた午後のひと時。何でもなかったはずの休み時間。転校生の私を気遣うように、質問が飛んで来た。「うん。俺、育ったのはこの辺りだけど、生まれは東京。夏春は?」
同じクラスにいた、浅田という少年。彼の声は、いつでもどこか、得意げに聞こえる。
東京生まれ、ということが、誇らしい様子だ。生まれた所が都会だということが、自慢のもとであるらしい。
「ぼ、僕は、韓国だよ。実は外国生まれなんだ」
級友の質問にやや戸惑いながら、私は彼に自分の出自を伝えた。気恥ずかしいから笑みを浮かべて、皺の寄ったシャツにズボンの恰好で。
その瞬間。
「こいつ、韓国人なんだって」
冷たい声音が、休み時間の教室に響いた。小学二年生の私は呆気に取られて彼の方を見る。