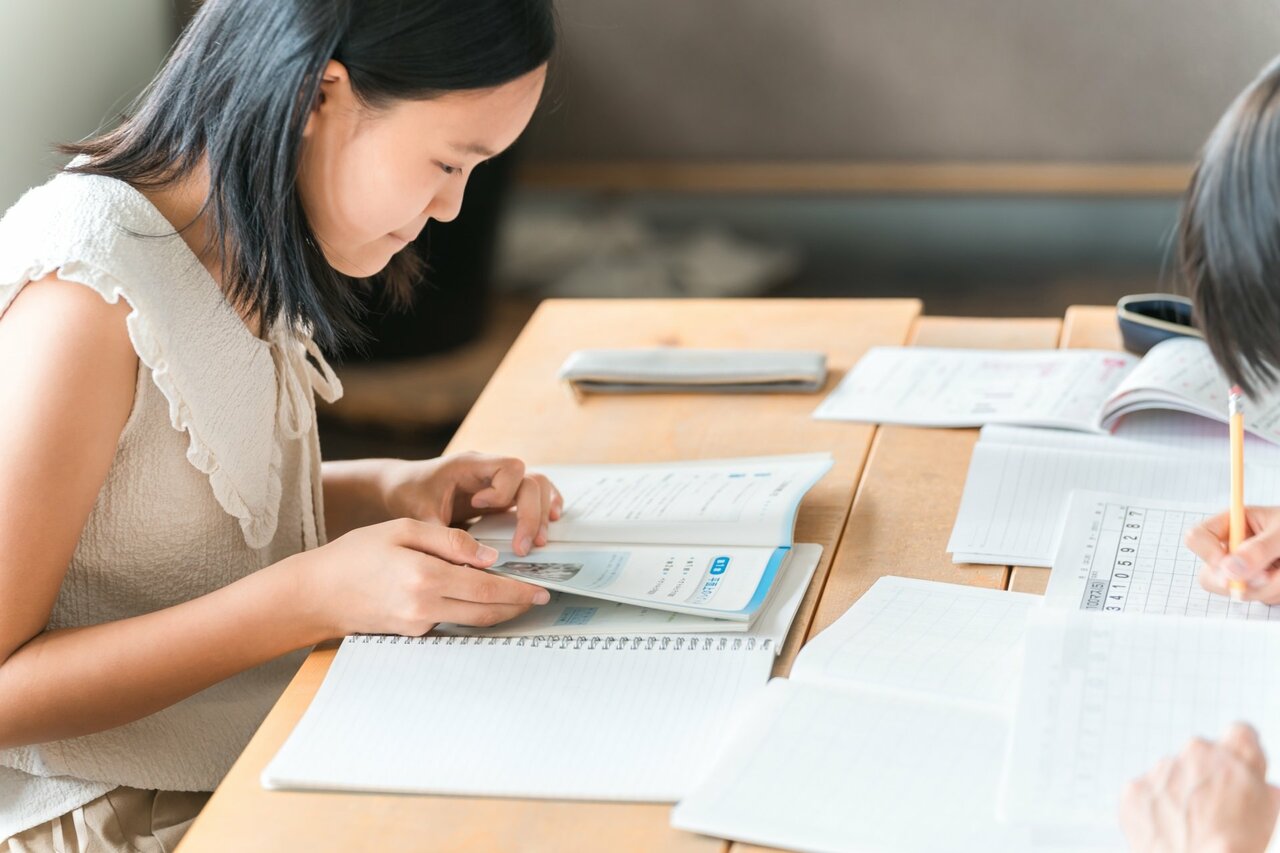④ なぜ、こういう取り組みでスタートしたのか
私がこの学級で考えてもらいたかったことは、
•素直と従順は違うのだ。既成の考えに従順であるのがよいのではなく、せめて「待てよ?」と自分の気持ちに素直になりそれが言える子になって欲しい。そういう子を育てたいということ
•それに伴って"本当にそれでいいのか"という場面が出てくるので、その場合も少数意見を大事にする民主的な子どもになって欲しいこと
•そういう仲間作りをしていきたいこと
であり、それを強く主張し実践したのです。
このスタートにあたり、子どもたちと共通の土俵の上で考え合えたことが良かったと思います。子どもは変わりたがっているんだと実感しました。もちろん、人に迷惑をかけるよりかけない方がいいでしょう。しかし『言葉は哲学』です。
そこにどんなメッセージが込められており、それに対して実感を持って共有できるかどうかは教育の根幹です。そういう意味では子どもたちが共感して「そうしよう」と言うようになっていったので、ひとまず安心して学級での生活をスタートすることができました。
学校生活は、学級を中心とする集団での学びが大半です。教師はその中心にいます。それだけにどのような学級にするかは重要になります。しかし学級は閉鎖的な集団です。したがって教師に任されることが多いので力量が試されるのですが、教師には自由度が高いのでやり甲斐があります。
column 自分の子ども時代を反面教師に
私は小学校2年の3学期から中学2年の3学期までの丸6年間、人前で話のできない子でした。友だちや家族と喋る時は何でもないのですが、順番が来て一人だけで話すようなちょっとした場面でも話ができないという毎日でした。
きっかけは学芸会の劇でやった、5つのセリフがあるフクロウのお巡りさんの役でした。張り切って上手に演じようとしたのですが、そこで失敗してしまったのです。
落ち込みました。その後、それがトラウマになって授業でも失敗するのではないかと思うようになり、手を挙げて発表することもできなくなりました。
初めのうちは指名してくれていた先生も指してくれることがなくなりました。そういう生活が続くうちに、人前で話せないことにだんだん平気になってきました。
「どうせオレはしゃべれないのだから」と、やらないことが当たり前になり何とも思わなくなったのです。
しかし今になって考えると、ずっとつらかったことには変わりなかったのに、それを逃れるために平気なふりをして自分の心を安定させていたのではないかと思っています。
【イチオシ記事】朝起きると、背中の激痛と大量の汗。循環器科、消化器内科で検査を受けても病名が確定しない... 一体この病気とは...