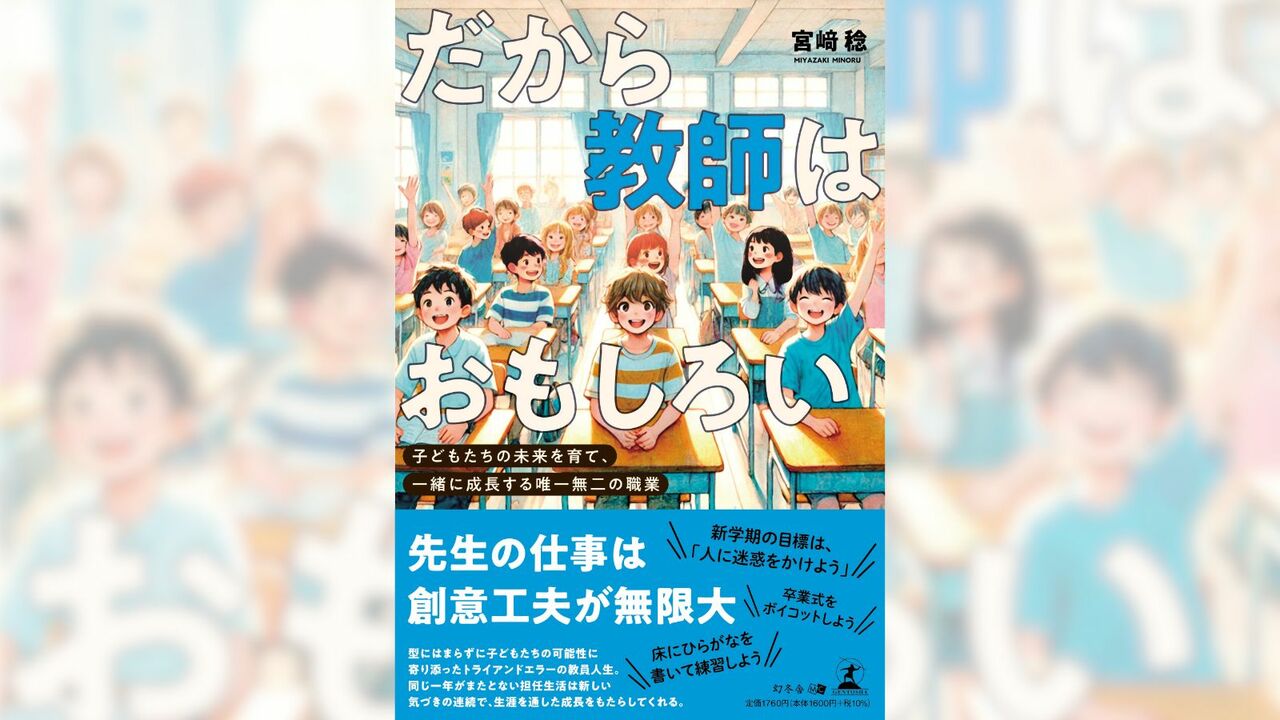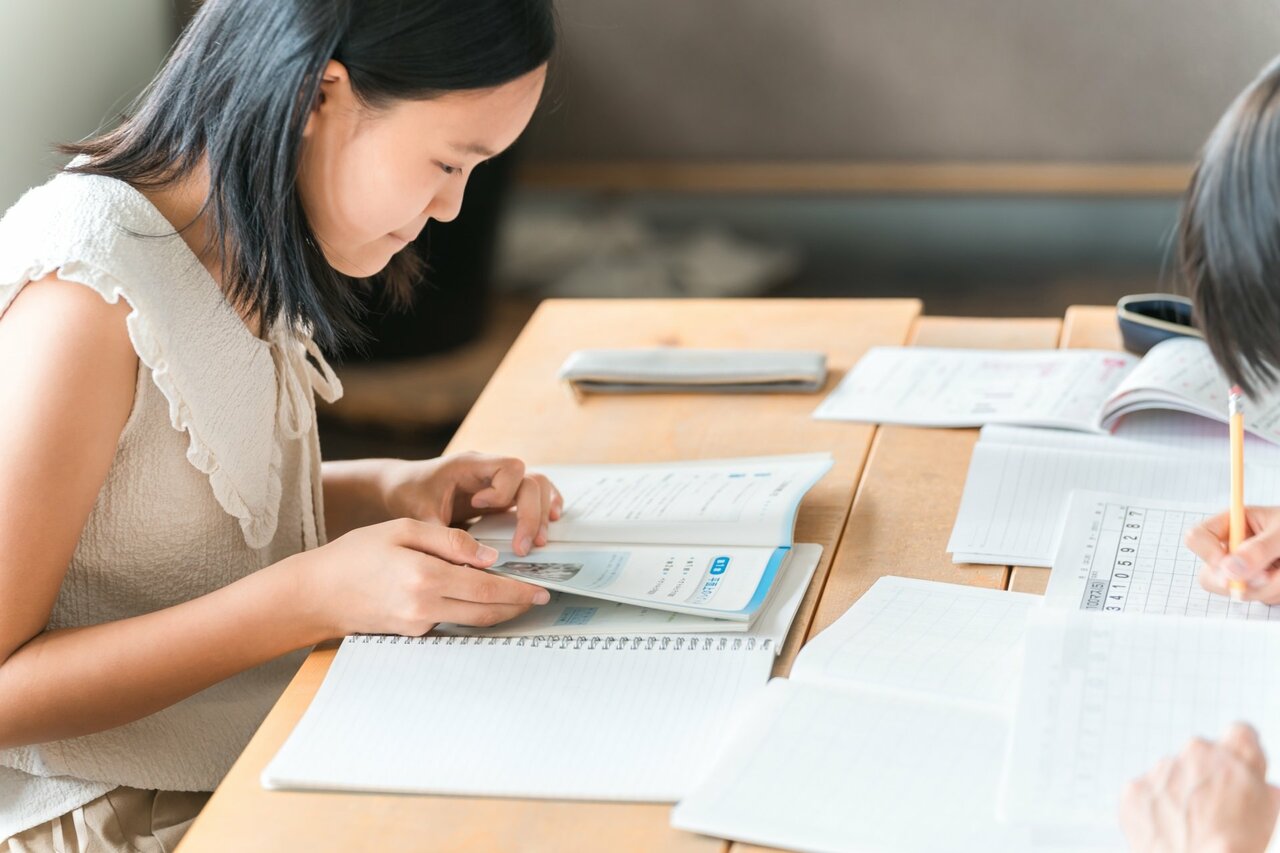【前回の記事を読む】教師の力量が試される学級での集団生活。「本音で考える学級」、「素直と従順は違う」――本当の仲間作りとは何か?
第一章 高学年の子たちと~分数から命の授業まで~
column 自分の子ども時代を反面教師に
そんな学校生活が6年続いた中学2年の3学期に担任のS先生はなんと「卒業式の在校生代表として送辞をしなさい」と私を指名したのです。
担任としてどんな思いで指名したのかは教員になってから見当がつきましたがその時は分かりません。
もちろん私は断り安心して帰宅したのですが、なんとS先生は家まで来て両親を説得したのでした。でも6年間の私の様子を知っていた両親は『不憫だから』と断ってくれていました。
ところがそこへ東京の会社へ勤めていた10歳上の姉が帰宅しました。姉は話を聞くと、「稔、いつまで逃げ回っているんだ。大人になれば人前で話をしなければならないときが絶対来る。その時のためにも、ここで引き受けなさい」と強く言い「先生、引き受けます」とまで言ったのでした。
その後の詳細は省きますが、私は大役を果たすことができました。そしてほかの場面でも話ができるようになり、ときには「おしゃべり」と言われるほど私の人生は変わっていきました。
小学校の教師になってから、自分が小学校時代の大半をつまらないままに過ごしたことを思い返し“学校は楽しいところでなくてはならない。そのための努力をしよう”と心に誓いました。
また話ができなかったことについても、学級の中にはさまざまな理由でやる前から「できない」と言う子がいることもあるだろうから、できないことに安住させておくのではなくいろいろな方法を駆使して『できるように粘り強く指導する』ために子どもの心に寄り添った教師になろうと思ったのでした。
2. 分かったら廊下に出る? できる子にも個別指導
算数の授業ではユニークな方法をとりました。個別指導についていつも疑問に感じていたことを何とか解決したくてとった方法です。
とかく個別指導というと、少し理解が遅れている子に特別な配慮をして何とか他の子に追いついていけるようにするという意識がまだ教育界の主流でした。
そのために教師はいわゆる遅れている子にかかりっきりになることが多く、また早くできてしまう子などはまだ問題が解けていない子の指導に当たらせて、それを称して「役割を与えたから個別に配慮をしていました」とうそぶいていたりする研究会をよく目にしていたのです。
確かに他の子を指導することによって多少は分かり方が定着するかもしれませんが、その子が持っている以上のことをさらに伸ばしてあげているわけではないと思っていました。
『どの子も伸びる権利がある』にもかかわらず、他の子と同じレベルのことをすればそれでよしとする風潮に対し“できる子はできる子なりにさらに伸びる時間にする”という考えのもとにできる子同士も競い合わせたのです。