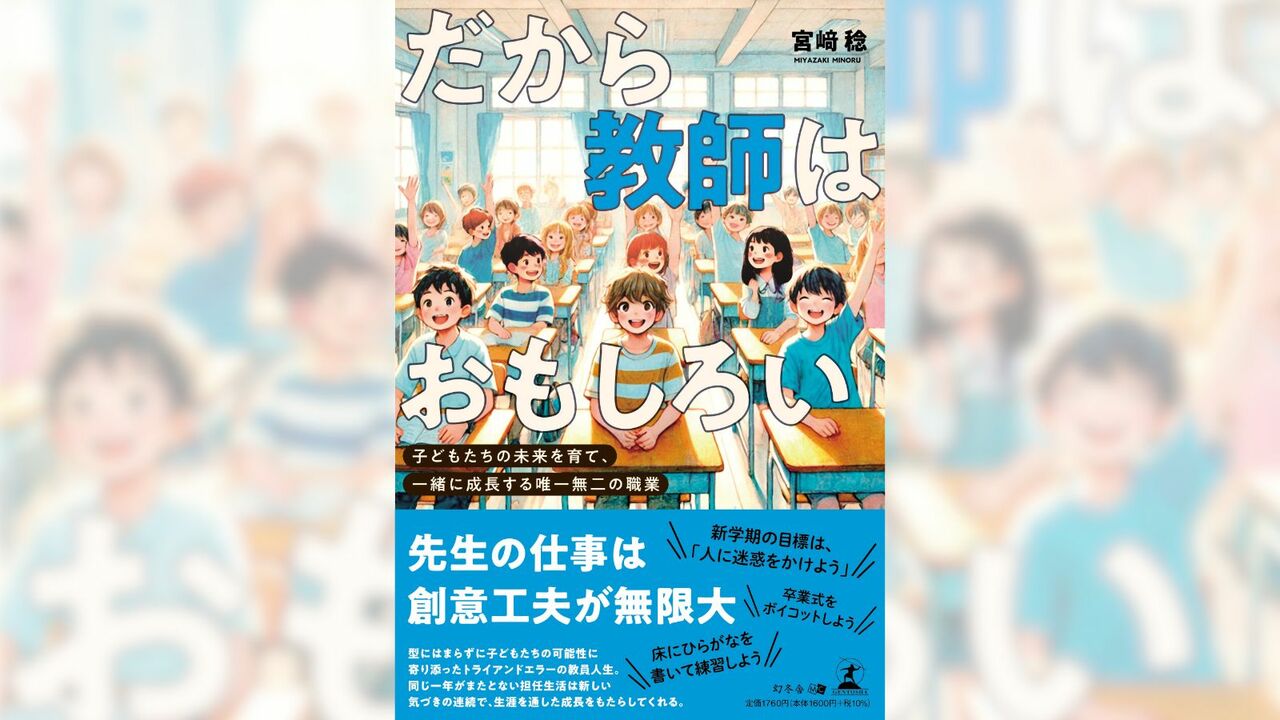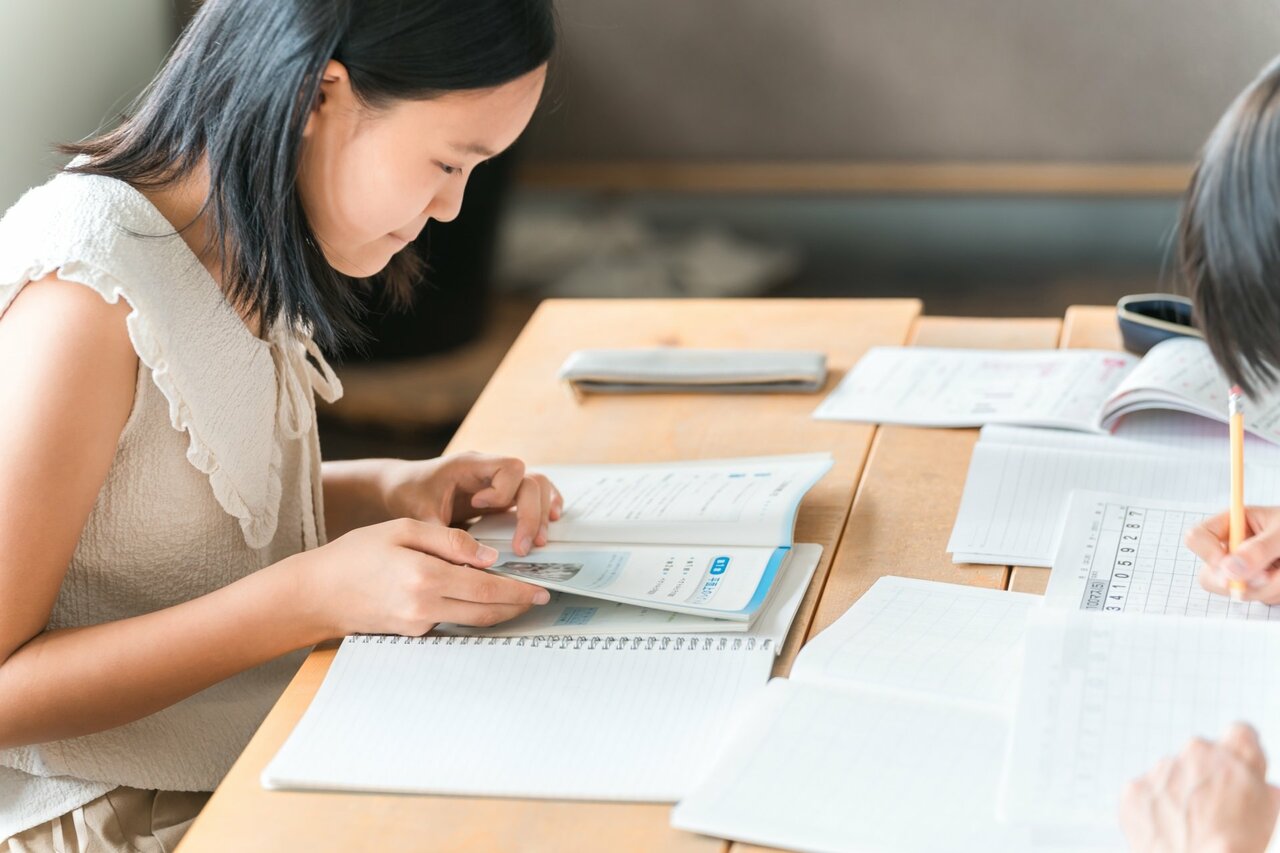【前回の記事を読む】「次の時間も算数を続けます」に、生徒たちは「やったあ~」!? …子ども達が“よく考えよく聞く”習慣を身に付ける勉強法とは?
第一章 高学年の子たちと~分数から命の授業まで~
2. 分かったら廊下に出る? できる子にも個別指導
⑤ 100点満点のテストで、245点を獲った子がいる
さてこうなると、テスト時間が不足してくる子が多くなります。特にいわゆる優秀児童ほど何分でも時間が欲しくなります。普通のテストでは、できてしまった子が時間を持て余していることがよくありますがこの場合は逆なのです。
前に“何分まで”と時間を区切りますが、終盤になって「あと○分です」とコールすると「えっ、もうそれだけしかないの」「あと5分ください」といった叫び声が聞こえてきます。
できなくて時間が欲しいのではなく、もっとやりたくて時間が欲しいのです。これまでは「できたらよく確かめなさい」と言っても、子どもは同じ解決パターンで確かめをすることがほとんどなので、ケアレスミス以外は自分ではなかなか間違いを見つけられませんでした。
しかしテストでもこのように別のやり方で見直すので今度は自分でミスを発見できるようになります。
このテストを採点する私も大変で、200点近い点をとる子はザラで、ある時は最高で245点をとった子がいました。答案用紙は裏もびっしりでした。子どもは本当に発想豊かですからユニークな考えを見つける楽しさもあって続けることができました。
column 40人以上の学級で創意工夫
私が担任の頃は学級の児童数も40人以上だったので、スシ詰め状態のなか一人の教師で対応していたものです。そのため教師は考えられるさまざまな工夫をして、できるだけ多くの子どもに力をつけようと奮闘していました。
しかし多人数を一人で指導するには限界があるので、最近では少人数指導教員などの名目で副担任的に補助教員を配置しています。子どもにきめ細かく対応するためにけっこうなことですが、そのような制度の導入によって教師自身の創造性が奪われてしまっているのではないかと危惧する面もあります。
「こういうことは補助教員にやってもらおう」と役割分担をしてしまい、担任がトコトン考えて『もう限界だ』という状態になるまで工夫しているのだろうかと思うのです。教育の喜びでもある『教師が創造性を発揮して自由に実践する』ということが少なくなってしまうのではないかと思うのです。
5・6年生の2年間担任したYくんは、50歳を過ぎたクラス会の時もこの学習方法を強烈に覚えていて、大学で研究者になっている今でも「自己紹介のときには『私は小学校の時の授業で研究(学ぶこと)の楽しさを知りました』と言うこともあるんですよ」と語ってくれたことがありました。