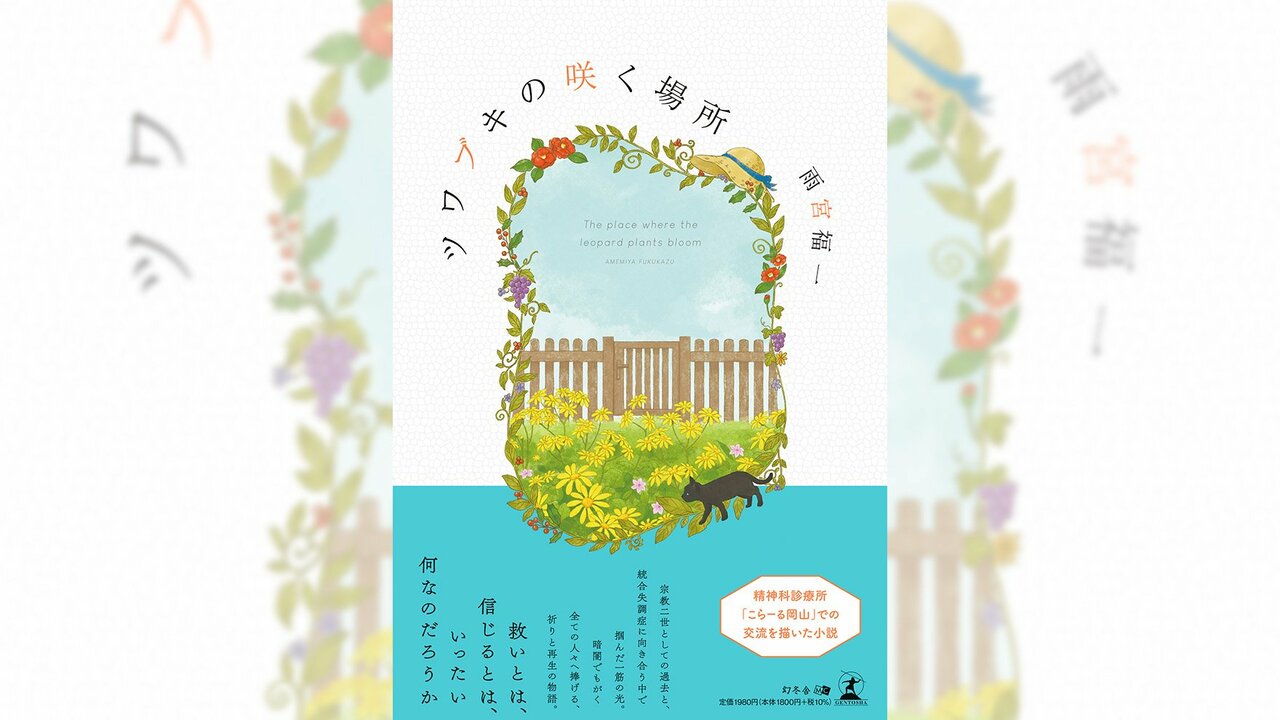【前回の記事を読む】宗教2世として生まれた彼女に選択肢はなかった。――「異端者だ」 ある日、老人をおじいちゃんと呼んだ少女の体は血と痣まみれになった。
第一章 靴
【 一 】
あの日。かたわらでそれを見ていた信者たちは、私がこの救世主をただの老人と扱ったことに激怒した。だからこそ私は殴られ、そのことは、それがどんなに不合理かつ理不尽なことであっても、起きた事実は一向に変わるところがない。
私は殴打され、足蹴にされ、ひどい傷を負うはめになった。 私を手当てしながら、母は、自分たちは地獄に落ちると言うのである。 しかし一方で、母は救いの可能性を話してくれもした。
今思えば、もしかしたら母は、私を助けることさえ満足にできない自分自身に、絶望していたのかもしれない。彼女は私と違って、自らの意志で教団へ所属していた人である。
救世主に楯突くような振舞は、かたく自制して生きてきた。 しかし、信者たちが息子である私に暴行を働くのを見て、また別の感情を持ったからこそ、泣きも笑いもしなかったのだとしたら……。
「いや、やめておこう」
私は母ではないから、あの時の母の気持ちを正確に推し量ることは土台無理である。蒸らし過ぎの茶を湯呑みに注ぎ、一口だけ飲む。淡い渋みが感じられる。
韓国で起きたことの顚末を妹に説明するというのは、私には至極難しいことであるように思われた。あの場所に蝟集(いしゅう)していた大人たちは、一人の例外もなく、文再先という老人を救世主だと信じて疑わない人間である。
教団に生を享けた子らもまた、文再先については親たちと同様の認識でいるよう育て上げられる。そんな環境である。
栄養を摂るため、ということで、サプリメントのような錠剤を渡された記憶もある。 ひょっとするとあの錠剤には、疑いを抱く健全な精神の動きを抑制する効能があったのかもしれない、といった荒唐無稽の疑念すら、起きてくる。
成分すら分からない気味悪い薬を、父も母も、当たり前のように私に飲ませようとした。 怖かったから、私はこれを、飲むふりをして捨てていたのだが、押さえつけられて無理やり飲まされるということも周囲には多く見られた。
それくらい、私の周りの大人たちは文再先を信じきっていた。 私がこうして記憶をたどっても、言葉に簡単にはできないことばかりが起きている。
今もきっと動揺している妹に、どのように話して聞かせてやればいいだろう。 妹が知りたいと望む父母の出会いのきっかけでさえ、伝える言葉が満足に見つからない。
「……救世主を騙(かた)る老人か。そこだけ聞けば、まるで漫画の悪役だな」真実であっても、平穏無事な日本では嘘のように聞こえてしまう。しかし、それこそが私の両親の結婚の理由であるに他ならない。
「……せめて、手紙が届いたことだけは連絡しておこうか」
迷いつつも私はそう呟いた。だが、すぐに今日は平日であったと思い直す。