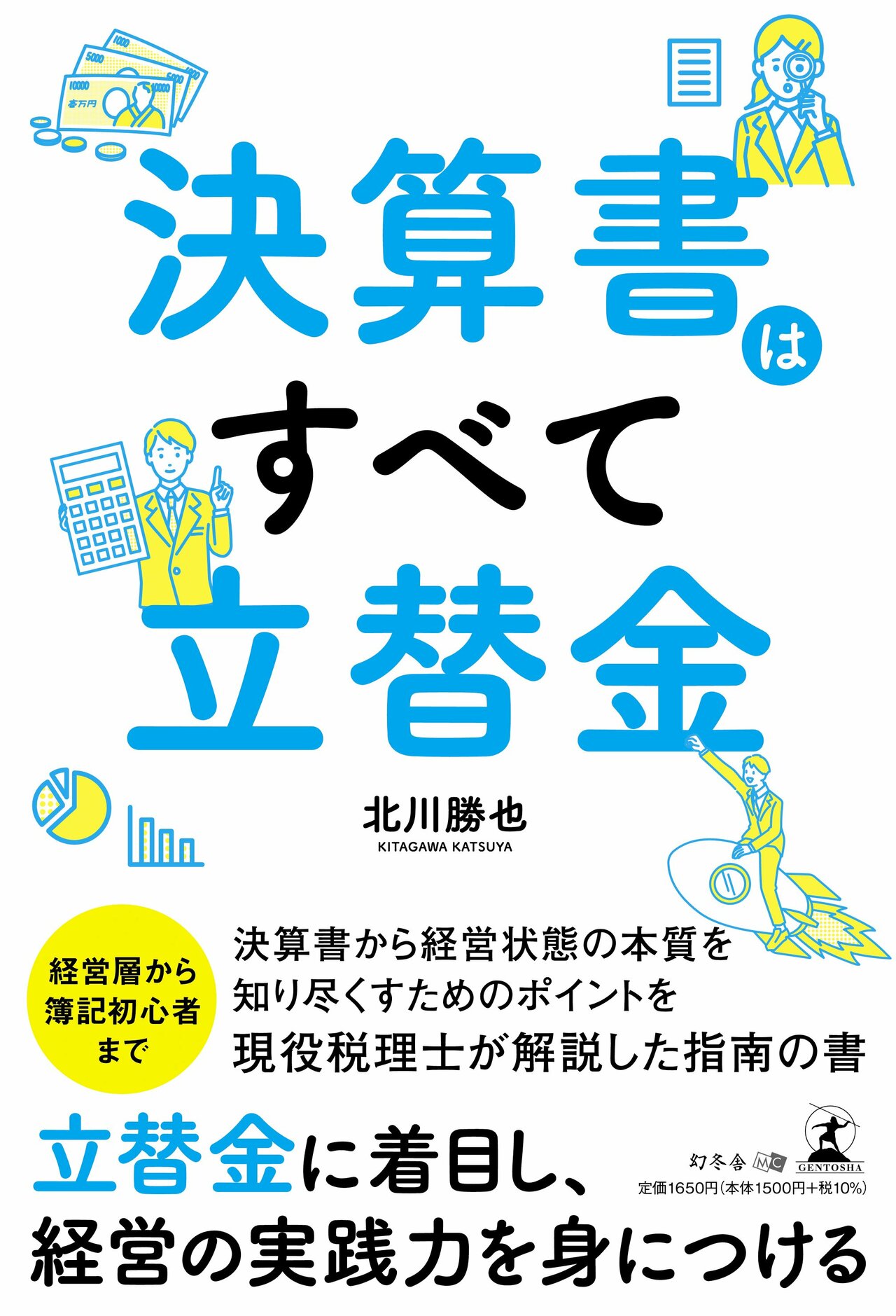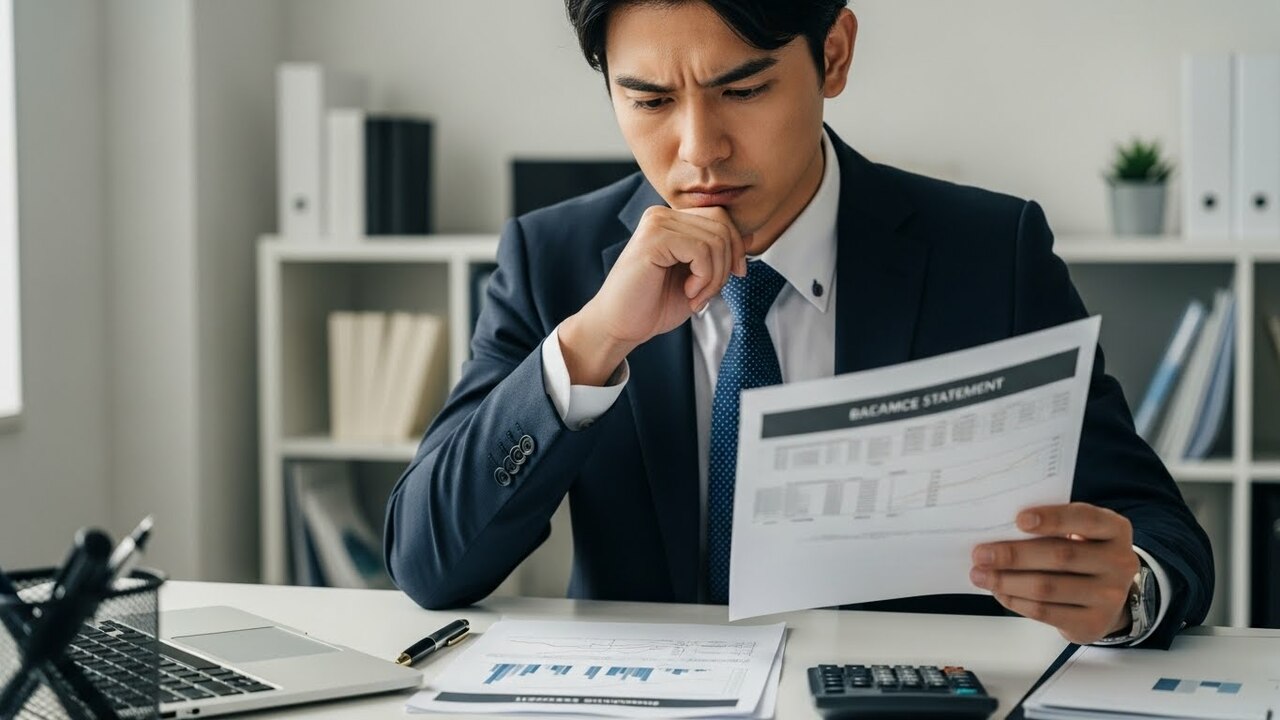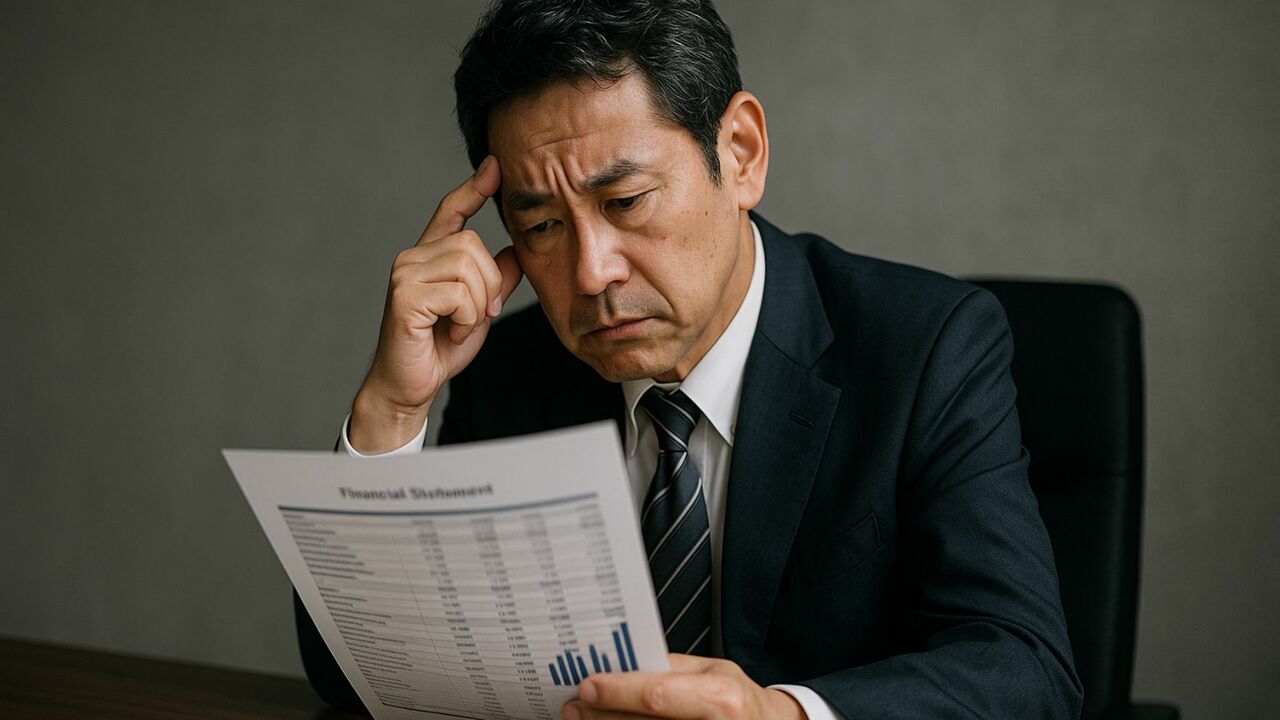この説明に少し戸惑うかもしれませんが、この事実を理解することは「決算書」を正しく読み解く上で不可欠です。
心配しないでください。本書を読んでいただければ、きっと理解していただけるでしょう。
ただ、手元にある資金は「供給者」への支払いや「融資者」への借入金返済に使用されるため、この重要な視点が見落とされやすいのも事実です。
また、簿記の学習においても混乱を避けるため、「預り資金」という表現は一般的には使われていません。
その結果、「現預金」の本来の役割について曖昧な理解をしている人が少なくないと思います。
「現預金」は、単に会社が自由に使える資金ではなく、「出資者」や「融資者」から一時的に預けられた資金、すなわち「預り資金」として捉えるべきものです。
この視点に立てば、会社はその資金を適切に運用し、「出資者」や「融資者」の期待に応えて利益を生む責任を負っていることが明確になります。
彼らが会社に資金を預ける目的は、最終的に利益を得るためです。
言い換えれば、あなたは経営活動において、供給者の債権に利益を上乗せし、それを「出資者」や「融資者」に売却しているのです。つまり、「出資者」や「融資者」に媚びる必要はなく、関係は対等であるということです。
この原理を理解することで、企業の財務管理における資金運用の責任感が強調され、「出資者」や「融資者」との関係性もより明確に意識されるようになります。
企業は、資金提供者の信頼に応え、適切な資金運用を行う責任を常に念頭に置くべきです。
まとめると、「現預金=預り資金」という視点は、経営者に対し、単なる資金運用にとどまらず、資金提供者の期待に応えるという重要な責務を再認識させるものであり、この理解が健全な経営判断につながるでしょう。