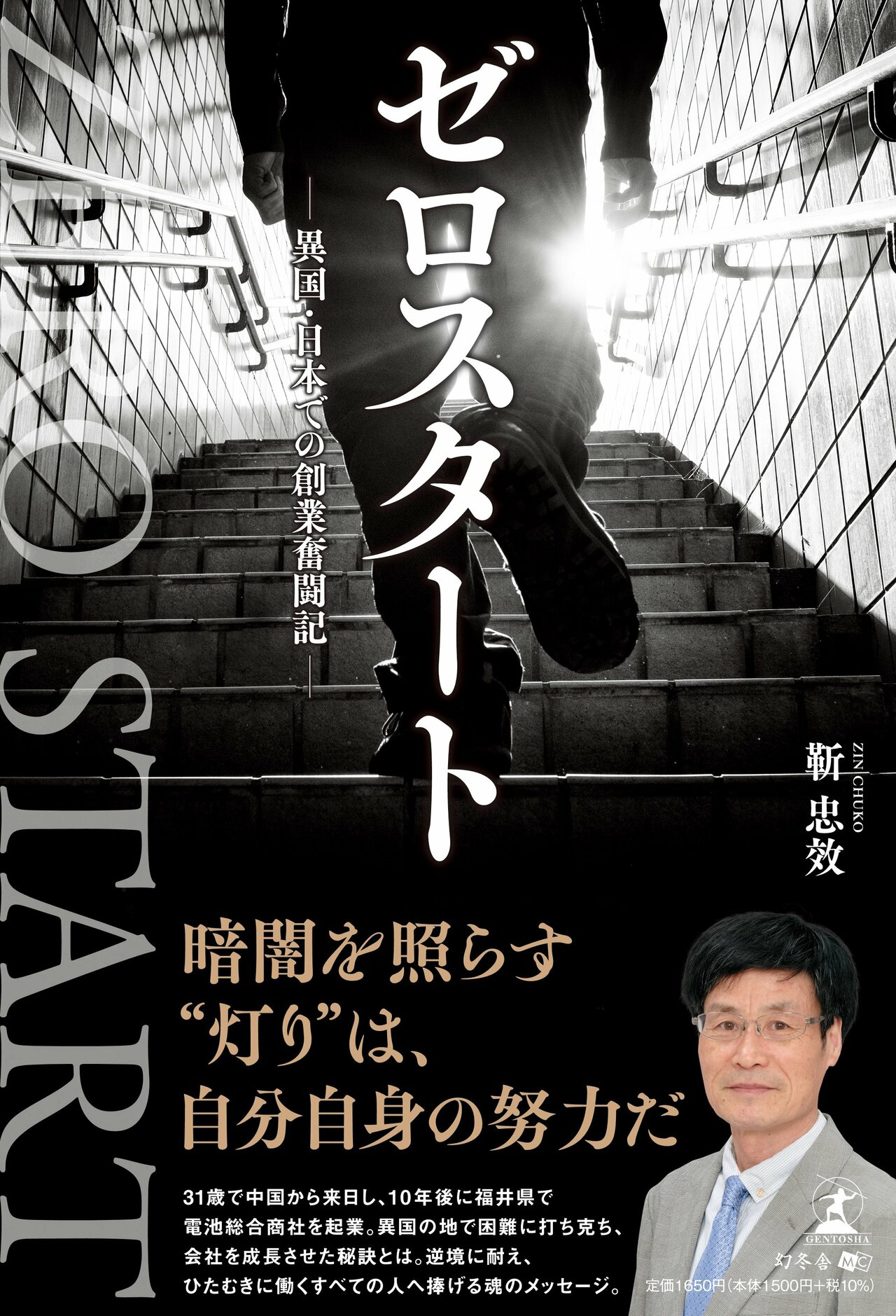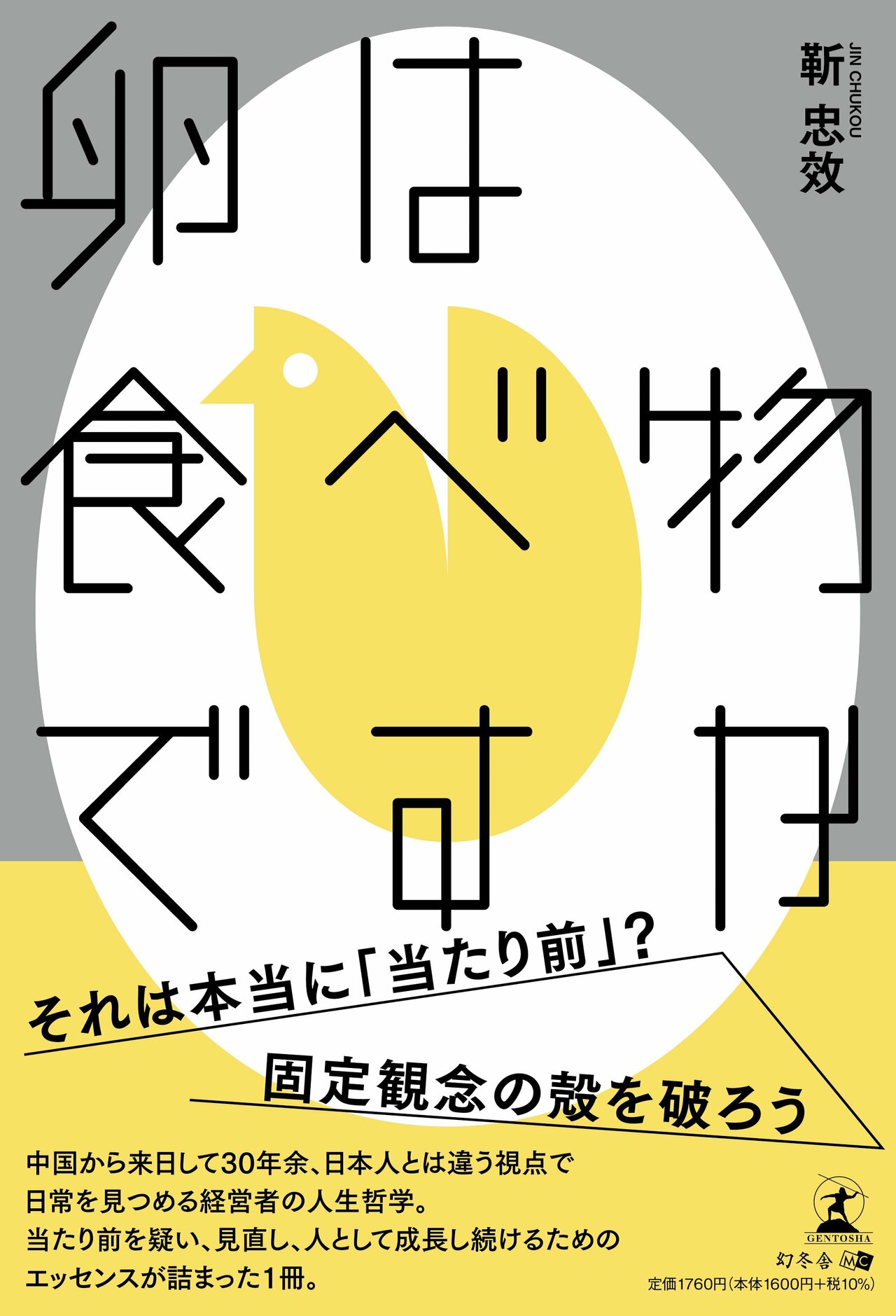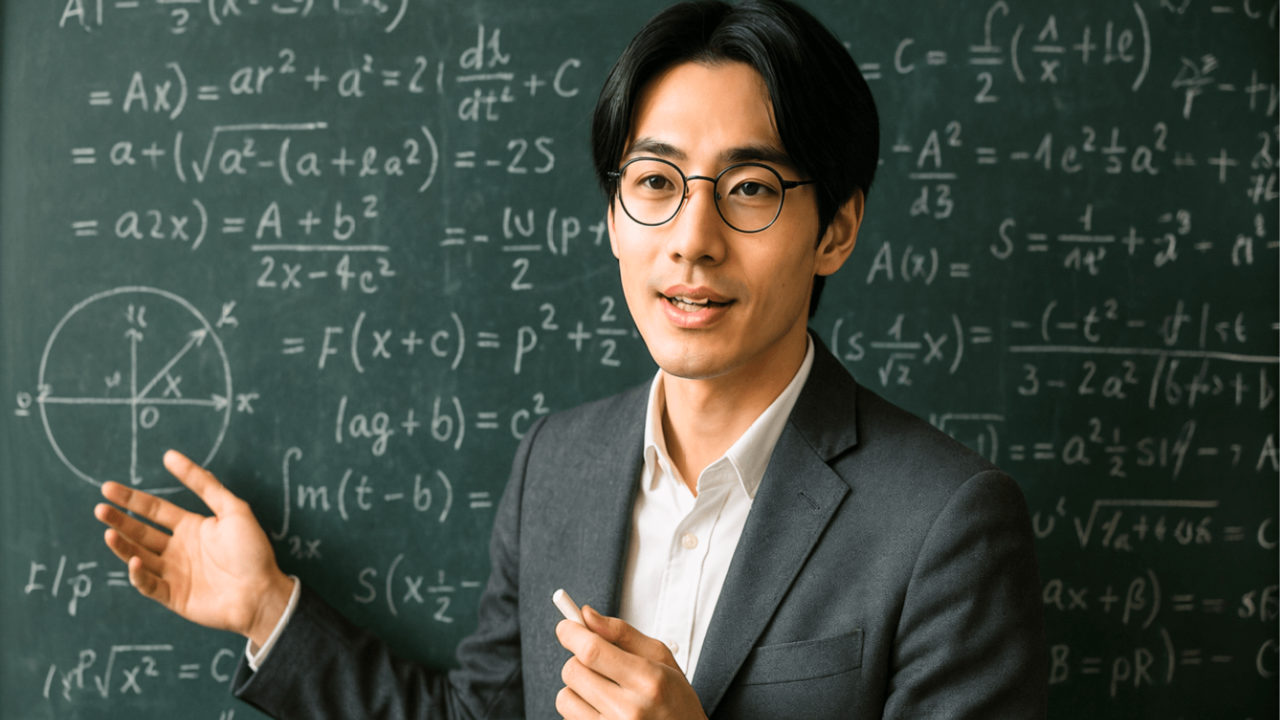学校では正解はひとつです。「1メートルの真ん中は端から0.5メートルの部分」が正解です。しかし現実の社会に出ると正解はひとつではありません。
学生から社会人になる際には、これを知っているかどうかで大きな違いが生まれます。ある人がいっていました。学校時代に優秀な成績を残した人は、実社会に出るとなかなか成功できないことが多いと。
その原因は学校の中での正解にこだわりすぎるからでしょう。社会に出ると、長い人生が待っています。人生はマラソンみたいなものです。それにくらべると学生時代は短い。学校でチャンピオンであっても卒業して現実社会に飛び込むと、良い結果を出すことができない人が多いのです。社会人になってから蓄積した知識こそが重要です。
中国では「本の中にある知識は死んだ知識だ」といいます。パソコンのアプリもそうですが、それをどう使うかによって結果はまったく変わってきます。知識を上手く活用できない人はほとんど失敗しています。
「1メートルの真ん中はどこですか」という問いには原則論プラスアルファの大切さが表現されているのです。それは「幅の大切さ」ともいえます。人生にも幅というものを考えれば、もっと余裕ができます。たとえば大事な面会の約束をしたとき、その時間に絶対に遅れることができないと考えると、1時間も2時間も前に着くようにすることになってしまいます。
そういうふうに思い詰めるより、約束の時間にも幅があり、遅れそうになったら電話で謝ればいい。そう思えると余裕が生まれます。それが大事なのです。
「幅」という言葉でもうひとつ思い浮かべるのは人間や動物の体温です。
人間の体温というと学校では「正常値は37℃」と教わりますが、これにも「幅」があります。37℃ぴったりというわけではなくて、35・3℃が平熱という人もいれば 37・3℃が平熱という人もいます。これは個性です。
ちなみにある本を読んでいて知ったのですが、ほ乳類の体温はみな37℃ぐらいなんですね。動物の体温にも人間と同じような「幅」があるのでしょうか。