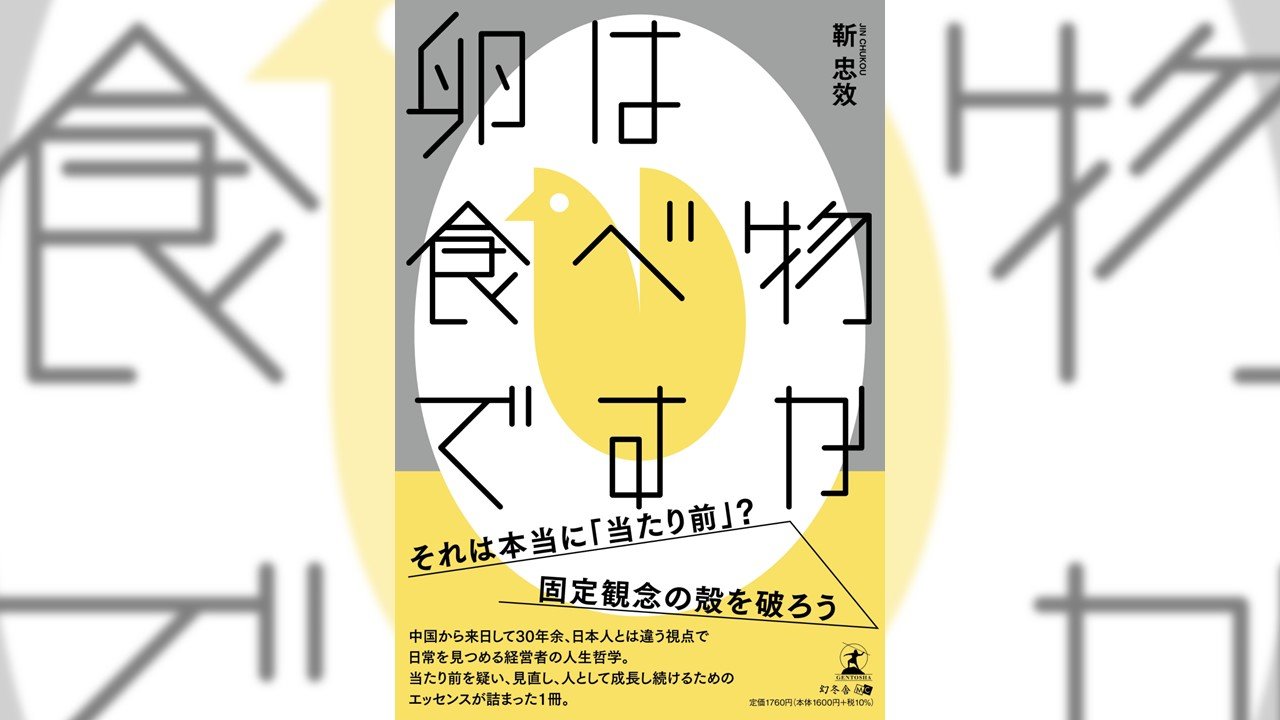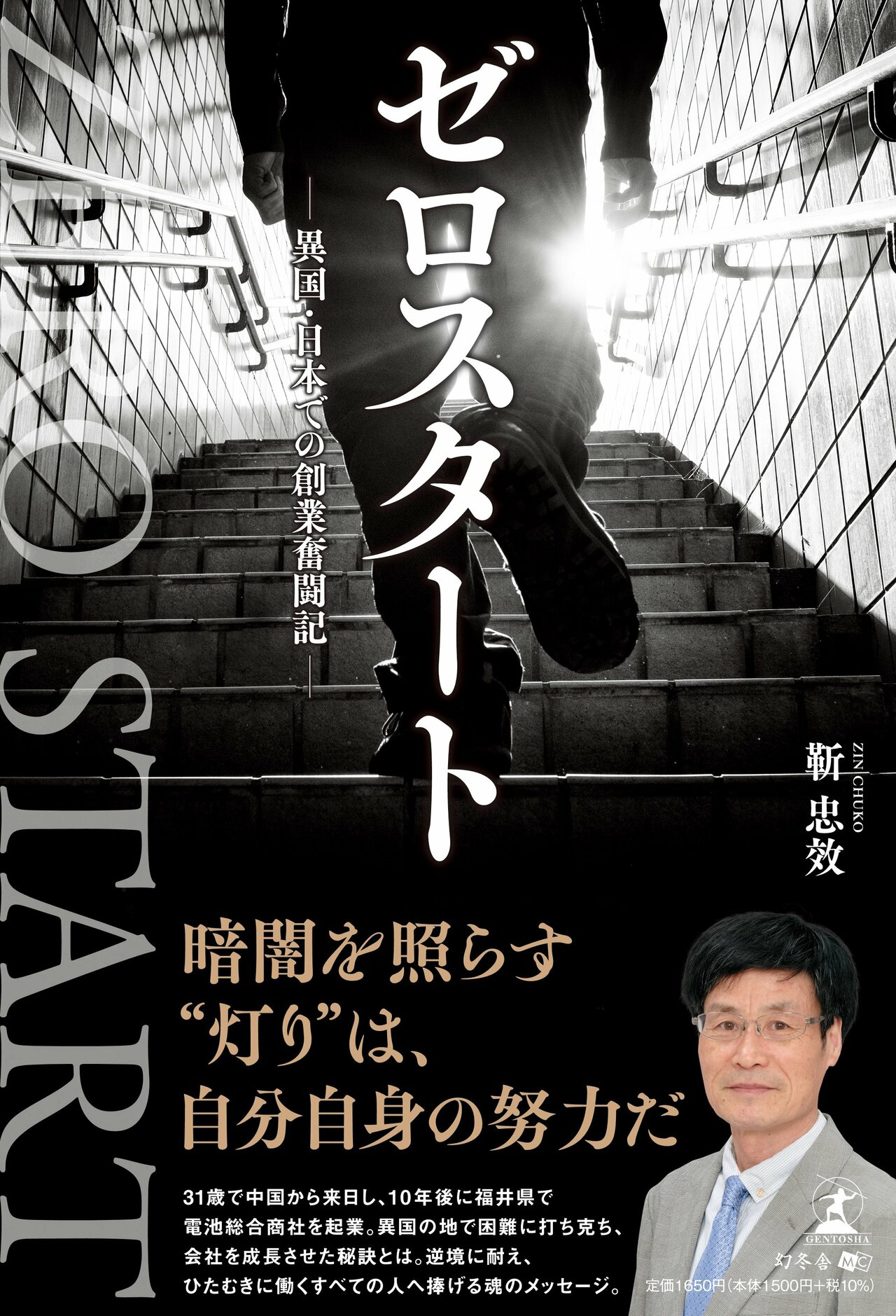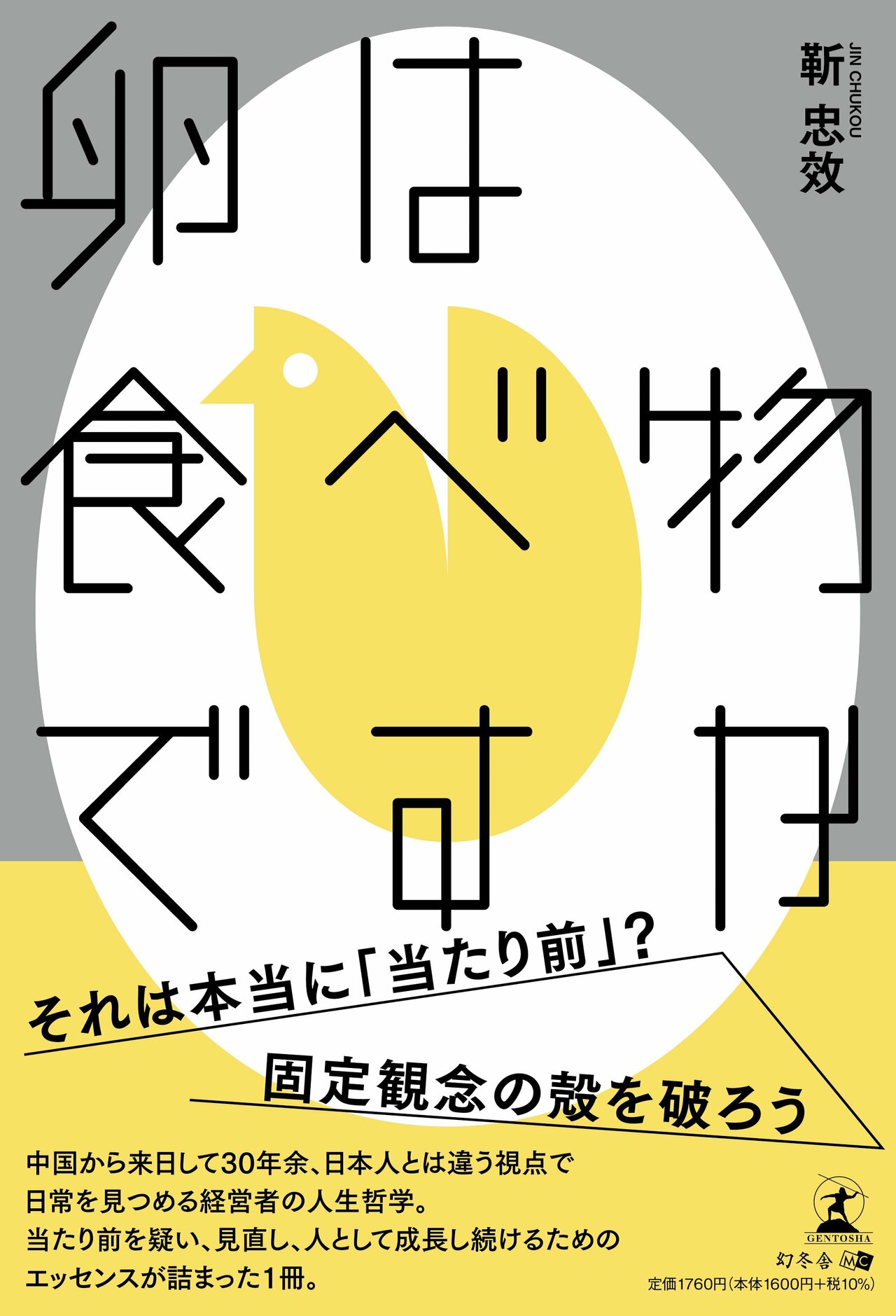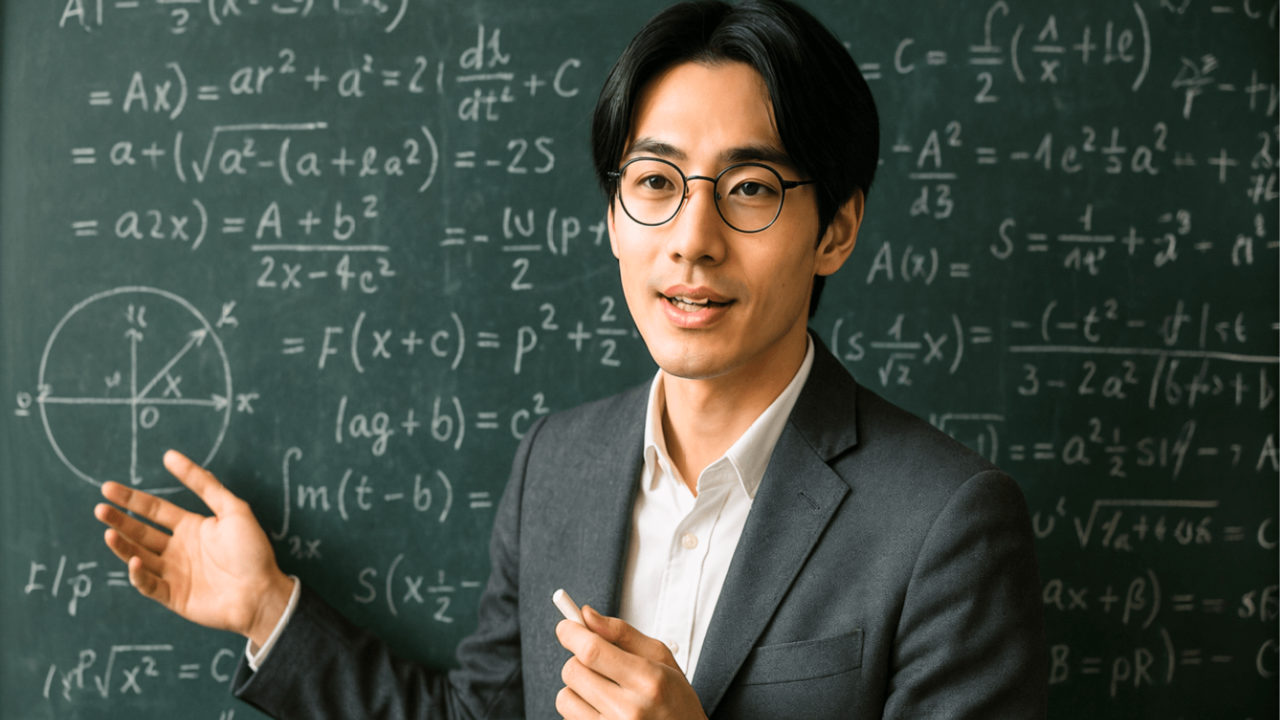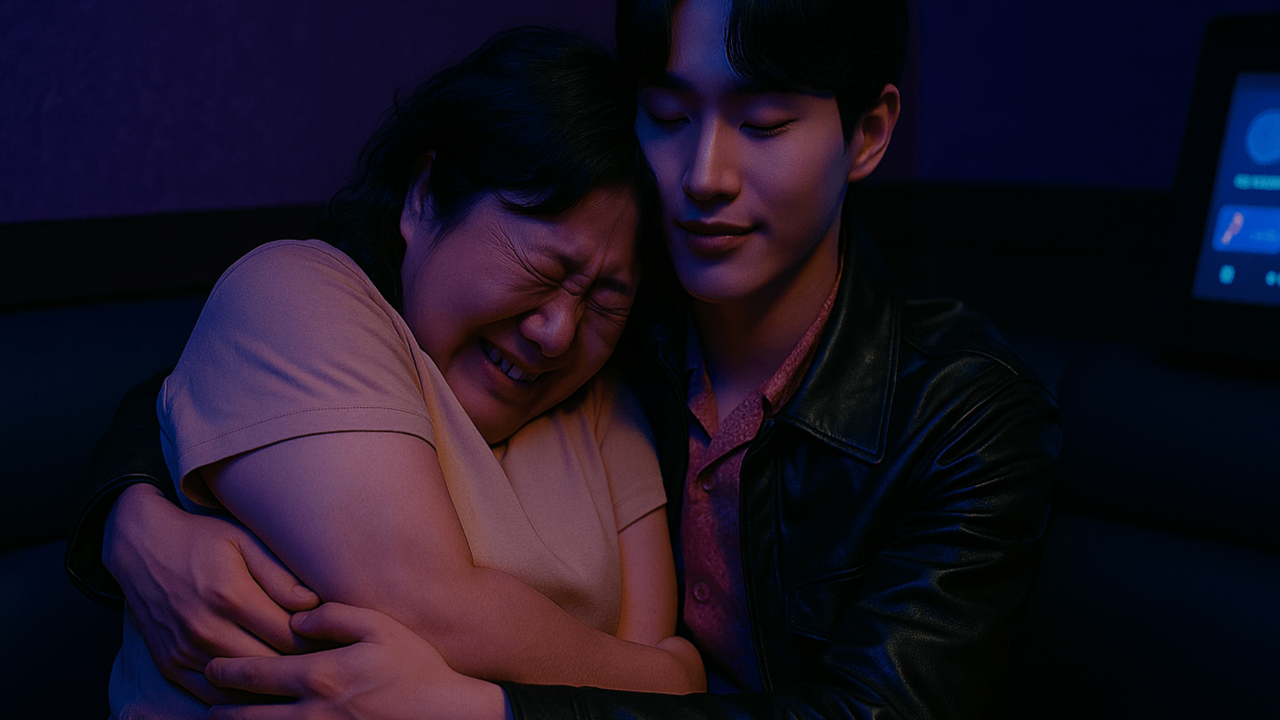【前回記事を読む】柔らかくも強く生きる──老子と黒田官兵衛が示した“水五訓”の知恵
Ⅰ 1メートルの真ん中はどこですか
歴史の本には真実が書かれていますか
私は子どものときから歴史書や伝記が大好きです。こうした本を見つけると、寝食も忘れてむさぼるように読みました。
でも歴史書や伝記が真実を描いているかどうかということを考えたことはほとんどなかったように思います。
「数年前のこともはっきりわからないのに、数百年前の歴史を書いた本は真実を描いているのか」
そういう議論があるのは、もちろん知っています。でも「真実かどうかに意味はない」というのが、この種の議論に対する私の結論です。
私がとくに好きなのは歴史小説とか伝記小説と呼ばれるものです。こうした分野では無限にある事実のなかから作家が自説に都合のいい事実を抜き出して、自由自在に自分の世界を構築していくのが常です。
たとえば、同じ歴史上の出来事という大きな「山」があるとしましょうか。それを前にしてある作家は尾根道から一気に山頂を目指す勢いで駆け上ります。ある作家は川を遡り、沢をつめて山頂を窺うでしょう。またある作家は、となりの山から森や林を俯瞰して全体像を把握するのに努めるかもしれません。
いずれにせよ、こうした作品を読むとき、私が注目するのは、それぞれの作家の、そのテーマに対する見方です。
その作品がどういう構成になっているか。数ある事実からなぜその事実をえらんだのか。そこから現代を生きるどんなヒントがもらえるか。それが大事だと思うのです。
「すこし高い」はどれぐらい高いですか
私が大学生だった頃ですから、もう40年以上前のことです。当時は数学が好きで一生懸命勉強していました。
そんなある日「その人は背が少し高い」というとき、この「少し高い」はいったいどれくらい高いのかと疑問が湧きました。そして数学を使ってこの「少し高い」を表すにはどうしたらいいかと考えました。
たとえば1より大きい数字は「>1」で表せますが、ここにはどれくらい大きいのかというニュアンスを表すものは含まれていません。われわれ人間が日常的につかう「少し」「ちょっと」という言葉に含まれるニュアンスを数学的に表すのは実はとても難しいことだとわかったのです。
それがわかったとき私は「数学にも限界があるんだなあ」と思うと同時に、人間の曖昧さというものが素晴らしく思えてきました。
日本人の平均身長は男性が約171センチ。女性で約158センチといいますから、
「少し背が高い男性」といわれれば、普通175センチぐらいの身長の人をだれもがイメージするでしょう。
でも実際にそれぞれにイメージする「少し背が高い男性」の身長を測ってみることができたら、それはその人ごとに違っているはずです。それなのに「少し背が高い男性」というイメージは共有できます。
さらにおもしろいのは「すこし」とか「ちょっと」といった言葉の意味が人間同士で異なっているだけでなく、自分の中でも日々変わっているかもしれないということです。自分の中で今日の「ちょっと」と来年の「ちょっと」が違っているかもしれないと気付いたとき、おもしろいなと感じました。
こういう曖昧さは数学では扱うのが難しいし、いま流行している「AI」も苦手な分野なのです。