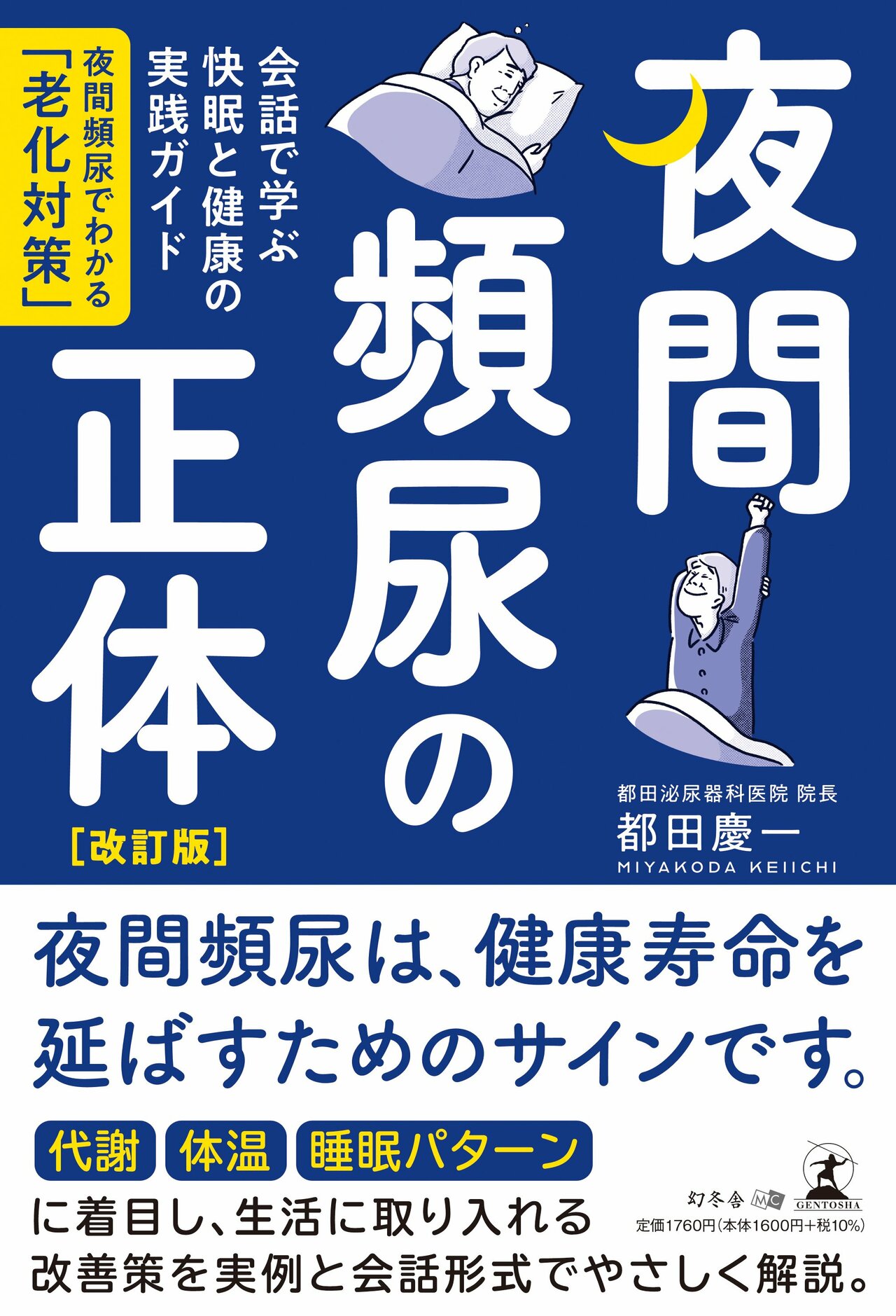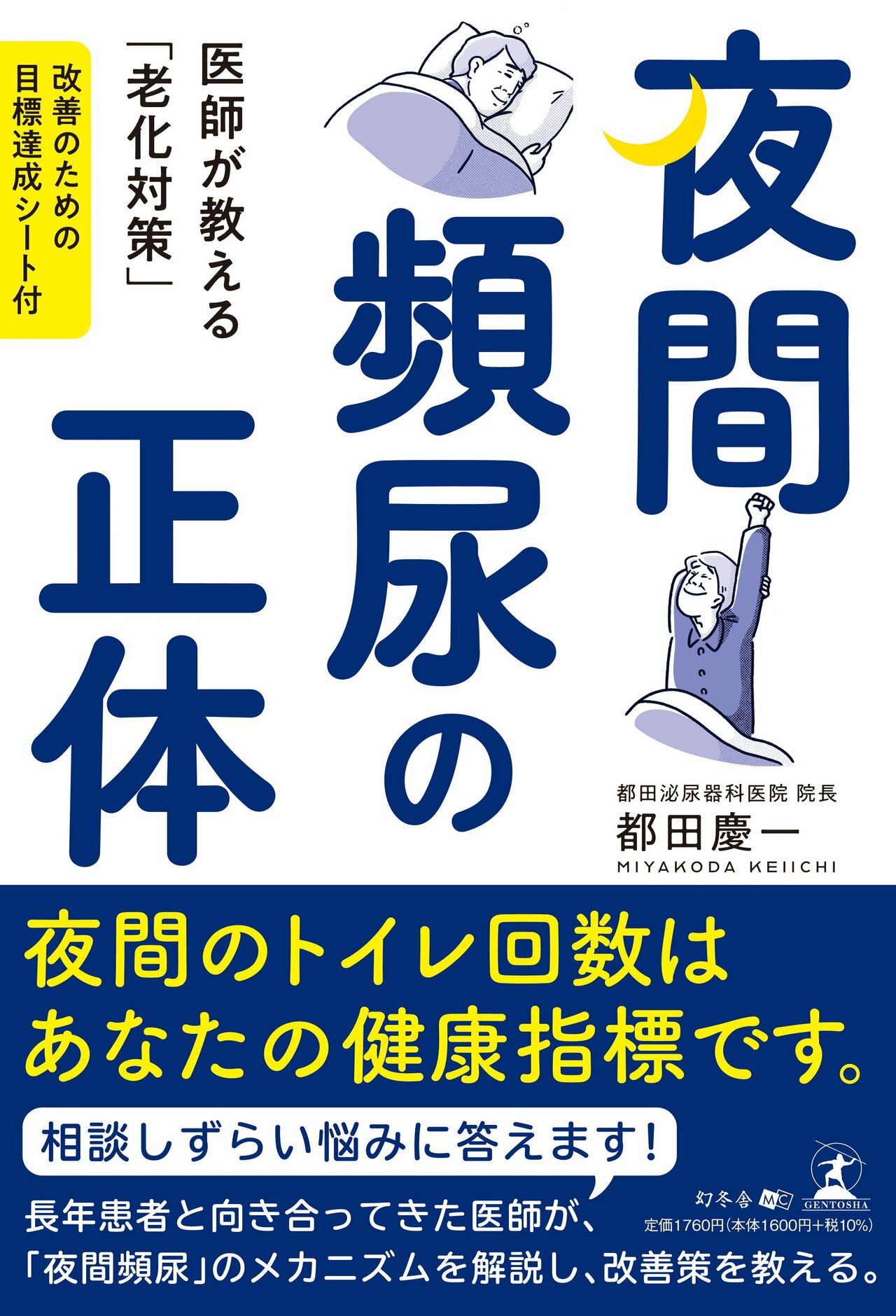▼2回が分岐点
年代が上昇するにつれて、治療抵抗性が出てきており、治療で1回以内(≦1・5)が占める割合が、高齢化に従って減少しています。しかし、80代でさえ1回以内(≦1・5回)の合計が全体の60%以上を超えています。
また、年齢世代が高くなるほど2回(1・5 <x 2・5)が占める頻度が図⑥.でもわかる通り、頻度が高くなっていることに注目してください。2回(1・5<x≦2・5)が高齢世代になるに従ってバラついて増えていきます。
夜間頻尿の抵抗性の改善目標は、夜間回数2回の範囲を改善していくことであると思います。すなわち、1・5回以内(≦1・5)にできるだけおさえることです。その分岐点が2回(1・5<x≦2・5)で、それを常態化しない努力が必要であると感じています。
各年代の2回の割合について、年代が上がるにつれて徐々に増えており、夜間頻尿の抵抗性が生体機能の劣化で次第に増えていく様子がよく現れています。
▼90代
元気に通院する90代になると、さすがに2回以上が多くなり、3回以上の治療(内服+生活指導)無効の人が2割近くになります。
やはりどうしても活動水準が落ちて生体機能の低下傾向が出るため、プレフレイル、ロコモ症候群、サルコペニア、フレイルなどが多くなり、無為にじっとしていることが多くなります。不可逆的に代謝が落ちていく人の割合が増えるに従い、夜間回数は生活指導に対応できなくなるし、内服薬も抵抗性が強くなることがうかがわれます。
このグラフでわかることは、80代においても夜間排尿回数の2回(1・5<x≦2・5)を常態化しないことが治療の努力目標になるということです。2回(1・5<x≦ 2・5)をいかに1・5回以内(≦1・5)にもっていくかの努力が必要です。よって、80 代でも治療(内服+生活指導)の目標値は2回未満としたいと思います。
次に、2019年の大阪の7月(平均気温26・5℃)から翌年1月(8・6℃)までの季節変化の中で、夜間回数1回以内と3回以上の割合を用いて年代別の変化を追い、さらに医院初診者の年間を通して増える時期を調べて季節との関係をみてみました。
【イチオシ記事】ずぶ濡れのまま仁王立ちしている少女――「しずく」…今にも消えそうな声でそう少女は言った
【注目記事】マッチングアプリで出会った男性と初めてのデート。食事が終わったタイミングで「じゃあ行こうか。部屋を取ってある」と言われ…
【人気記事】「また明日も来るからね」と、握っていた夫の手を離した…。その日が、最後の日になった。面会を始めて4日目のことだった。