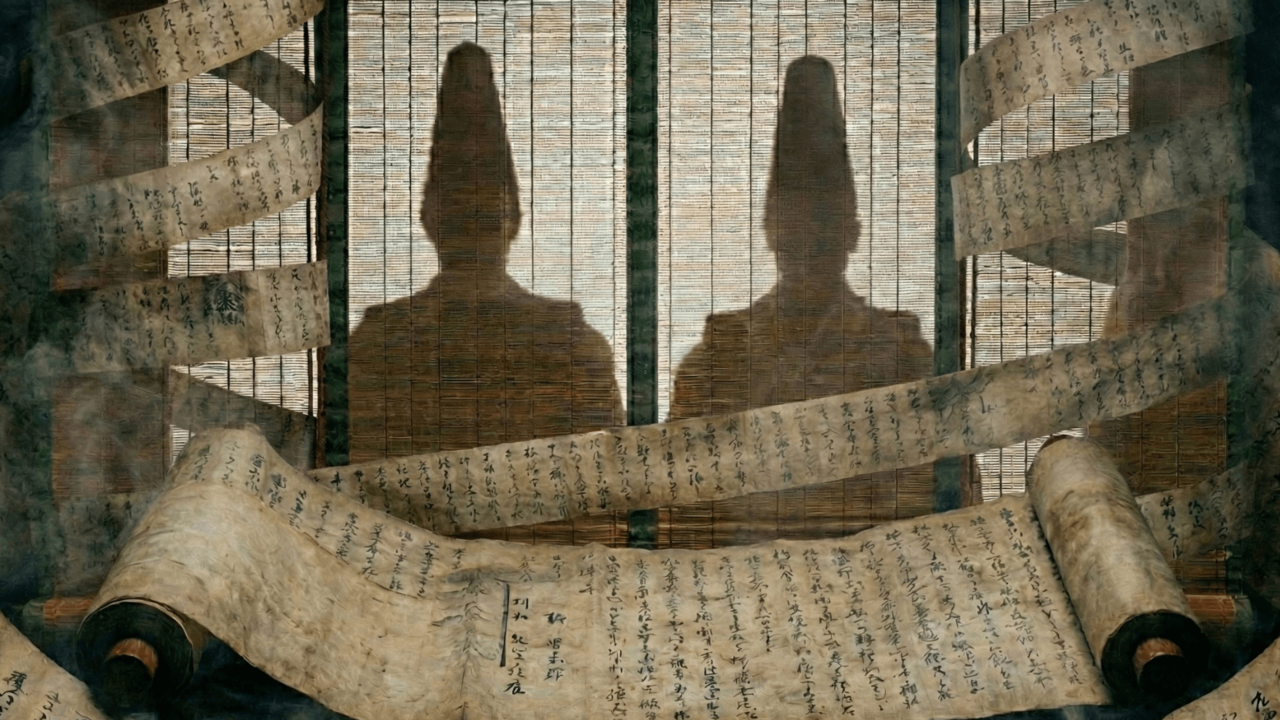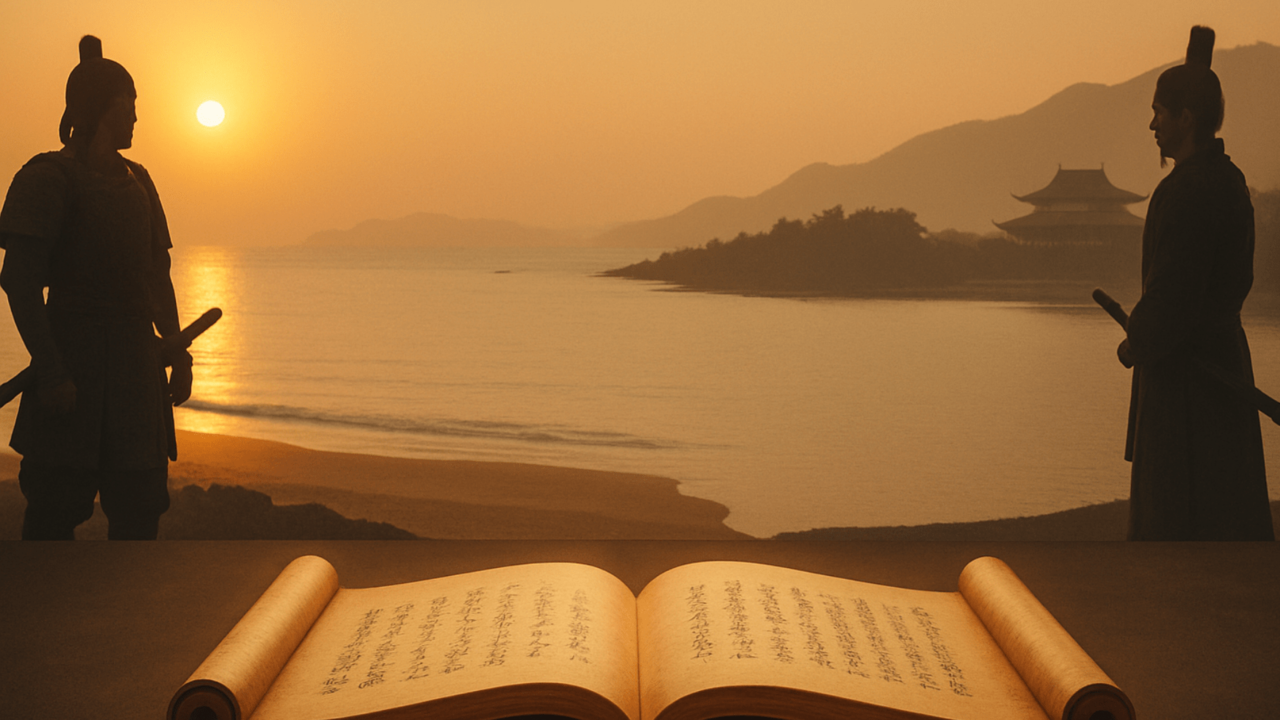文献・金文の章
第二話 「倭の五王」 と「倭王武」の上表文
古墳時代の政治を反映する一級資料が存在する。『宋書』夷蛮伝にある「倭王武」の上表文である。これを吟味する前に、「倭の五王」が日本史において歴史学者の悪癖にまみれていることを見てみよう。
「倭の五王」を一六代「仁徳天皇」(あるいは一七代「履中(りちゅう)天皇」)から二一代「雄略天皇」に比定する歴史書や参考書は多い。しかしこの組み合わせが成立しないことを指摘する在野の歴史研究家の合理的見解は、歴史学者の固陋(ころう)の壁に跳ね返されている。
なぜ「倭の五王」が「大和天皇家」に対応しないかを考察する。まず中国と日本の史書を対応させる根拠がどれほど合理性を持つのだろう。
1.五王の親子兄弟関係が、「履中天皇」から「雄略天皇」まで似ている
2.讃は「履中天皇」のイザホワケのザの音をうつしかえた
3.珍は「反正(はんぜい)天皇」(一八代)の「瑞(みず)歯別」の瑞の字が転訛した
4.済は「允恭(いんぎょう)天皇」(一九代)の「雄朝津間(おあさずま)」の津の字が転訛した
5.興は「安康天皇」(二〇代)の「穴穂」の穂の字が転訛した
6.武は「雄略天皇」の「大泊瀬幼武(おおはつせわかたけ)」の武である
7.『宋書』に載せられた「倭王武」の上表文に「東に毛人を征す」「西に衆夷を服す」とあり、日本の東西の中央部つまり大和に武の本拠地がある
7については後述するが、1から6のまったく統一性も合理性もない五王=「大和天皇家」説に以下の五点で反論したい。
⒜ 歴代天皇の実在証明がない。「古墳がある」「『記紀』に載っている」から実在すると考えるのは、「河童塚がある」「河童伝説がある」から河童が実在すると考えるのと同様非科学的論法だ。
⒝『記紀』には中国南朝(五世紀)宋時代に朝貢や交流についての記述は一切ない。
時代を遡るが「神功皇后」の代に、『魏志倭人伝』が引用され、あたかも卑弥呼に対応するかのように工夫されている(引用資料1)。このことは『記紀』編纂時に、中国史書を読んでいたことを示しているが、『宋書』夷蛮伝の引用は全く見られない。
⒞『記紀』を読む限り「大和天皇家」に一字名の習慣はない。むしろ修飾を施し長名にする傾向があることは周知の事実である。
⒟中国側が倭王の改名を行った可能性はあるか。中国史書の倭国に関する記事には、南朝時代以前、以後とも一字名の例はなく、すべて表音漢字を宛てている。『後漢書』に「倭国王 師升」、魏志に「太夫難 升米(なしめ)」「次使 都市牛利(つしごり)」「使太夫 伊聲耆(いせき)、掖邪狗(えやく)」、『隋書』に「阿毎多利思比孤(あめのたりしひこ)」など。
中国南北朝時代の史書における朝貢記事を総ざらいして、この時代の習慣として外国の王や首長の一字改名やその転訛が有り得るのか検討すべきだろう。
ただ中国皇帝が「お前の国の王は名前が長すぎる。もっと短い名前を与えよう。」だとか、中国の史官が「こんな長い名前より一文字のめでたい字の名に変えよう。」などの場面を空想するのは面白いが、常識的にはあり得ないだろう。
もしあったなら、史官はそのことをも記録するはずだから。
引用資料1 「神功皇后紀」巻第九『魏志』引用の記事 三九年。
是年(ことし)、太歳己未(つちのとひつじ)。魏志(ぎし)に云はく、明帝(めいてい)の景初(けいしょ)の三年の六月、倭(わ)の女王(じょわう)、大夫(たいふ)難斗米等(ら)を遣(つかは)して、郡(こほり)に詣(いた)りて、天子に詣(いた)らむことを求(もと)めて朝献(てうけん)す。太守(たいしゅ)鄧夏、吏(り)を遣(つかは)して将(ゐ)て送(おく)りて、京都(けいと)に詣(いた)らしむ。
四〇年。魏志に云はく、正始(せいし)の元年に、建忠校尉梯携等(けんちうこういていけいら)を遣(つかは)して、詔書印綬(せうしょいんじゅ)を奉(たてまつ)りて、倭国(のわくに)に詣(いた)らしむ。
四三年。魏志(ぎし)に云(い)はく、正始(せいし)の四年、倭王、復使大夫(またつかひたいふ)伊声者掖耶約等八人(らやたり)を遣(つかは)して上献(しょうけん)です。
【前回の記事を読む】【日本史】史実が書かれていない第2~9代天皇、「欠史八代」。天皇は実在したのか、創作なのか? 否、別の可能性が…
【イチオシ記事】あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。初めて体を滅茶苦茶にされたときのように、体の奥底がさっきよりも熱くなった。