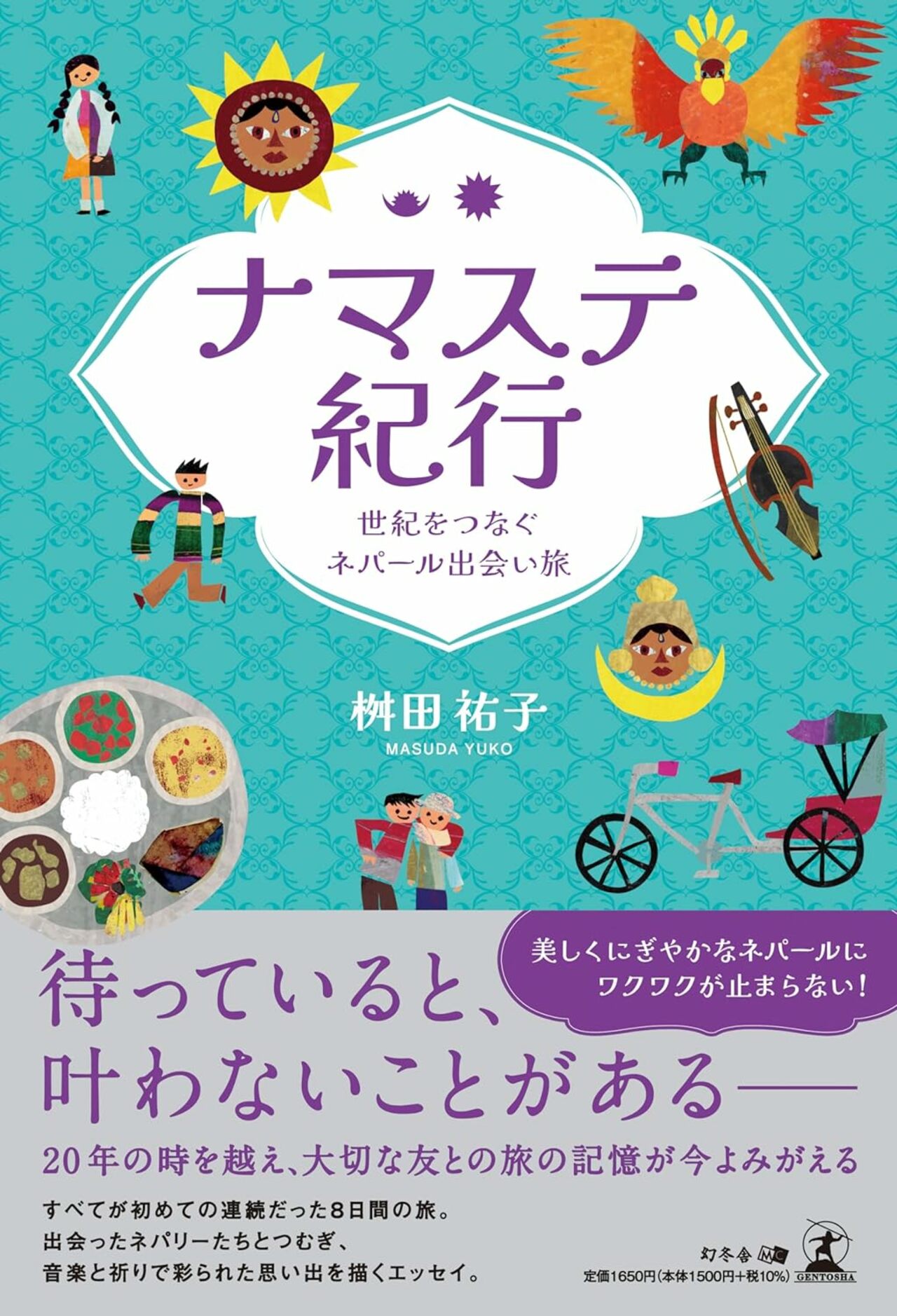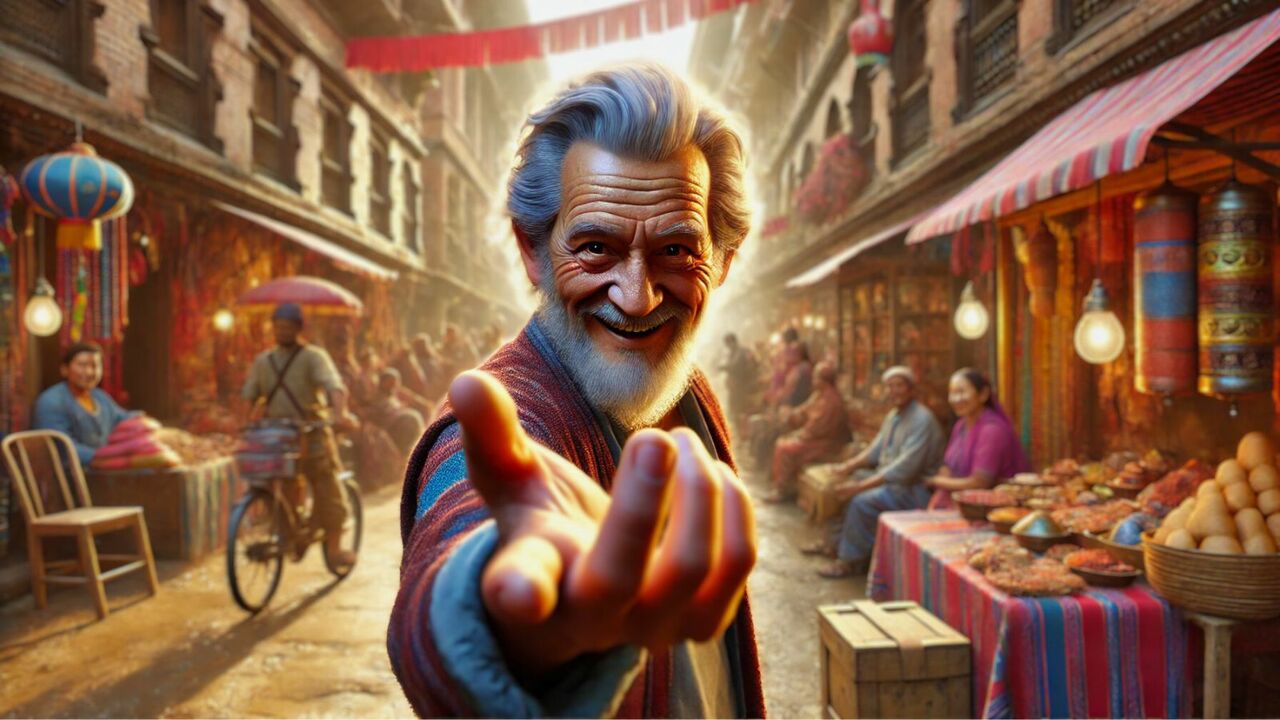そんなクマリに選ばれる条件の中で、興味深いものがある。
・菩提樹のような体
・子牛のようなまつげ
・獅子のような胸
・鹿のような脚
・アヒルのように柔らかく透き通った声
「~のような○○」というたとえが面白い。いかにも古くからの言い伝えという感じだ。誰にでもわかりやすい一方で、どのようにも受け取れる曖昧な表現。この緩い表現だからこそ、条件として長く続いているのかもしれない。
しかし、それらの条件をクリアした後の最終試験には驚いた。祭りの際に生け贄として捧げる動物の頭部を、同じように並べた暗い部屋に閉じ込め、泣いたり騒いだりせずに耐えられるかどうかを試すという。まさに肝の据わった選ばれし少女だけが、この大役を担うことができるというわけである。
二〇〇八年の王政廃止に伴い、クマリの制度についても変化があったようだ。毎年九月に行われるインドラ・ジャトラ祭において、クマリがひざまずく国王の額にティカを付け、翌年の統治を行う権利を与える祝福の行為は行われなくなった。
その代わり、クマリが山車の巡行に出発する際には、大統領や首相が白い宮殿のバルコニーに並んで見送っているという。また、クマリの生活も、教育を受けることや家族と過ごす時間が以前よりもさらに保障されるなど、改めて見直しが図られている。
こうした様々な問題点を抱えながらもクマリの制度が廃止にならないのは、それだけネパールの人たちにとって大きな存在だということを示している。ヒンドゥー教と仏教が共存するこの国で、クマリはどちらの女神でもあるからだ。
さて、頭から血が出なかったのはよかったが、逆に友人は心配して、絶えず頭のこぶ周辺を診てくれた。幸い、大事に至ることはなかった。ネパールでは自分の身は自分で守る。旅行中ずっと付き添ってもらうこの痛みを、たたりではなく旅の守り神だと思うことにした。
【前回の記事を読む】ネパールの支援活動に協力することになった私たち。使われなくなった日本の鍵盤ハーモニカを、スーツケースに詰めて…
【イチオシ記事】あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。初めて体を滅茶苦茶にされたときのように、体の奥底がさっきよりも熱くなった。
【注目記事】急激に進行する病状。1時間前まで自力でベッドに移れていたのに、両腕はゴムのように手応えがなくなってしまった。