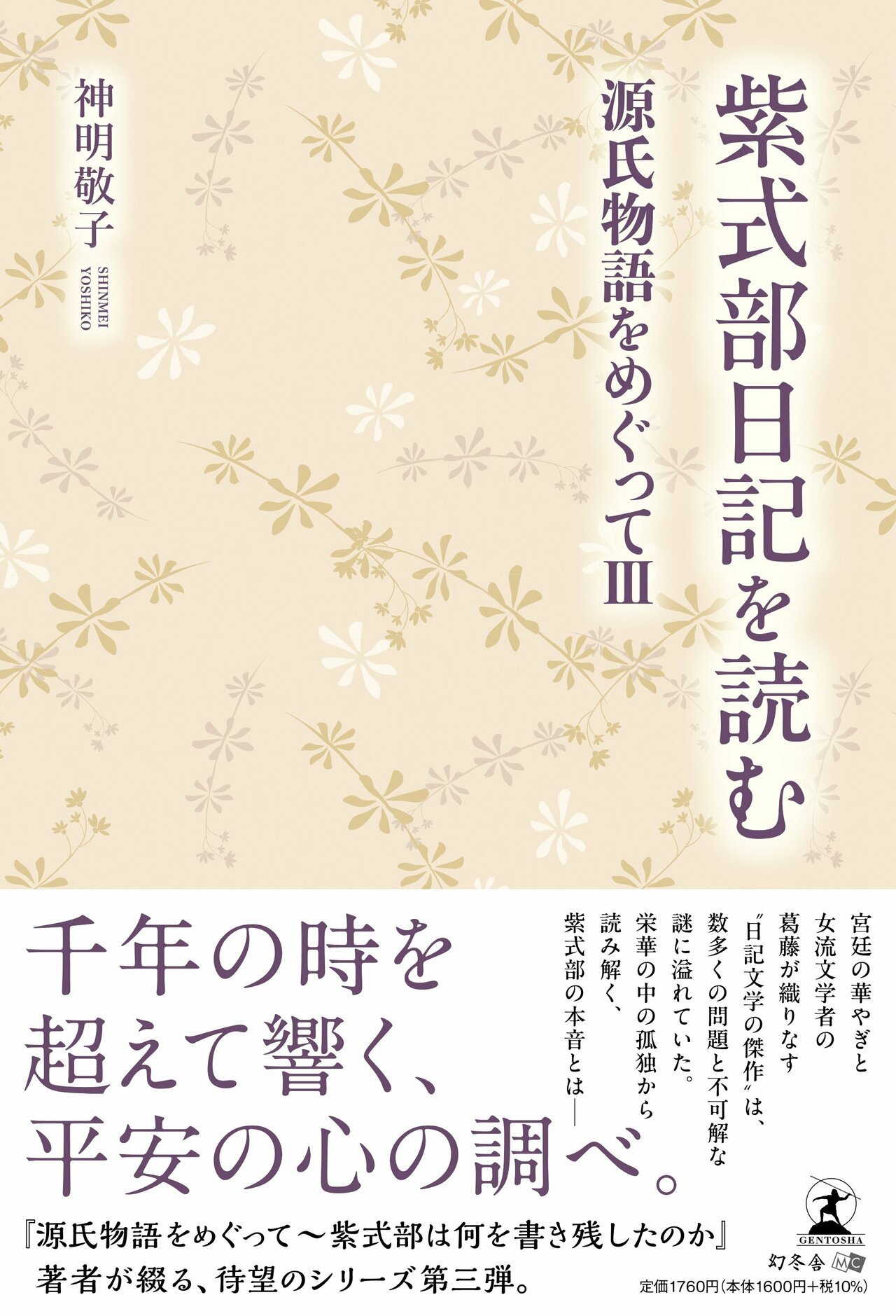第一章 紫式部日記
一 現行日記に沿って
冒頭
秋のけはひ入(い)りたつままに、土御門殿(つちみかどどの)の有様、いはむかたなくをかし。池のわたりの梢(こずゑ)ども、遣水(やりみづ)のほとりのくさむら、おのがじし色づきわたりつつ、おほかたの空も艶(えん)なるに、もてはやされて、不断(ふだん)の御読経(みどきやう)の声々、あはれまさりけり。やうやう涼しき風のけはひに、例の絶えせぬ水のおとなひ、夜もすがら聞きまがはさる。
(一二三)
この冒頭を口語訳すると、次のようになる。
秋の気配が深まるにつれて、土御門邸の有様は、言いようもなく趣深い。池のあたりの木々の梢や、遣水のほとりの草むらが、それぞれの色あいで一面に色づきわたって、あたり一帯の空の様子の美しさに引き立てられて、不断の御読経の声々が、一段としみじみと聞こえてくる。しだいに涼しくなる風の気配に、いつもの絶え間ない遣水の音が、一晩中、不断の御読経の声々と混じって聞こえてくる。
秋の気配が深まって、庭の木々が紅葉しているので、この冒頭の季節は、八月の半ば過ぎだと考えられる。僧たちの不断経の声々を引き立てているのは、この季節の空であると考えられる。『源氏物語』の八月後半の場面にも、空がしみじみと趣深いと描かれている。『源氏物語』から、三例引用する。
「宿木」の次の場面は、匂の宮が夕霧の六の君のもとを訪れる箇所で、八月十七日のものである。匂の宮は、「日が暮れてしまう」と思って、夕方のうちに寝殿に渡っている。
暮れぬれば、夕つ方寝殿へ渡りたまひぬ。風涼しく、おほかたの空をかしきころなるに、(⑤四一二)
「夕霧」の次の場面は、「八月中の十日ばかり」の情景で、空が美しく、水が澄んで、風の音が聞こえ、読経の声が尊く聞こえる点は、この冒頭とよく似ている。
【イチオシ記事】あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。初めて体を滅茶苦茶にされたときのように、体の奥底がさっきよりも熱くなった。
【注目記事】急激に進行する病状。1時間前まで自力でベッドに移れていたのに、両腕はゴムのように手応えがなくなってしまった。