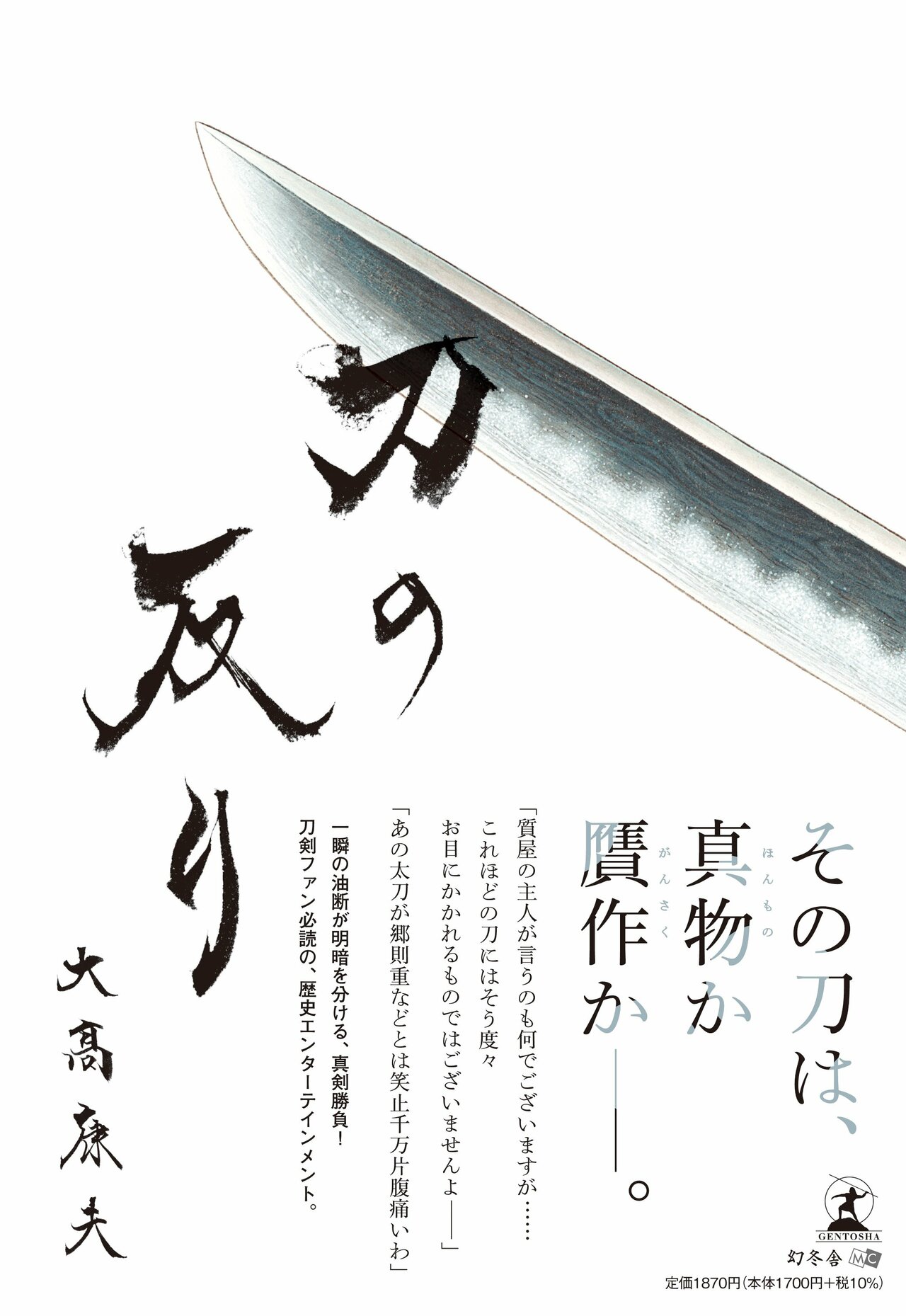潜(くぐ)り戸の前に立つと猛之進は暫し躊躇(ためら)いを見せていたが、長い息を吐くと思い切ったように屋敷の中に足を踏み入れた。玄関先に立ち主人が戻ったことを告げるまでもなく、気配を知った若党(わかとう)の太一郎が間を置かずして現れた。
太一郎はこの家に長く居る若者で、猛之進とは子供の頃から一緒に育った弟のような存在であった。若党は士分とはいえ、家の奉公人に近い存在である。隠居した父の仁左衛門の代に仕えていた与六という奉公人の息子で、与六が亡くなるとそのまま須田の家に若党として仕えることになったのだ。
「旦那様……何かあったのですか?」
猛之進の尋常でない雰囲気を感じ取ったのか緊張した様子が在り在りと顔に出ている。
「よい……心配いたすな」
「は……しかし……」
「どちらにしても明日の朝にはわけを知ることになろう。今宵は下がって休め」
太一郎が持ってきた水桶で足を洗っていると背後から妻の瑞江の声がした。
「おまえ様、こんなに遅い時刻まで……何かあったのですか」
猛之進は上がり框に立つと眉を顰(ひそ)める瑞江の顔をじっと見詰めた。
「たった今、人を斬ってきた」
「何があったのです。お斬りになったのは一体誰なのですか」
刀も預けず足早に奥の部屋に向かう猛之進の後ろを歩きながら、気丈にも瑞江はそう訊いた。猛之進は座敷に入ると忙しげに大小の刀を刀掛けに置き、出し抜けに瑞江の手を取った。
「来い……瑞江」
「……」
猛之進が寝間の襖を開けたとき、瑞江は主人の心意を汲み取った。部屋にある行灯(あんどん)には既に火が灯り、そこに敷かれた夜具を艶かしく照らし出していた。
「おまえ様……只今身支度をして……」
「身支度などせずともそのままで良い」
猛之進はそう言いながら息遣いも荒く袴を脱ぐと、瑞江を布団の上に押し倒して帯も解かず着物の裾を捲り上げたのである。