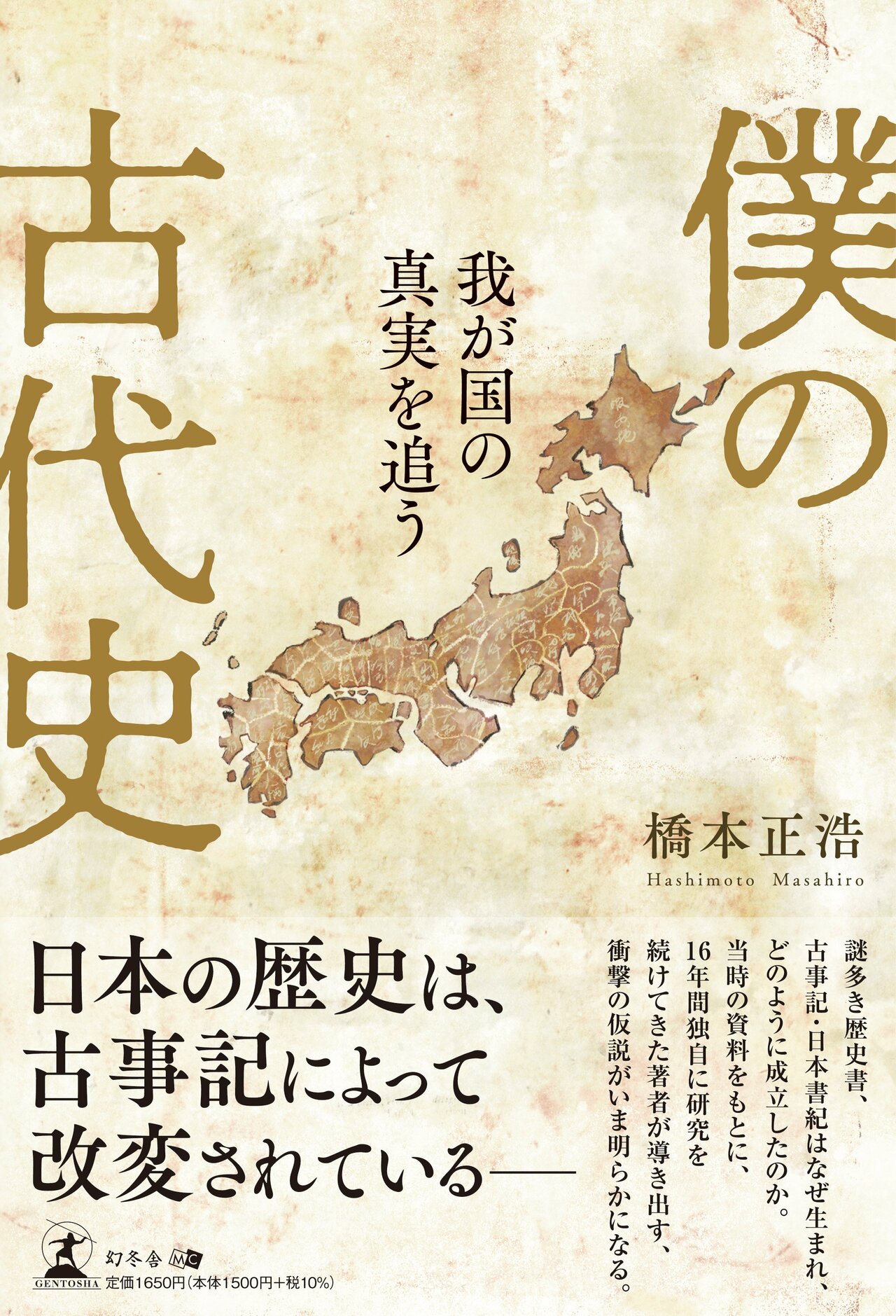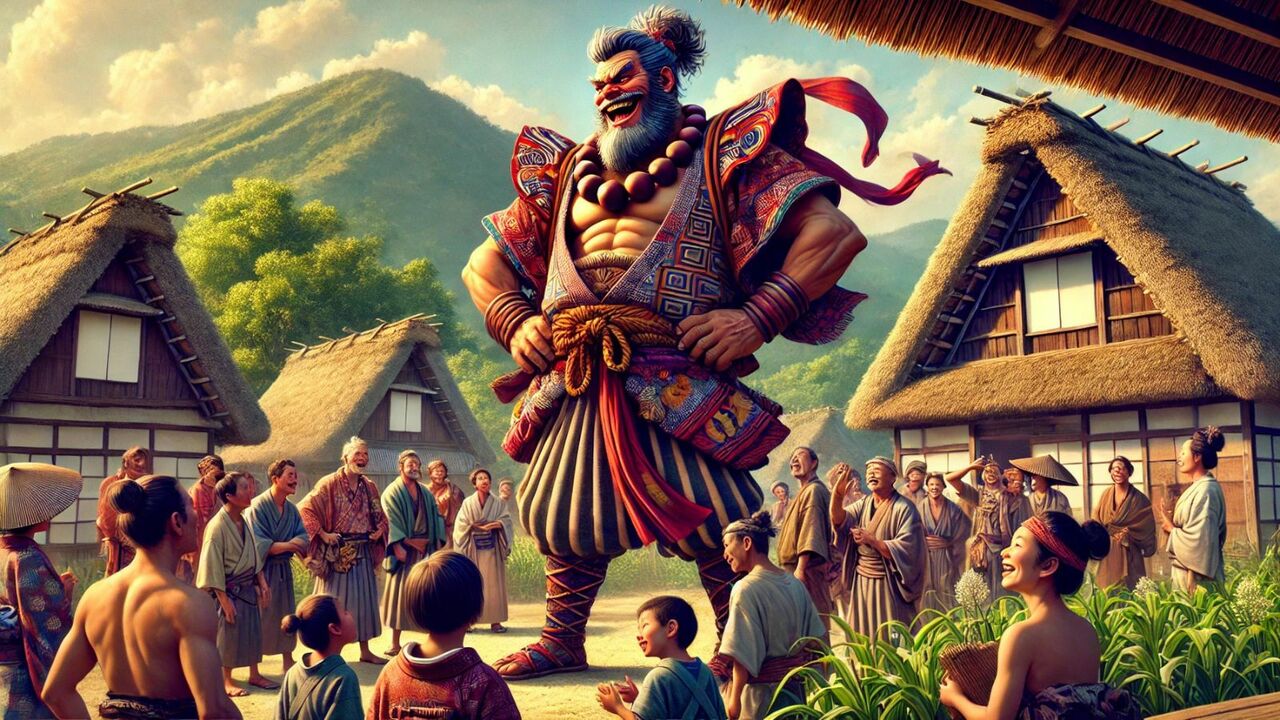その後AD7世紀初頭に我が国のタリシホコは隋の煬帝に対して対等交流をしましたが、この隋もやはり鮮卑族の王朝なのです。タリシホコの煬帝に対する書面を見ると、以前からの倭国の流れを受け継ぐ姿勢を貫いているように見えます。当然我が国のポリシーとして朝貢などは考えられない相手だったのです。
「日出ずる処の国の天子が書を日没する処の天子に致す、恙(つつが)ないか、云々」の書き出しは見事にこのポリシーを表現しています。鮮卑族の王朝が天子を名乗るのならば、我々も天子を名乗るよ、と言っているようで、やはり我が国のそれ以前からの姿勢を引き継いでいます。
タリシホコも亦、倭国のポリシーを引き継いでいたのです。
日本国を唐に認めさせた時の旧唐書の一文に次の一節があります。
「その人、入朝する者、多く自ら矜大(きょうだい)(誇り高ぶる・尊大)、実を以て対えず。故に中国焉(こ)れを疑う」(「旧唐書倭国伝」 石原道博編著)はまさにこの我が国の鮮卑族の国家である唐に対する意識の表れでもあるのでしょう。
日本国も倭国のポリシーを引き継いでいたのです。日本国も倭国の王朝から出たと思われるのです。
我が国の古代王朝は、漢王朝の流れを汲む王朝にのみ、歴代朝貢していたのであって、中国の王朝全てに朝貢していたのではなかったのです。
隋・唐の時代になると、我が国の中国王朝に対する朝貢外交は終わりを告げていたのでした。
五.倭国誕生・大王(おほきみ)による地方分権時代
一方、このような8C以前の我が国の歴史の流れの中で、我が国の内を見れば、AD1世紀、我が国は後漢書に見られるように、九州にあった奴国が紀元1世紀中頃に、倭の国王(何国かは不明)の師升がAD2世紀初頭に、それぞれ後漢の光武帝と安帝に朝貢をした、と後漢書に見えます。
この奴国が光武帝から下賜された金印が後に志賀島で発見され国宝となっています。この後、魏志の倭人伝によると、邪馬壹国の卑弥呼が二三八年に漢の流れを汲む魏の明帝に大夫の難升米を使者として送り朝貢したとあります。
同じく倭人伝にはこの邪馬壹国の卑弥呼が狗邪韓国以下、奴国までの二十九国に女王として共戴されていたと記しています。
この二十九箇国の比定地の分布に関して九州内なのか西日本に及んでいるのかで、邪馬壹国が九州なのか近畿なのかに分かれて主張し合い混乱していますが、卑弥呼が魏帝から下賜された絹織物や、鉄器などの出土状況から見て、邪馬壹国は九州にあった(「風土記にいた卑弥呼」古田武彦著)と思われます。
【前回の記事を読む】【古事記・日本書紀】屯倉と國造…同じ役割なのに違う呼び名―!? その鍵は、王権に従いも滅ぼされもしていない豪族たち!
【イチオシ記事】喧嘩を売った相手は、本物のヤンキーだった。それでも、メンツを保つために逃げ出すことなんてできない。そう思い前を見た瞬間...