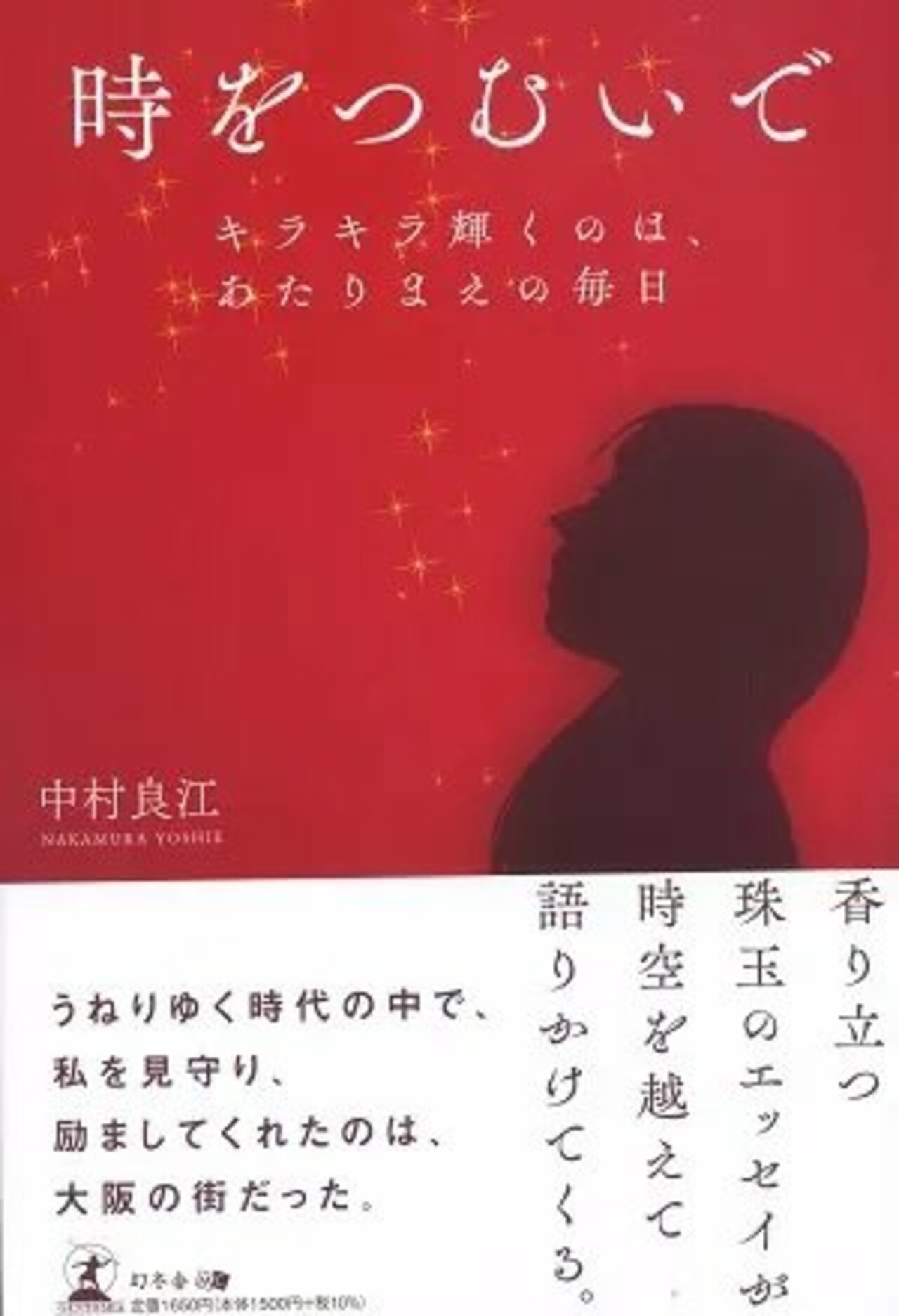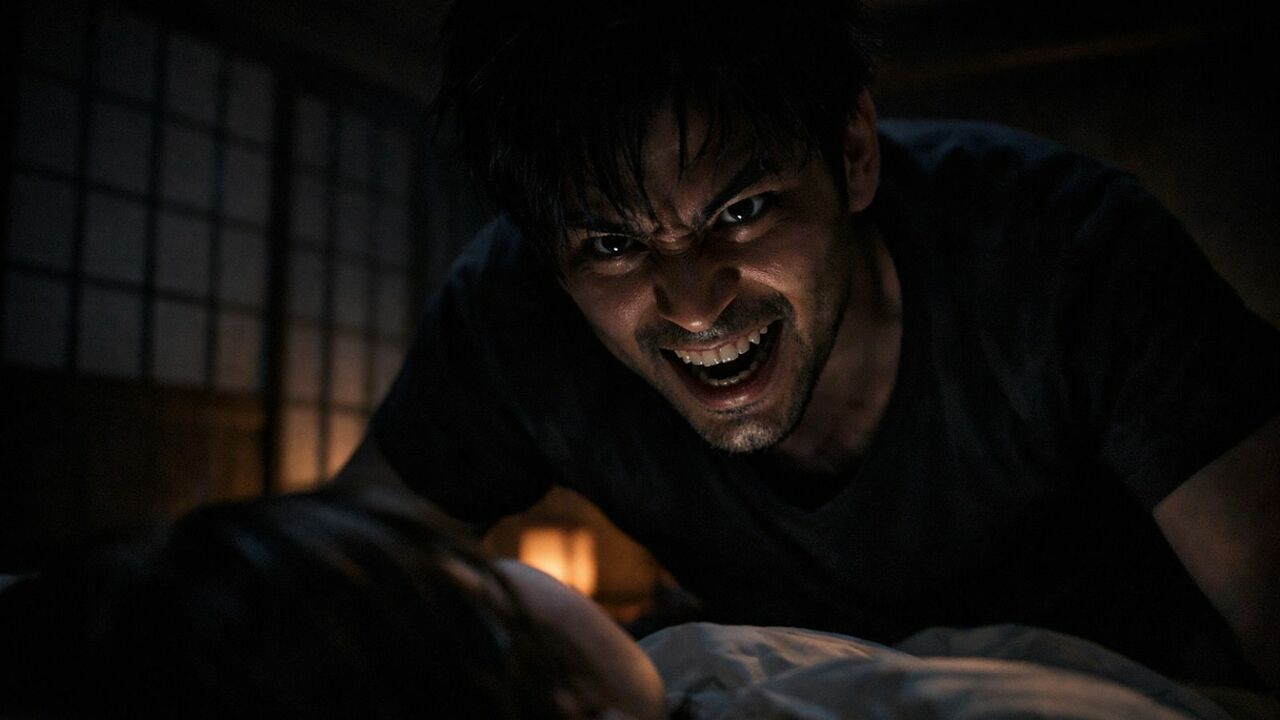第2章 戦時中から戦後の生活
1 女学校時代
造兵廠壊滅
警報が解除になると、私たちは必死に逃げて来た道を、また造兵廠に向かって歩き出した。午後四時もとっくに過ぎていただろうか。造兵廠の門の辺りには、爆弾でえぐられた直径10メートルぐらいのすり鉢状の大きな穴が幾つもできていた。
そして廠内は徹底的に破壊され、焼き尽くされ、沢山の人が死んでいた。「ひと足違いで森の宮のガードを越せなかった人らは、逃げおくれて死んだらしいわ」そんな話が伝わってきた。
「あの日、朝子はもうあかんと思うた」と、後日父が親類の人に話しているのを耳にした。
学校へ戻る
終戦と共に学徒動員から焼け残った学校へ戻ったものの、暫くはまともに勉強ができる状態ではなかった。戦後の混乱期、日本人は衣、食、住にこと欠き世間は失業者であふれた。徴用にとられて造船所で働いていた父も敗戦と共に職を失った。とても元の呉服の商いができるわけがなかった。
最悪な食糧事情の中でもヤミ市の露店では法外な高値で何でも売っていた。「住吉公園で、薄いお粥(かゆ)を茶碗一杯いくら(値段は忘れたが)で売っていた」と、近所の人が話すのを聞いて「お粥(かゆ)まで売るとは」と私は驚いた。
焦土と化した大阪市内は市電が止まり、南海電車を難波で降りてから三十分ばかり歩いて学校に通った。途中、心斎橋筋では焼け跡にバラックながらボツボツと店が建ち、復興の兆しが見えはじめた。学校でも、少しずつ勉強ができるようになった。
戦後になって初めて敵性語と禁じられていた英語を習った。国語の授業はまことに魅力的だった。わら半紙の粗末な教科書に出ている『奥の細道』を、くり返しくり返し暗唱した。数学が苦手の私が、なぜか図形の授業は面白くて仕方なかった。紙質の悪いノートに、少しでも紙を節約しようと小さな小さな字を書いた。