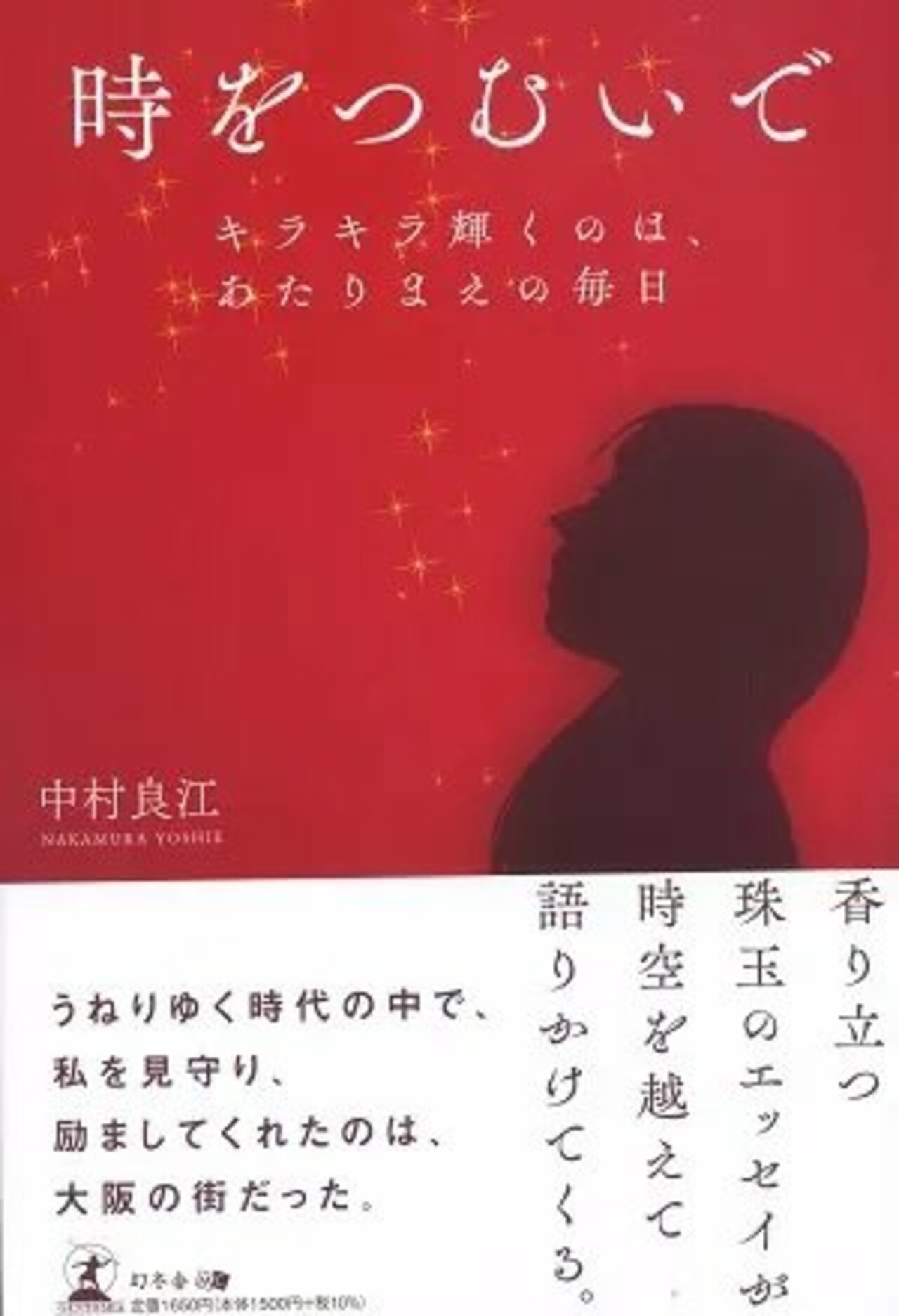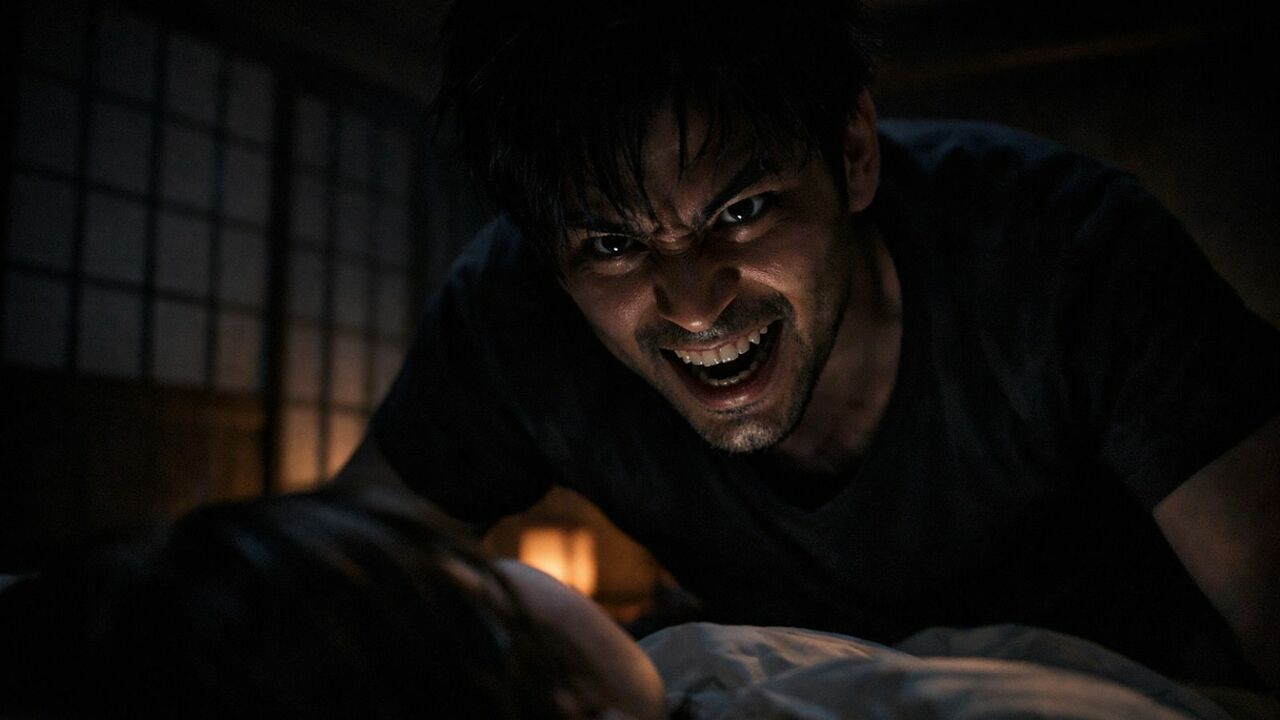【前回記事を読む】2度の自転車泥棒に、新品を盗まれ…ヤミでどっさり儲けている家もあるだろうに、どうしてこう貧しい家を狙うのか。
第2章 戦時中から戦後の生活
3 大八車の旅
自転車泥棒
かつて弟は、行きたくても学校へ行けなかった。今では登校拒否をする子のために、親や先生がその対策に苦慮しているという。
朝日新聞の「天声人語」に、「アメリカの子供たちの読み書きの教育のために、日本の人の援助を期待している」という信じられないような記事が載っていた。戦勝国で豊かなアメリカ、敗戦国日本という意識が、今も頭のどこかにある戦中派の私にとって、まさに驚き以外の何ものでもない。世の中の移り変わりをつくづくと感じたことであった。
5 高田薬品時代
昭和二十三年の春、道修町にある高田薬品に就職することができて営業部第三課に勤務することになった。課員は十五名でそのうち女性は私より七つ年上の牧田さんと、結婚で退職した人の後に入った私の二人だけだった。
毎朝仕事が始まる九時よりも十五分ぐらい前には出社して、牧田さんと一緒に全員の机の上を固く絞った雑巾で拭き、次々と出勤してくる人たちにお茶をいれて配る。それが一日の仕事の始まりだった。
課それぞれの担当者から回されてくる、特約店からの注文の薬品名と数量を、出荷伝票に記入して倉庫係へ回すのが私の主な仕事で、その他にも来客のお茶の接待や、様々な雑用で忙しかった。けれど家と学校の暮らしだけしか知らなかった私には、何もかもが目新しく新鮮で、毎日を張り切って過ごしていた。課の人たちもみんな親切だった。
昭和二十三年といえばまだまだ戦争の後遺症を色濃く引きずっていたころで、食糧をはじめすべての物資は欠乏していた。そんな中で会社から弁当代わりにと、一人に一個ずつ配られるコッペパンは有り難かった。まだそんな時代だった。
会社の近くのビルの入り口の脇(わき)で、付近のサラリーマンたちの靴を磨いたり、修理をしたりしている靴屋のおじさんがいた。顔見知りになったこのおじさんにある時、「私、新しい靴が欲しいんやけど……」と話しかけると、「まかしとき。わしがええのんこしらえたげるよってに」といって、早速紙に鉛筆で私の足の型をとった。
「いくらぐらいするの」と聞くと何と私の給料の二カ月分だという。びっくりした。「そのかわり本革(牛革)のええのんやでぇ。二回に分けて払うてくれたらええ」とおじさんはにこにこして言った。