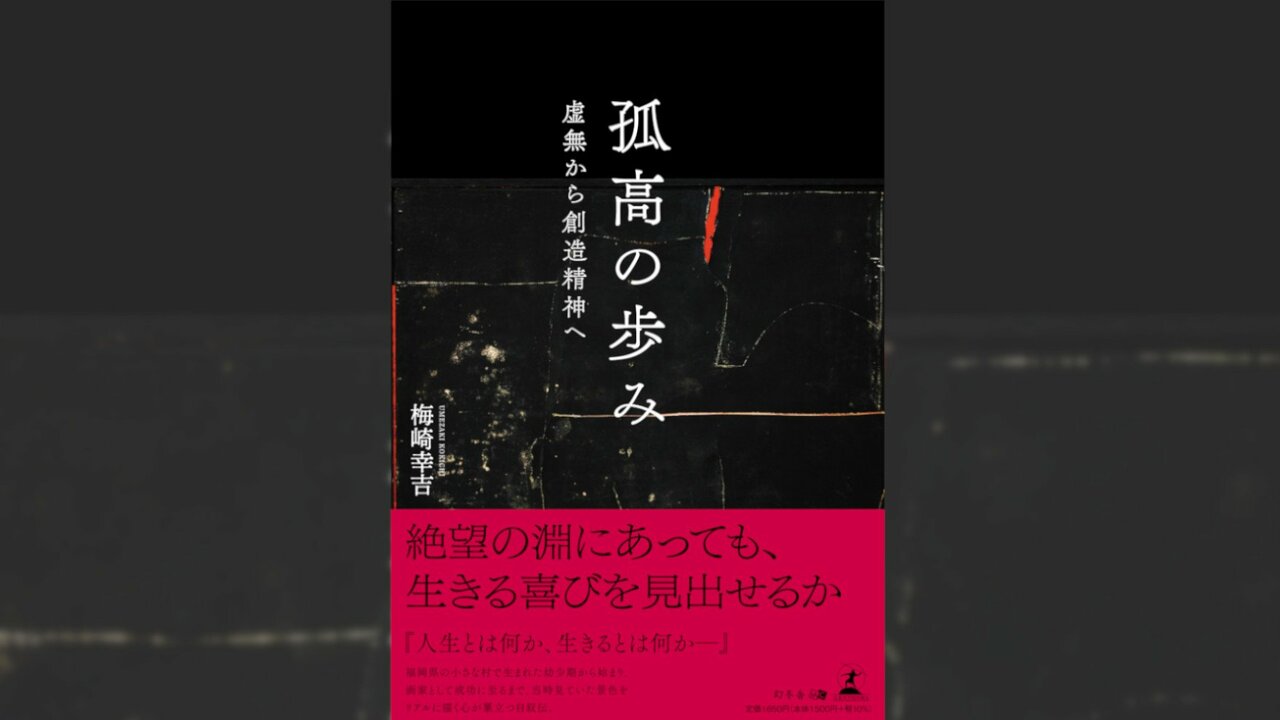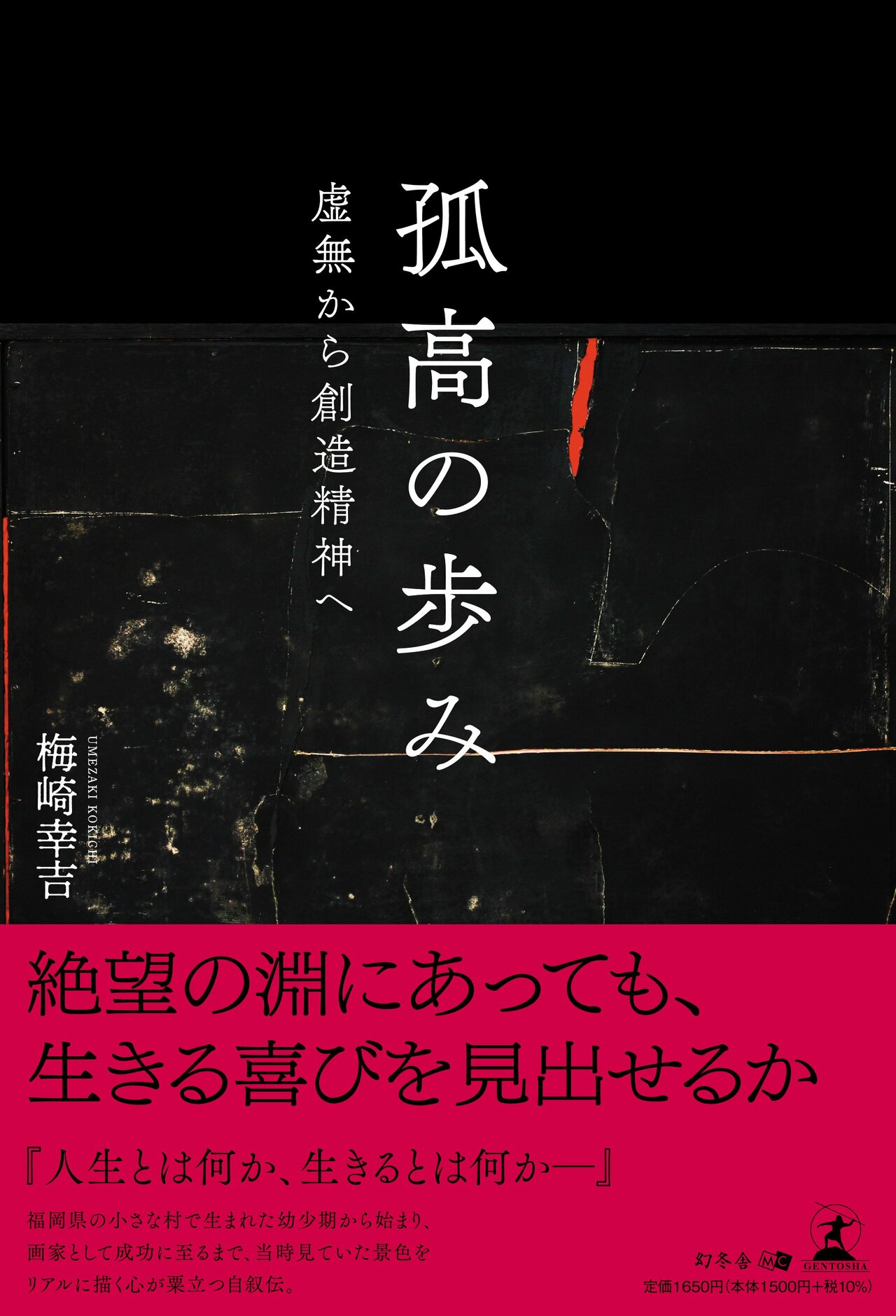一、
弟は村で差別された分、学校では同じ村の子供を喧嘩で押さえ付けていた。いわゆるガキ大将であった。
冬はさらに厳しい生活となった。犬のクロも自活を強いられた。当然、村人にとっては犬も私達と同じく、村のものを盗むよそ者であった。村人達にとっては誰が盗ったか分からぬものは全て私達の仕業(しわざ)になった。義祖母の凄い剣幕は、もう村人を怯えさせることはなかった。
兄は学校の先生に気に入られていたし、弟はガキ大将であったが、私は内気で無口な子供を意識的に演じていた。
私は誰かに怒られても、何か文句を言われても一時間でも二時間でも無言でいることなど何でもなかった。嘘泣きして涙を流すこともできたのである。私は周囲に抵抗するにはまだ幼すぎた。無言が唯一の抵抗であった。
納得できないものに対しては徹底的に無言を通した。皆、私の事を少し知能が足りないと思っていた。むしろ私にはそう思われていたほうがよかった。周りの人間は子供でも大人でも人間の姿をしている限り、私にとっては信じられる存在ではなかった。
誰も彼もが力関係で動いていた。私はその関係を弱肉強食と名付けた。この原理はまだ当時の私の中では観念的な言語化はできなかったが、この世界を支配する唯一のものと確信していた。
私達に対する同情がなかったわけではない。村に、よその町から来た嫁がいた。村には共同風呂場があり、十数軒が持ち回りで風呂を焚いていた。脱衣場は別でも木造の風呂は混浴であった。
一畳ほどの風呂桶には町から来た嫁は夜遅くに入りに来ていた。羞恥ゆえである。最後に入る者は浮かんだ湯垢をすくって入らねばならない。それでもその嫁は人が入り終わった頃に来る。
その嫁などが、夜中にこっそりと自分の家では食べない野菜のクズを置いていくことがたまにはあった。無論、見つかれば私達ほどではないが同類と見なされるからだ。
ある時、駐在所の若い警官が牛乳を二本持ってきてくれた。若い彼は同情的正義感に動かされたのだろう。
私の母は色白のふくよかな体形で男好きのする顏立ちであった。私は母が居酒屋で働いているのは分かっていた。恐らく、飲み屋ではさぞもてたに違いない。