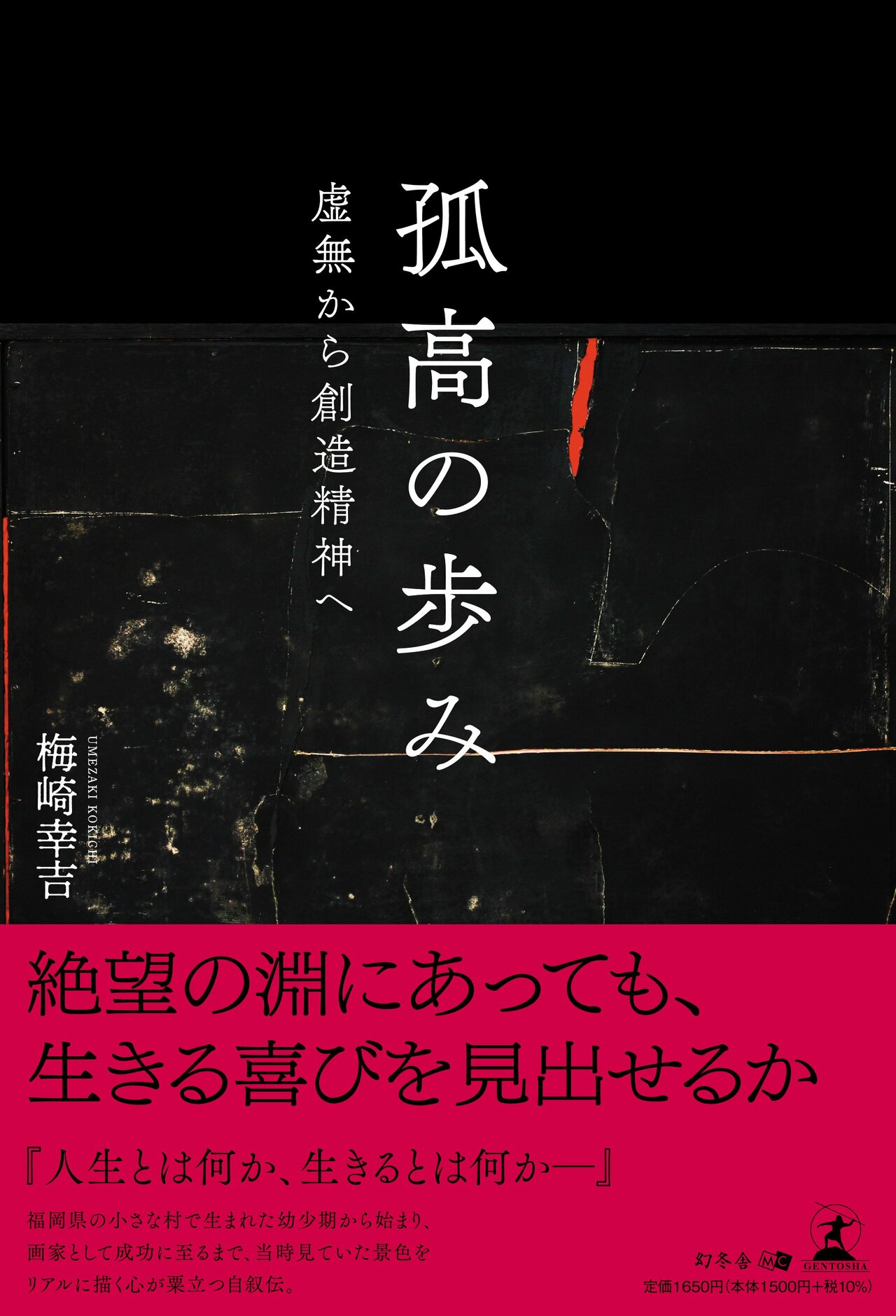母は気紛れか、或いは嫌なことでもあったのか、たまに家に帰ってくる。しかし、帰宅しても家にいるのは、せいぜい四、五日である。その間に複数の男が家を訪ねてくる。
相手によっては母は居留守を装うために私達を使った。「これはお父さんには内緒だ」と私達に少しの小遣いを渡した。
夜中に酔っ払って来る男もいたが、「ほっときなさい」と言って布団をかぶる。すでに布団の中は綿が千切れてぼろぼろである。雨の時は家中雨漏りだらけである。畳も腐って斜めに傾いている。藁ぶき屋根の古家でもあり、手入れをする者がいないと傷むのも早い。
母は、いつの間にか家からいなくなっていた。また、いつ帰ってくるかも分からなかった。私の家が隣の農家の借地であるということも村人に教えてもらった。それも、毒を含んだ口調で、である。
私には何よりも愛犬クロと自然が支えだった。自然は村人のように干渉はしない。私は稲妻や地震、洪水が好きであった。天災は全てに対して公平だからであった。
洪水の風景の最初の記憶は私が三歳の時である。弟が二階の柱に縛られていて、村中が流れる泥水湖のようになった。死んだ牛、豚やヤギ、鶏、壊れた家具類などが流されていた。
自宅の小さな庭の桐の木の細い小枝にはたくさんの蛇が巻き付いていた。毎年のように起こる洪水で泥水湖になった村に、町の消防団の人が船を漕ぎ、おにぎりを運んでくる。そのおにぎりの味は特にうまかった。
私達は冬でも夏の格好であった。足は裸足である。家には塩すらない。一度もらったタマネギを水煮で食べたことがある。だが口に含んでも不味い、それで無理に飲み込んだら胃が受け付けずに吐いた。その時はまる三日間何も食べていなかった。
水だけはいくらでも飲めた。家の狭い庭に井戸があったからだ。尤も、私達は川の水を飲んでも平気であった。すでに、半ば野生化していたのだろう。
兄の病弱な身体も極貧のなかにあって丈夫になったのだから。そのような生活のなかで、私だけは同学年の中では一番太っていた。
【前回の記事を読む】「よそ者」を受け付けない村社会。入院した父と、失踪した母、残された子供たちを待ち受けていたのは...