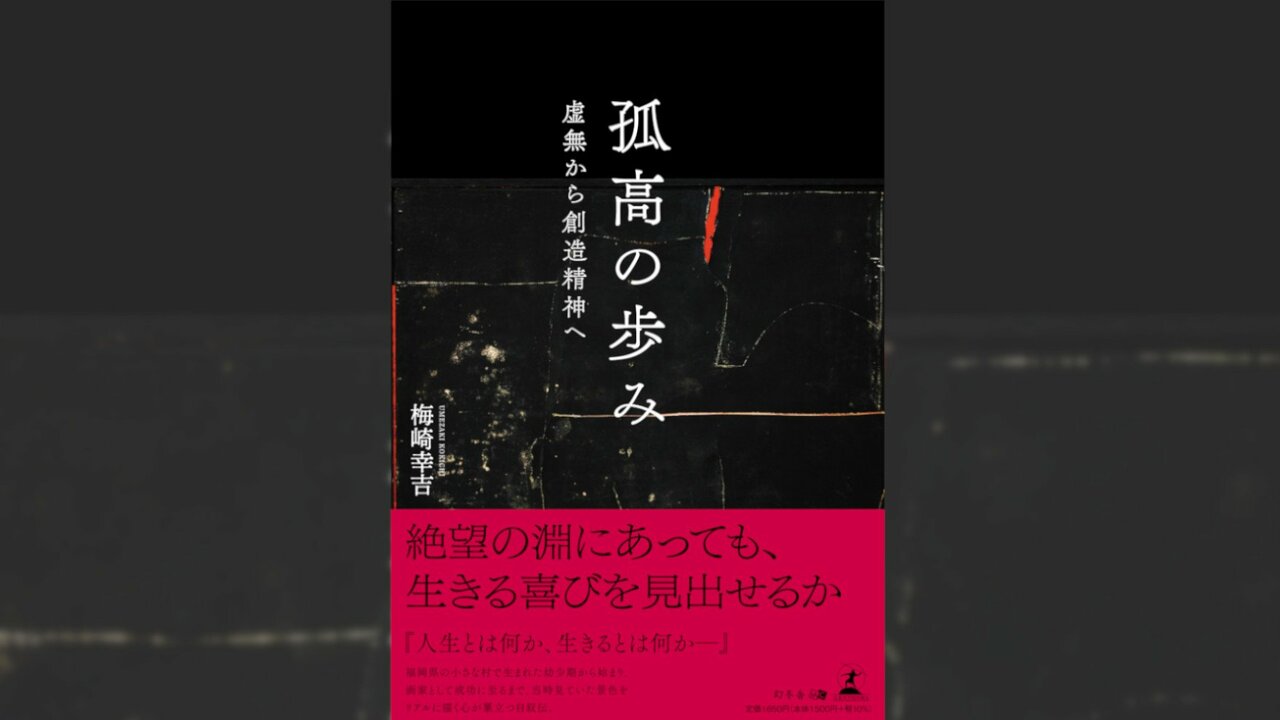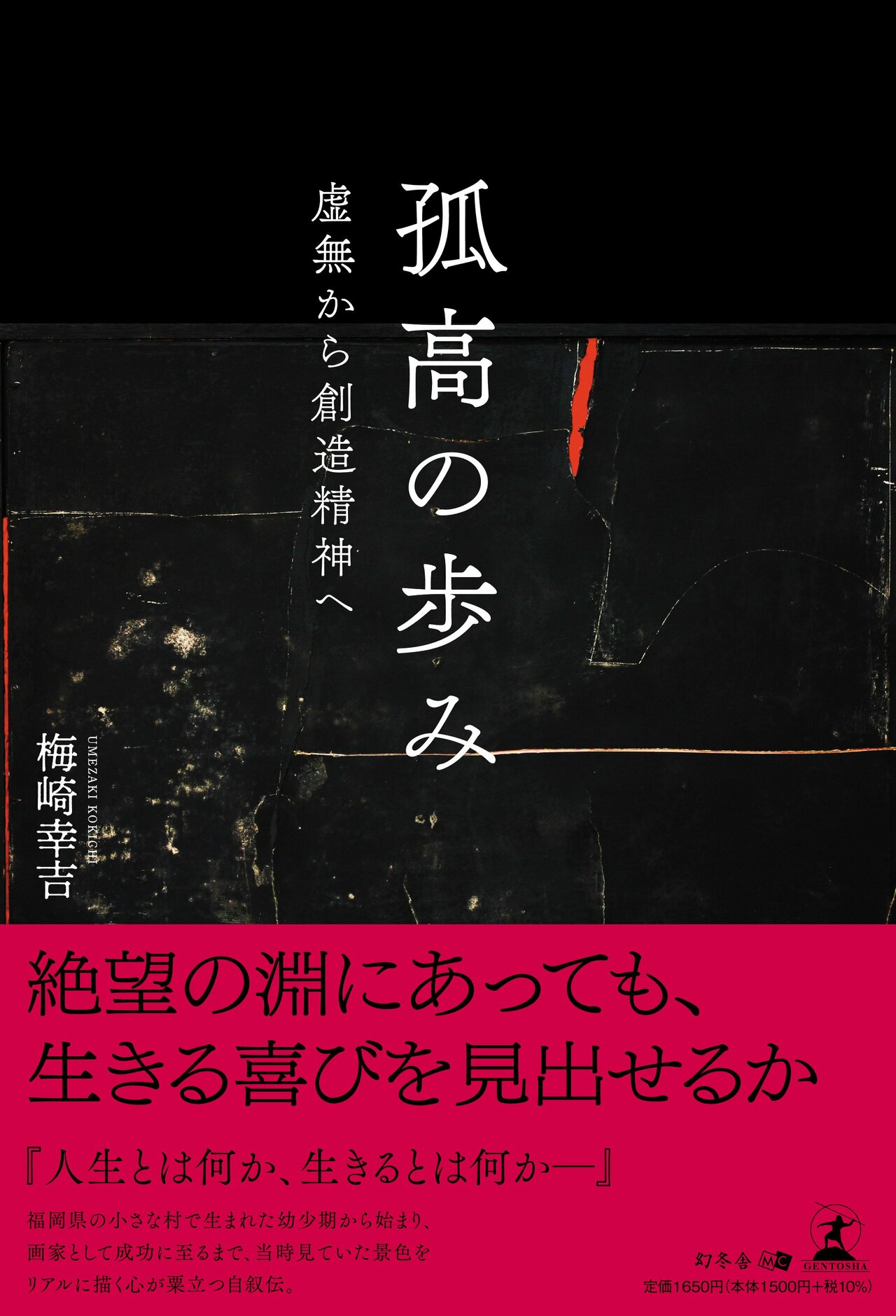一、
春になれば食えるものは柳虫、ザリガニ、雷魚でも何でも食べた。だが、さすがに蛇は食べたことがない。私達兄弟は単に獸のように飢えていたのだ。
ただ、普通の人間にある日常的感情は私には希薄であった。自分の欲しいものを手に入れることができなければ諦めるのは簡単であった。始めからないと思えばよかったのである。
私のこの合理的なものの考え方は幼い頃からすでに備わっていた。始めからないものであれば私の個人的な感情も起こらない。私はいわゆる人間の感情というものがよく理解できなかったし、少しでも私自身から生じる感情の出現自体がすこぶる不快であった。
何で他人は些細なことで感情的になるんだろう?と。だが、他人と一緒のときは私も皆と似たものを出さないと逆に目立つ。私は他人からの干渉を極度に嫌ったのである。私にはその頃から客観性の強い個人主義的相対的意識が動物にも似た形で天性のものとして備わっていた。それをはっきりと自覚したのは両親の離婚を通してであった。
母は、父が完全に精神的病いが治っていない時に離婚を迫った。父と母は何度もお互いを罵(ののし)りあった。私はその光景を嫌というほど見せつけられた。子供の立場ではただ成り行きを見るしかなかった。母には男がいた。それも二人の子持ちの男である。離婚が成立してもまだ父は未練があるようで苦悩していた。
私の意識の内では、一晩で自分の母は単なる他人となった。これは誰もが信じ難いと思う。まだ十歳の子供が簡単に母親を他人とみなせるかと。
しかし、私には実に簡単な意識の操作であった。私にとって親は、子供の面倒を見る限りはどんなことをしても親である。他の男と寝ようが泥棒しようが、さらに言えば人殺しをしても子供の面倒を見る限りは、私にとっては親である。だが、捨てるとなれば話は全く別である。
それまでは私が女に一番可愛がられていた。太った色白の大人しい素直な子供で、体温の高い私を女は湯たんぽ代わりに抱いて寝ていた。
私の本性を、女は全く見抜けなかった。女にとって自分の見栄と貧乏に対する嫌悪は当人にとって離婚の原因とはなっても、私達を捨てる理由とは全く関係のないことである。私は自分を育てる限りにおいて親とみなす。だが、子供を捨てれば、すでに親ではない。
私は他人となった女に執着する父の心情が分からないわけではなかった。それで一緒に演技で泣いた。私を引き取った父に私は同情しなければいけない、と自分で判断した。無論、一度きりではあったが。
父は私と兄を引き取ったので、すぐにでも仕事をしなければならない。だが、近辺では仕事はあまりなかった。木工所のかんな削り程度の仕事でも当時は少なかった。